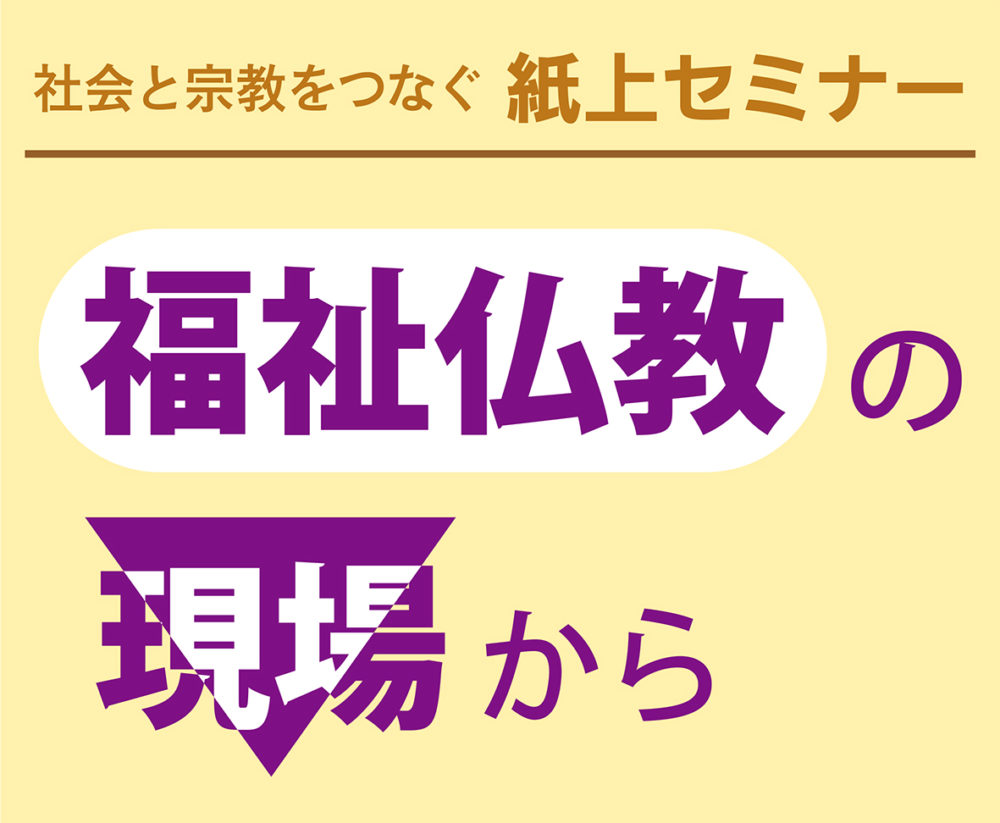インタビュー
橋渡しインタビュー
【東日本大震災15年】原発の記憶をアート作品に
2026年1月2日 | 2026年1月3日更新
東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の記憶を伝える「おれたちの伝承館」が2023年、福島県南相馬市に開館した。原発の記憶をアート作品にとどめる常設展示が行われている。館長の中筋純さん(59)は13年から同県浪江町の写真を撮影。福島と東京の2拠点生活を送りながら、風化させてはならない記録を撮り続けている。(飯塚まりな)
JR小高駅から徒歩5分。平坦な道のりを歩いたところに、「おれたちの伝承館」はある。ガス水道設備の倉庫だったという建物には、福島ゆかりのアーティストをはじめ、さまざまな作家の作品が展示されている。
同じ敷地内にあるコンテナには、今も放射線量を測る線量計が設置され、元原発作業員の人がボランティアで山に生えるキノコを収穫し、測定しているという。
館内に入ると、一枚の写真が目に飛び込んできた。防護服を着た男性が、先祖の遺影と傾いた仏壇を背景に写っている写真だ。表情はよく分からないが、不安と冷静さの入り混じった強い眼差しを感じる。

吹き抜けを利用して、巨大な天井画が展示されている。笛を吹く女性や馬、魚など南相馬市を連想させるモチーフが、幻想的で豊かな色彩で描かれている。
1階には、手のような形の彫刻がある。「鳳凰」の翼をイメージしており、力強く天に伸ばして何をつかもうとしているように見える。どちらも福島県出身のアーティストによるものだ。
館内では、畳の上で寝転がりながら作品を鑑賞することもできる。どこか荒々しく、まぶしい照明に映えるポップな色合いが、他の美術館にはない刺激を感じさせる。

「生温かさ」が残る被災地
中筋さんは18歳で上京し、出版社に勤めていた。30歳でフリーのカメラマンになり、1986(昭和61)年のチェルノブイリ原発事故から21年後のウクライナで、撮影を行った。事故当時のまま残る旧ソ連の風景と「時間の経過」を、写真に収めた。
4年後、東日本大震災で原発事故が発生し、ショックを受けた。2013年、帰還困難区域になった市町村へ撮影許可を願い出たが、唯一許可が出たのは浪江町のみだった。町長の計らいで、カメラを手に街の中を歩いた。
誰もいなかった当時の浪江町には「生温かさが残っていた」という。「チェルノブイリの撮影では、すでに年月がたっていたため、人の気配はなかった。でも、浪江町にはまだ人の気配や生活臭を感じて、今にも誰かに会うような気がした」
始まりは「もやい展」
その後は全国で自ら写真展を開催。たくさんの来場者の目に触れたが、震災の現状をつらくて直視できないという声もあった。そこで、アーティストたちに声をかけ、震災や原発事故をテーマしたアート作品を展示する「もやい展」を企画した。
絵、写真、彫刻、言葉などを通じ、作家たちのさまざまな思いがいくつもの表現になった。共感する人が増え、いつでも気軽に鑑賞できるギャラリーを作りたいと「おれたちの伝承館」の構想が持ち上がった。
南相馬市小高区で旅館を営む小林友子さんが協力し、場所を見つけてくれたという。
現在は、誰もが気軽に入れるよう、定期的にイベントを開催しながら住民と交流している。
「原子力がいいか悪いかと議論するよりも、この場所で起きた大きな出来事をどう見届けるかを大事にしたい」と、中筋さんは作品を見渡した。

過去を振り返れる場所
すっかり南相馬市に愛着を持った中筋さん。「伝承館を建てたとき、『外の人間だからこそできる』と言われたのはありがたかった。心を開いて、震災のことを振り返れる場になれたら」と語った。
伝承館のある小高区の人口は、震災前で約1万4000人だったのが、現在は4000人ほど。避難指示区域に指定され、約5年間は住民の立ち入りが禁じられた。
戻ってきた人は高齢者がほとんど。「福島には戻らない」と話していたが、墓守の必要性から、故郷での暮らしを再開した人も出てきている。だが、子どもがいる若い世代は、他に定住先を見つけて生活が安定すると、ほぼ戻ることはない。

一方で他県からの移住者や起業家は年々増えている傾向にあり、東京などではできない挑戦を実現するには適しているともいう。
この先、福島から避難した子どもたちが大人になって、再びふるさとに帰ってくる可能性もある。どんなに変化しても、震災からの歩みを丁寧に記録し、芸術の力で伝えることが中筋さんの役割だ。