




つながる
福祉仏教ピックアップ

※文化時報2026年1月16日号の掲載記事です。 医療と仏教の協働について学ぶ西本願寺医師の会=用語解説=の第10回総会が、浄土真宗本願寺派本山本願寺(京都市下京区)の聞法会館で開かれた。医療関係者らの悩みに寄り添うことに焦点を当てた講演や討論が行われ、医師が医療現場で抱く苦悩を赤裸々に告白した。(奥山正弘) …
2026年2月19日

※文化時報2026年1月13日号の掲載記事です。 真言宗大覚寺派成福院(今井弘道住職、兵庫県宝塚市)は昨年12月14日、釈尊が悟りを開いたことを祝う成道会と、障害のある子を持つ親の分かち合いの場「親あるあいだの語らいカフェ」を開いた。参加者25人は、ダウン症で右手の欠損があるピアニストの鈴木凜太朗さん(34)に…
2026年2月17日

※文化時報2025年12月19日号の掲載記事です。 認定NPO法人抱樸(ほうぼく)(奥田知志理事長、北九州市八幡東区)は9日、東京都港区の明治学院大学で講演会「抱樸おんなじいのちのツアー」を開催した。約500人が聴講し、奥田理事長が2026年秋に北九州市小倉北区で開設予定の「希望のまち」について語ったほか、計画…
2026年2月15日

※文化時報2025年12月16日号の掲載記事です。 一般社団法人「親なきあと」相談室関西ネットワーク(藤原由親・藤井奈緒代表理事)は11月29日、大阪市立青少年センター(大阪市東淀川区)で開いた定例セミナーで、障害のある人の能力を開花させるシステム「シームレスバディ」を開発した障害者就労支援会社「ダンウェイ」(…
2026年2月14日

※文化時報2025年12月16日号の掲載記事です。 マルシェをきっかけに死別などのグリーフ(悲嘆)について知ってもらう「おかざきグリーフケアマルシェin本光寺」(実行委員会主催)が6日、愛知県岡崎市の真宗大谷派本光寺(稲前恵文住職)で開かれた。講演やコンサート、子ども・若者向けのワークショップなどが行われ、前回…
2026年2月12日

※文化時報2026年1月1日号の掲載記事です。 NPO法人これからの葬送を考える会九州は12月14日、事務局を置く日蓮宗妙瑞寺(菊池泰啓住職、大分市)で、「最期のかたちも人それぞれ~多様化する生き方の中での死と葬送」をテーマにした連続講座の第4回をオンライン併用で開いた。永代供養墓の草分けとして知られる日蓮宗妙…
2026年2月10日

※文化時報2025年12月9日号の掲載記事です。 龍谷大学世界仏教文化研究センターは、大宮学舎(京都市下京区)で国際ワークショップ「オランダにおける『仏教スピリチュアルケア(BSC)』プログラムの展開」を行った。大学、刑務所、軍で活動する3人の仏教チャプレン=用語解説=が、同国でのスピリチュアルケア=用語解説=…
2026年2月7日

※文化時報2025年12月9日号の掲載記事です。 障害のある子の親たちが情報交換して交流を深める「親あるあいだの語らいカフェ」が11月28日、鹿児島市の浄土真宗本願寺派妙行寺(井上從昭住職)で行われた。NPO法人CILひかり(鹿児島市)代表で、重度の身体障害がある川﨑良太さん(38)がゲストとして登壇。障害者の…
2026年2月5日
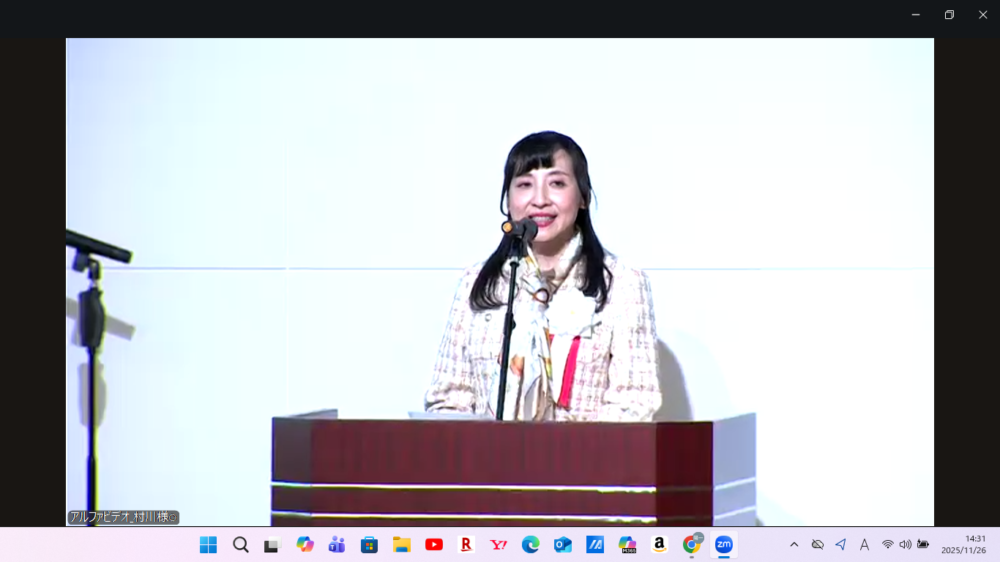
※文化時報2025年12月5日号の掲載記事です。 身寄りのない高齢者や障害者の身元保証と見守りなどを担う事業者が、業界の健全な発展とサービスの質の向上などを目指す業界団体として、一般社団法人全国高齢者等終身サポート事業者協会(全終協=黒澤史津乃理事長、東京都千代田区)を設立した。11月26日に東京都内で設立フォ…
2026年2月3日
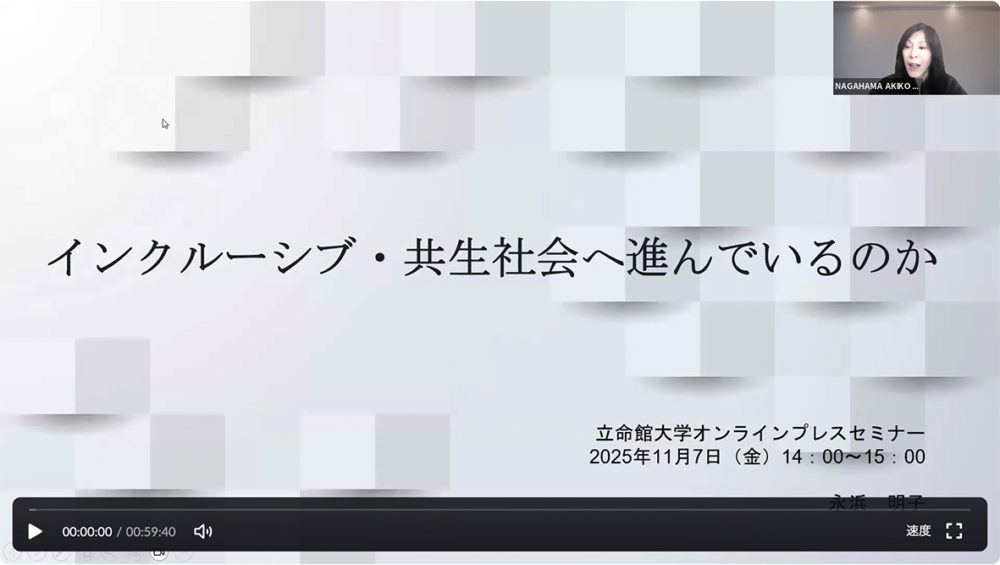
※文化時報2025年11月21日号の掲載記事です。 立命館大学(仲谷善雄学長、京都市中京区)は7日、障害の有無や性別、年齢などの違いにかかわらず、多様な人々を受け止めるインクルーシブ=用語解説=社会の本質をテーマに、報道関係者向けのオンラインセミナーを開催した。スポーツ健康科学部の永浜明子教授が「感動ポルノ」に…
2026年2月1日

※文化時報2025年12月5日号の掲載記事です。 東京都葛飾区の浄土宗香念寺が奇数月に開いている「介護者の心のやすらぎカフェ」が10年目に入った。介護の悩みや苦労を打ち明け、相談や情報交換する場になっており、最近では介護を終えた後の心中を吐露する人が多いという。下村達郎住職(43)は「同じ境遇だからこそ話ができ…
2026年1月30日

※文化時報2025年11月28日号の掲載記事です。 ユニークな活動をする僧侶らの話を聞き、地域社会について考える「第2回オモロー寺子屋発表会」が8日、大阪市天王寺区の浄土宗銀山寺(末髙隆玄住職)で開催された。登壇者5人がそれぞれの活動や地域との関わり方を発表し、参加者約20人が耳を傾けた。(坂本由理) …
2026年1月28日

※文化時報2025年11月28日号の掲載記事です。 「人生の終焉(しゅうえん)をデザインする」がテーマのイベント「医療デザインサミット」が9日、大阪府東大阪市の大阪樟蔭女子大学で開催され、医療・介護従事者とエンディング産業関係者ら約250人が参加した。主催は一般社団法人日本医療デザインセンター。同市で地域包括ケ…
2026年1月26日

※文化時報2025年11月25日号の掲載記事です。 京都府亀岡市の浄土宗光忠寺(齋藤明秀住職)は15日、十日十夜法要=用語解説=に合わせ、講演会「仏教と心理学からみた幸せ」を開催した。心理学者で浄土宗晴明寺(同市)の真田原行住職が登壇し、脳がどう働くことで苦を感じ、それを仏教がどのように解消していくのかを考察し…
2026年1月24日

※文化時報2025年11月25日号の掲載記事です。 社会課題に取り組む市民団体と、団体に土地や建物を提供する浄土宗寿光院(東京都江戸川区)・見樹院(同文京区)をつないで市民による活動を支える一般財団法人リタ市民アセット財団(藤居阿紀子代表理事)は9日、東京都内でシンポジウム「市民が社会を変える~自治するコミュニ…
2026年1月21日
