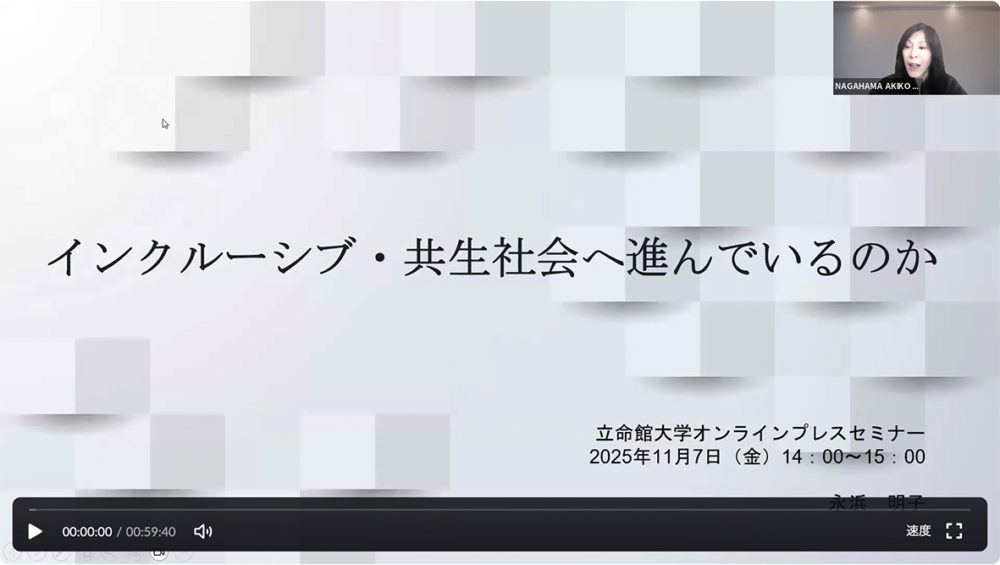つながる
福祉仏教ピックアップ
その名も「墓デミー賞」 お墓参りの作文表彰
2025年2月20日
※文化時報2024年12月3日号の掲載記事です。
お墓参りにまつわる作文と写真を通じてお墓と供養の大切さを見直してもらう「第5回墓デミー賞」(実行委員会主催)の授賞式が18日、京都府庁旧本館議場(京都市上京区)で行われた。いわゆる墓じまいなどの逆風を懸念した石材業者が、コロナ禍をきっかけに続けてきたイベント。約20人が集まり、受賞作品の朗読に聞き入った。(主筆 小野木康雄)

墓デミー賞は、コロナ禍で政府が緊急事態宣言を出した2020年にスタート。帰省の自粛が呼び掛けられ、お盆期間中でさえ墓参がままならない状況を懸念し、大橋石材店(神奈川県横須賀市)の大橋理宏社長が発案した。映画のアカデミー賞をもじった名称や「お墓版Go To キャンペーン」と称した遊び心を通じ、気軽にお墓参りに行くことを提唱してきた。
今年は作文と写真43点が寄せられ、最優秀賞と優秀賞3点が選ばれた。石材業者を通じてではなく、一般からの応募が目立ったという。
最優秀賞に選ばれたのは「月命日にラブソングを」を書いた神奈川県藤沢市の廣瀬純子さん(48)。音楽プロデューサーの夫=当時(52)=を今年1月にがんで亡くし、納骨のときにサックスを吹いて以来、月命日に墓前で楽器を演奏していることを明かした。お墓参りを「二人のデート」「音楽で対話をする泣き笑いの時間」とつづった。

授賞式では、応募写真で手にしていた弦楽器「バンジョー」の弾き語りを披露。「あなたと会えて幸せだったと、お墓の前で言い続けたい。そして、それを皆さんに伝えたい」と、涙交じりに受賞の喜びを語った。
受賞作品は全てプロのナレーターが朗読。故人への思いとお墓にまつわるそれぞれのエピソードが紹介され、会場は温かな雰囲気に包まれた。
審査委員長を務めた石材などの輸入卸を手掛ける孔雀(岡山県倉敷市)の藤原巧会長は「お墓参りはみんなが幸せになれる一つの手段。先祖のことなどをもっと考えられるような世の中になっていけば」と話した。
受賞作品はホームページで公開している。
供養と墓参の文化守る
墓じまいのニーズが高まり続ける一方で、弔いと供養の大切さはなかなか伝わらない。「墓デミー賞」は、一般の人からお墓参りのエピソードを集めて表彰・公開することによって、そうした社会状況に一石を投じた取り組みといえる。

厚生労働省の統計「衛生行政報告例」によると、墓じまいやお墓の引っ越しなどに伴う改葬件数は、2023年度で16万6886件に上った。13年度(8万8397件)に比べると10年間で約1.8倍になっており、前年度(15万1076件)に比べても約1万5千件増えた。
「家墓」と呼ばれる先祖代々受け継がれてきた石のお墓から、納骨堂や樹木葬などへと供養の形が変化してきたことも相まって、石材業界を取り巻く環境は厳しさを増している。
そうした中、大橋石材店の大橋理宏社長は、供養全般を視野に入れた事業を展開。契約者が死後お墓に入ったあと、一定期間墓守を続けて墓じまいまで引き受ける「お墓のみとり」を17年に始めた。墓じまいの生前予約サービスとして、全国に加盟店を広げている。
また、墓じまい後の墓石をアクセサリーなどに加工・再生して手元に残す「リ墓(ボ)ーン」も手掛けている。
これに対して「墓デミー賞」には、お墓参りを文化として守ることで、石材業界や供養業界を活性化させたいという願いがある。大橋社長は「同業者に注目してもらいたいのはもちろん、お墓参りの良さをアピールできるイベントとして、お寺さんにも関心をもっていただければ」と話している。