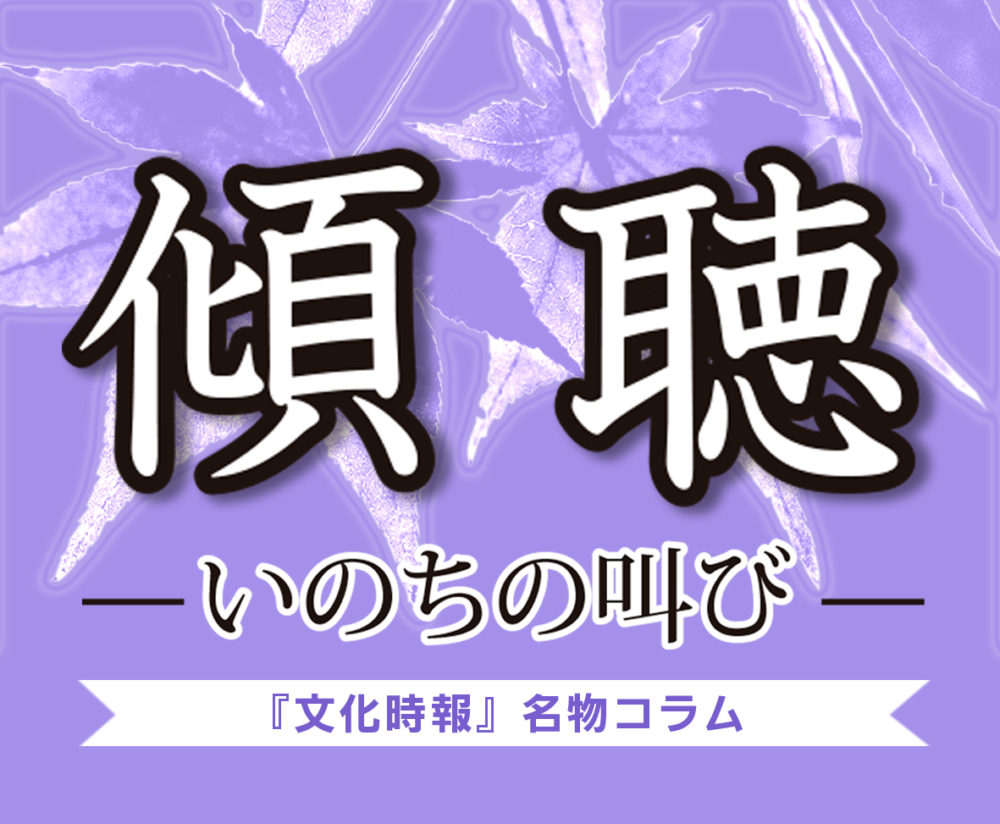知る
お寺と福祉の情報局
「あなた」と対話する 埼玉いのちの電話
2025年12月24日
悩みを抱えた人の救いになる相談窓口「いのちの電話」。昨今は有名人の自殺が報道される際、自殺防止のために併せて紹介される機会が増えた。電話に出るのは、研修を受けたボランティア相談員たち。どんな相談対応をしているのか。社会福祉法人「埼玉いのちの電話」事務局長の松井晴美さん(69)に聞いた。(飯塚まりな)

24時間365日、電話は鳴り止まない。取材日は2人のボランティア相談員がデスクにある受話器を取っていた。話を聞いていた。
「いのちの電話」の活動は、英国・ロンドンで行われていた自殺防止の電話相談を起源とする。日本ではドイツ人宣教師のルツ・ヘットカンプ氏が中心となり、1971(昭和46)年10月に東京でスタート。現在は全国50カ所に広がった。
埼玉いのちの電話は、93(平成5)年に35番目のセンターとして開設された。相談員の実働数は全国最多の317人が登録しており、現在は大宮、川越、越谷の3地区で活動を行っている。運営費用は共同募金、埼玉県などからの補助金や団体・個人からの寄付によって成り立っている。
年間の相談件数は2024年、約2万6千件に上った。1日平均70件以上が寄せられている計算だ。1件の応答時間は平均37分。電話の内容はさまざまだが、現在は「人生・孤独」「対人関係」「自身の病気」が多いという。
電話をかけてくる世代は主に40代と50代。仕事や家族関係で人生の岐路に立たされる人たちの声が届く。若い世代はメールで相談が送られてくるケースが多い。必ず1週間以内に返信を送っている。
相談員は具体的なアドバイスは行わず、批判もしない。親身に話を聞き、相手が気持ちを落ち着かせ、自ら電話を切るまでじっと待つ。
しかし、内容によっては自分の経験談などを話したくなることもあるという。
「たしかに、そういう気持ちと葛藤することがあります。電話を切った後に『今の電話は良かった』と相談員自身が満足したときほど注意が必要。その場合は、自分のことを話しすぎている可能性が高いです」。松井さんはそう話す。
電話から社会を知り、視野が広がった
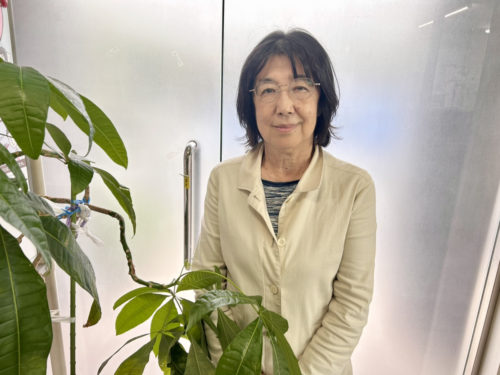
松井さんがいのちの電話に出会ったのは30年前。専業主婦で子育てに没頭していた際、ボランティア相談員をやらないかと声をかけられた。「私にできるだろうか」と思いながらも研修を受け、子どもが学校に行っている間に受話器の前に座った。
「飼っていた金魚が死んだ」と悲しむ小学生からの電話や、塾に行く前に必ずかけてくる学生の話にも真剣に向き合った。現在と比べて寄付金や補助金が少なく運営費もかかり、整った環境や設備はなく、メモを取る鉛筆も節約し、短くなっても最後まで使い切った。
電話口から聞こえてくる相談者の言葉から、松井さんは社会を学んだという。
「いのちの電話で自分の視野が広がりました。たくさんの方とお話しできたことがありがたかった」。専業主婦の生活だけでは得られない経験をさせてもらえたと、感謝の思いを持ち続けている。
研修は自分を知る1年半
ボランティア相談員を希望する場合は、1年半の研修が必須となる。講師には経験豊富なベテラン相談員たちも含まれる。
電話をかける役と相談員役を交代でロールプレイし、観察者が「なぜ、その問いをしたのか」「どうしてその言い方を選んだのか」などと尋ねてやり取りを振り返る。
指摘を受けて落ち込むこともあるが、その過程で自分の思考や口調の癖に気付かされる。単なる傾聴を学ぶだけでなく、自分を知って成長できる期間になるという。

特に強調されるのは「相手と対話する気持ち」。話を聞き終えた後は「あなたの思いを受け取りました」「話してくれてありがとうございます」と、相談員自身の素直な感情を伝えることが大切だと教えられる。
「私たちが、相談される方の世界に入っていくような感覚です。電話で生の声を聞けるのですから、気持ちのやりとりを大事にしています」と、松井さんは力を込めた。
「話を聞いてほしい」と思ったら
いのちの電話は、自殺を考えるほど追い詰められたときの「最後のとりで」だけではないという。松井さんは「私たちは決して、相談内容の大小を問いません。自分自身を追い詰める前にかけてきてほしいのです」と語る。

一方で、相談件数が多いため、電話をかけてもつながらないという現実もある。
遺族から「いのちの電話にかけた履歴が残っていた。どんなことを話していたのか教えてほしい」と問い合わせがくることがある。しかし、その多くはつながらなかった電話だ。「せっかくかけてきてくださったのに、とても残念なことです」と、松井さんは肩を落とす。
一本でも多くの電話を取るには、相談員の補充が欠かせない。だが、無償で交通費も支給されず、研修にも決して安くない費用がかかる。「やってみたい」と思っても、すぐに手を挙げられない人は多い。
それでも、心ある人には挑戦してほしい活動だ。新たな若い力も必要とされている。助けを求める人の電話がつながることを願いたい。