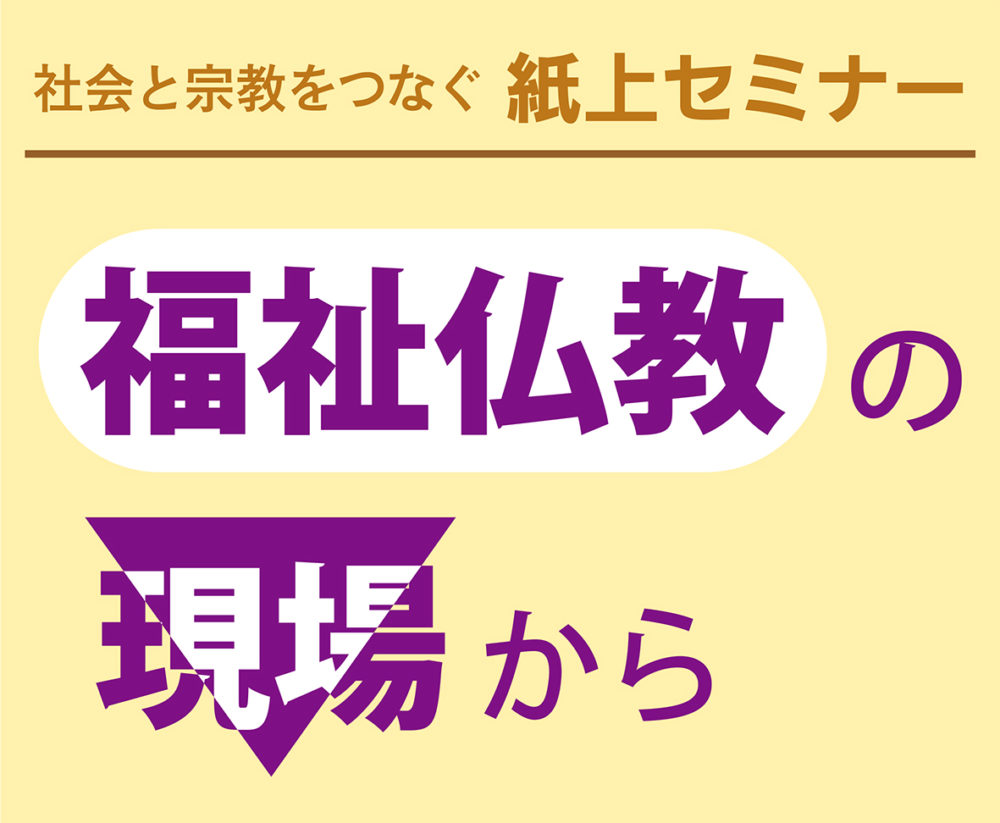つながる
福祉仏教ピックアップ
人生の終焉考えよう 大阪で「デザインサミット」
2026年1月26日
※文化時報2025年11月28日号の掲載記事です。
「人生の終焉(しゅうえん)をデザインする」がテーマのイベント「医療デザインサミット」が9日、大阪府東大阪市の大阪樟蔭女子大学で開催され、医療・介護従事者とエンディング産業関係者ら約250人が参加した。主催は一般社団法人日本医療デザインセンター。同市で地域包括ケアの構築を目指す任意団体、東大阪プロジェクトが特別協力した。
淀川キリスト教病院の医師登壇
医療・介護従事者に自身の死生観を考えてもらおうと、有識者2人が「さいごの授業」を行った。「もし、残された人生が半年間と知ったら、自分は誰に何を伝えるか」という前提に立って行う講義で、米国の大学教授の実話を元にしている。

同日午後に登壇したのは淀川キリスト教病院(大阪市東淀川区)の緩和医療内科主任部長、池永昌之氏。同病院は1984(昭和59)年に日本で2番目となるホスピスを開設し、現在も年間約300件の看取(みと)りを行っている。
池永氏は、人が死を恐れる理由として、自分で時期をコントロールできない▽苦痛を伴うこともある▽死期が近いことを認識しつつ生き続けなければならない―ことなどを挙げ、自分自身の死生観についても「どれだけ『いい看取り』を経験しても、自分の死が怖くないわけではない」とコメントした。
ホスピスのがん患者からは「どうして自分だけがこんな目に遭うのか。何か悪いことをしたのか」「どうせ死ぬのだから、何をしても無駄だ」といった多くの悩みが寄せられるという。これに対しては「私たち医師が画一的に答えを出せるものではないし、そもそも本人は私たちに回答を求めていないのではないか。結局は、本人が自分で答えを探すしかないと思う」と語った。

さらに、病気や災害などで大きな苦難に遭った人は、それまでの価値観や信念が変化すると指摘。「家族に言えなかった感謝や愛情を素直に口にできるようになるなど、前向きな変化が見られる。死についても同じことが言える。このような『苦悩の見方を変える支援をする』ことが、私たち専門家の役目ではないだろうか」と締めくくった。
午前にはファイナンシャルプランナーのいちのせかつみ氏が登壇。遺言書は財産のことばかり書くというイメージがあるが、実際には付言事項として残された人たちへのメッセージも記載できることに触れ「自分の手料理のレシピを書き残して亡くなった人もいる。お金や財産でなくても残せるものはたくさんある。それを大切にしてほしい」と訴えた。