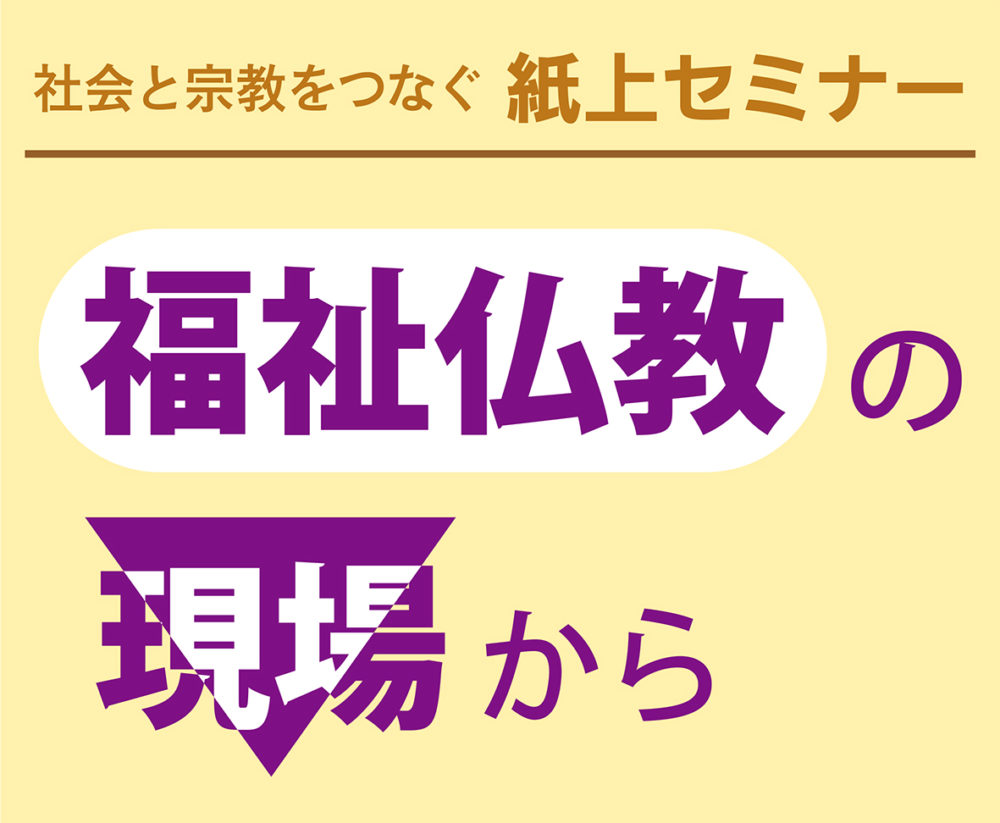知る
お寺と福祉の情報局
乳幼児の日常にアート 保育園美術館プロジェクト
2025年11月23日
保育園にアート作品を常設展示し、子どもたちが日常的にアートに触れる環境を生み出そうという「保育園美術館プロジェクト」に関する活動発表が、武蔵野美術大学市ケ谷キャンパス(東京都新宿区)で行われた。「保育園美術館プロジェクトフォーラム2017-2025」と題し、研究を行ってきた同大学の教授や保育園関係者らが登壇。美術教育に関心のあるアーティストや学生らが参加し、活発に意見を交わした。アートは想像力や発達にどう影響するのだろうか。(飯塚まりな)
美大生の卒業研究から
フォーラムは8月30日に開催され、武蔵野美術大学の杉浦幸子さんと米徳信一さん、川口短期大学の木谷安憲さん、社会福祉法人陽光福祉会理事長の大庭正宏氏さん、「あおぞら保育園」(東京都羽村市)の田中奈穂美さん―の計5人が登壇した。
保育園美術館プロジェクトとは、0歳から6歳までの子どもたちが過ごす保育園を「美術館」と位置付け、園内のさまざまな場所にアート作品を展示する試みだ。
発端は、武蔵野美術大学の学生がアルバイトをしていた保育園で、アート作品を園児たちに鑑賞してもらう取り組みを行い、卒業研究で発表したことだった。その学生の指導教員だった杉浦さんたちがその学生の研究に触発され、発展させた。
その舞台となったのが、あおぞら保育園。発達特性を持つ子どもたちも受け入れる「インクルーシブ保育」を実践している。

フォーラムでは、米徳さんが撮影・編集を行った7年半の活動をまとめた映像が上映された。
アートが子どもたちの成長にどう影響するのか、ひいては人生に何をもたらすのか。研究は園児のみならず、保育士や保護者も巻き込んでいく。
2017(平成29)年に始まったプロジェクトで最初に展示されたのは、造形作家辻蔵人さんによるオブジェだった。鉄廃材で作られたペンギンに戸惑う子どもが多い中、普段は内気で人形にも触れられなかった女の子が、シャベルで砂をすくい、まるで食べさせるようにくちばしへと運ぶ姿が映像に記録されていた。

これによって「子どもはカラフルなものが好き」ということが固定概念だったことに気付かされる。子どもは色よりも凹凸のある立体造形に関心を寄せ、新たな手触りに刺激を受けたことが、表情から見て取れた。
他にも恐竜のトリケラトプスの頭部のオブジェを見て、祈りをささげるように振る舞う男児もいた。
あおぞら保育園の田中さんは「このときは、この子の母親が入院していたので『早く帰ってきますように』と祈ったのかもしれない」と話した。幼いながらに救いを求める姿は、尊く感じられた。
作品の女の子にキス
プロジェクトの中で、一番作品を提供していたのは川口短期大学の木谷さんだった。日頃から保育士や幼稚園教諭を目指す学生たちに授業を行っている。
作品を展示する際には、必ずプロジェクトメンバーの大人たちが直接園に出向いて、子どもたちに新しい作品を持ってきたことを説明する。
ピンク色で描かれた女性のイラストを見て、子どもたちが「かわいい」と声を上げた。「どこに絵を飾ろうか」と、杉浦さんが子どもたちと相談する。配置を決めると子どもたちは、絵の周りではしゃいだ。
これ以降は動物、人物、お化けなど、子どもが親しみやすいモチーフや抽象画の作品が展示されていった。

普段、子どもたちは絵を気にせず素通りしているが、いざ別の教室に絵を移動させるとなるとなぜか嫌がり「私のもの」「僕のだよ」と訴える。子どもは無意識のうちに、作品を大事なものとして認識していた。
木谷さんの描いた女の子の絵に、思わずキスする子どももいた。保育園という慣れた場所で作品を見るからこそ、感情を素直に表現できるのだろう。
2020年からのコロナ禍で訪問できなくなると、木谷さんは風景画や花の絵を送った。活動が制限される時期に届いた絵を見て、保育士たちは声を上げて喜んでいたという。アートは子どもたちだけでなく、日々の保育に追われる大人の心にも力を与えていたのだ。
保育士の思いも込めて
今年は新しい展開として、保育士たちや園の職員に「自分の好きな絵を選ぶ」ことを体験してもらった。
保育士たちは、担当している子どもの年齢やクラスの雰囲気から作品を決めていった。 年長クラスの担任は「今よりもっと仲良くなって卒園してほしい」と、2人の子どもが向き合う絵を選んだ。

これまで7年余りに及んだ活動で、アートは役に立ったのだろうか。
子どもの成長にどのような影響があったのか、まだ答えは出ていない。ただ、「家にも絵を飾りたいから買って」と母親に頼むなど、絵を飾ることの価値を理解している子どもはいたという。

杉浦さんは「この場で答えを出すのではなく、プロジェクトを振り返り、一緒に考える機会をつくれたことに意義がありました」と語った。
大庭さんは「大人が思う以上に、子どもは確実に何かを受け取っている」と語る。