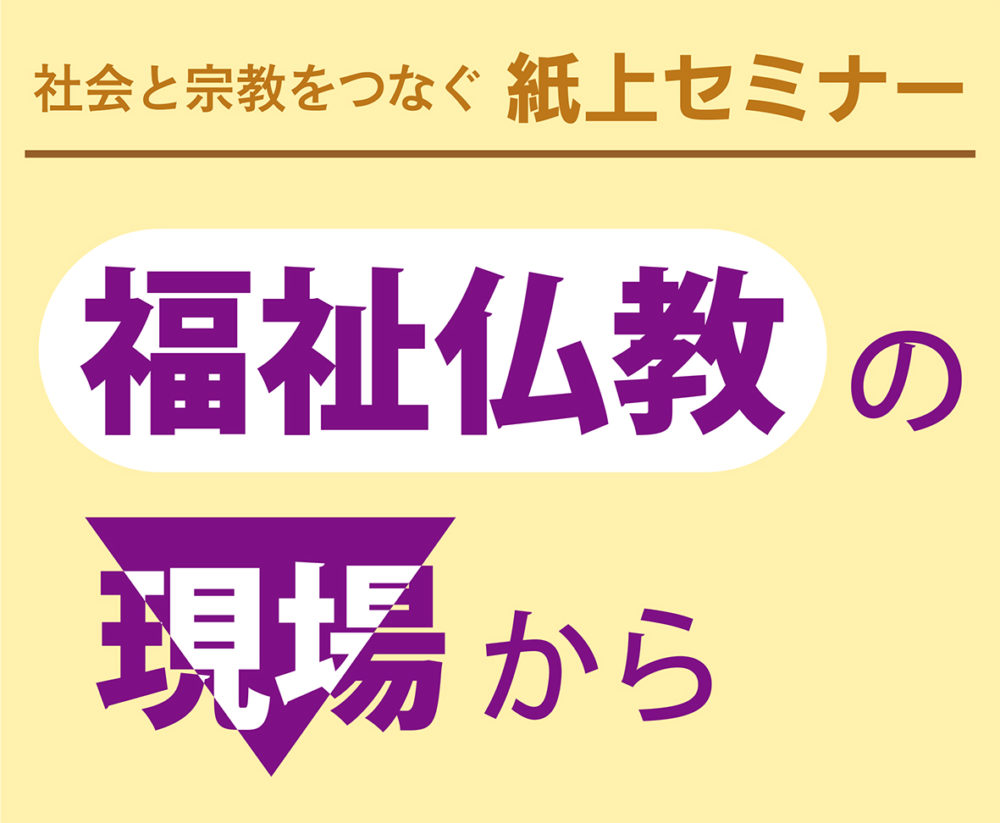読む
「文化時報」コラム
〈92〉齢(よわい)を超える
2025年11月25日
※文化時報2025年9月19日号の掲載記事です。
9月7日、63回目の誕生日を迎えた。還暦を過ぎると、もはや誕生日を心待ちにするような心境ではなく、人に言われて思い出すぐらいの、いたって「普通の日」なのだが、今年は少し、胸がキュッと締め付けられるような感慨があった。

それは、「夫の年齢を超えた」ことだ。
夫は4年前の10月21日に、62歳でこの世を去った。夫が生きて迎えることのできなかった年齢に、三つ年下の自分が到達したのである。年上の、頼るべき存在だった相手の年を追い越し、これからはその差がどんどん開いていく。言いようのない不思議な気持ちである。
実は、私は同じ経験を15年前にも一度している。48歳で早世した父の年齢を超えたときだ。
父が亡くなったとき、私は高校3年生で、まだ17歳だった。それでも父は、幼いころから私を一個の人格として尊重し、私の考えに耳を傾け、ときには激しい議論になったりもした。家は貧しかったが、音楽会や美術展、メーデー行進など、さまざまな場所に連れて行き、何でも経験させてくれた。まるで、自らの寿命を悟り、自分がいなくなった後に私が一人で生きていけるよう、大切なことを急いで伝えようとしているかのようだった、と後に母から言われたことがある。
父のいない人生を30年以上過ごした後に、父の歳を超えたとき、父の記憶はかなりおぼろげなものとなってしまっていた。それでも、理不尽な現実に黙っていられず、端から見れば無鉄砲とさえ言えるような言動に出てしまうところや、狭い自宅にたくさんの人を呼んでもてなしたがる寂しがり屋のところなどは、どう考えても父親からの遺伝以外の理由を見つけられない。
一方、赤の他人同士からスタートし、結婚して31年間、家族としての時間を過ごした後に旅立っていったのが夫である。
こちらは今もなお、ふとした拍子に日常のさまざまな場面、食事や会話、仕事でのやりとり(夫は私が独立し、法律事務所を設立したときから事務長として同じ事務所で働いていた)が思い出され、夢にも(死んだ人としてではなく)普通の登場人物として現れる。息子夫婦との間でも、「あのとき父ちゃんが○○だったよね~」「あ、それ父ちゃんが言ってたやつだ」といった会話が頻繁に登場する。
夫と自分の関係性や年齢差は永久に変わらないものという、ある種の「錯覚」の中にあって、しかし現実には夫の年齢を超え、これからどんどん自分の方が年上になっていくことに、父の年齢を超えたときとは異なる違和感を覚えるのだろうか。
生きて歳を重ね、先立たれた家族の齢を超えることは、「そこから先は、相手の知らない世界への一人旅」になることなのかもしれない。
でも、背中には遺伝やら思い出やらを、たくさん担いで、一足一足踏みしめながら、歩いていきたい。