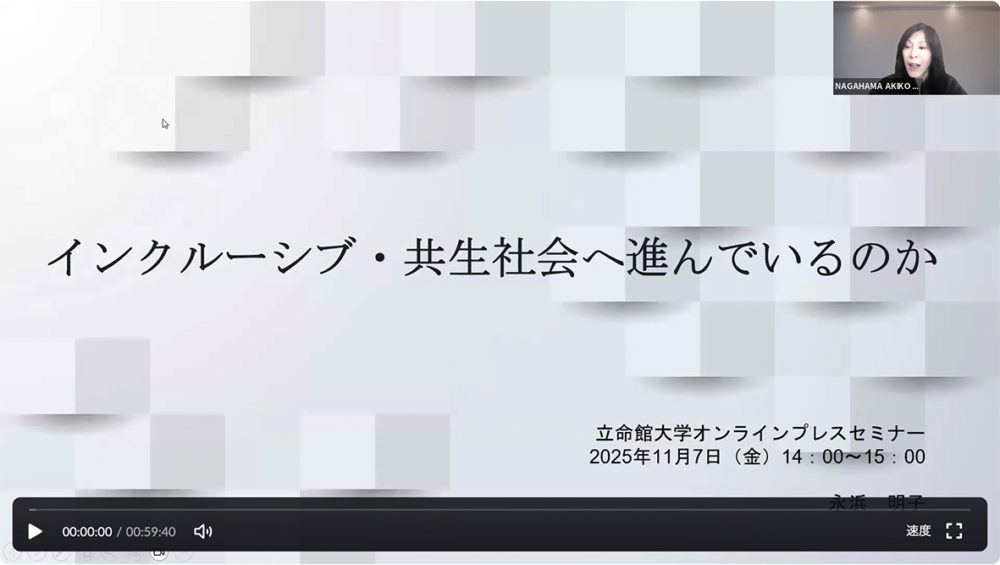読む
「文化時報」コラム
〈77〉新しい年、新しい命
2025年3月31日
※文化時報2025年1月17日号の掲載記事です。
この3年余り、多くの大切な人たちとの別れを経験してきた。2021年に夫、23年に母を送り、京都で独り暮らす身となった私に、お正月を一緒に過ごしましょう、と誘ってくれたのは、息子の妻・あさひの両親だった。

あさひの実家のある宮城県岩沼市で4度目のお正月を迎えた今年は、これまでになくにぎにぎしい新春となった。これまで大人5人で過ごしていたお正月に、昨年10月16日にあさひが里帰り出産で産んだ第一子・理倶(りく)が加わったからである。
この世に生を受けてまだ2カ月半の小さな赤ん坊が、まさに世界の中心で輝きを放っている。大人5人は理倶の一挙手一投足に目を細め、歓声を上げ、笑い合い、会話を弾ませる。生まれながらにこれほど人を惹(ひ)きつける力を授かるのは、逆にそうしなければ自力では生きていけないからなのだろう。
三が日を、ひたすら初孫と触れ合うことに費やした私は、無条件で愛情を注ぐ相手がいることの豊かさを、本当に久しぶりに実感していた。日頃、無実を訴える冤罪(えんざい)被害者と共に闘い、法改正に向けて国会議員や法務省と丁々発止の攻防を繰り広げ、ひりひりするような緊張と消耗の中に身を置く者にとって、この穏やかな時間はどれほど尊く、どれほど貴重であったか。
一方で、冤罪被害に苦しむ無実の人にも、それを支えている家族にも、そして、目の前の相手を犯人と思い込み、厳しい取り調べの末、無実の者に自白をさせた警察官や検察官にも、法廷で誤って有罪判決を言い渡した裁判官にも、このように無防備で柔らかく、無垢(むく)な存在であった時期が間違いなくあったのだと思うと、人の世の因果のやりきれなさ、切なさを思わずにはいられない。
正月滞在の3日目、岩沼市に鎮座する竹駒神社に、理倶のお宮参りに付き添って参詣した。竹駒神社は、日本三大稲荷とも称され、842(承和9)年に小野篁(おののたかむら)が多賀城の陸奥国府に陸奥守として着任した際、奥州鎮護の神としてこの地に創建した御社である。江戸時代には仙台藩伊達家歴代藩主の手厚い庇護(ひご)の下で領民の信仰を集め、現在も東北全県からの初詣客でにぎわう。
本殿で神楽舞付きの祈禱(きとう)を受けに訪れた多くの参列者とともに、雅楽の音色と巫女(みこ)の舞に迎えられ、頭を垂れてお祓(はら)いを受け、祝詞を聞きながら、1200年の歴史の中で、さまざまな思いを胸に祈りをささげた幾多の人々に思いを馳(は)せた。
理倶が80歳まで生きることができたら、私には見ることのできない22世紀を、彼は見ることになる。
新しい年の初めに、新しい命の健やかならんことを願う。
【用語解説】大崎事件
1979(昭和54)年10月、鹿児島県大崎町で男性の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、義姉の原口アヤ子さん(当時52)と元夫ら3人が逮捕・起訴された。原口さん以外の3人には知的障害があり、起訴内容を認めて懲役1~8年の判決が確定。原口さんは一貫して無実を訴えたが、81年に懲役10年が確定し、服役した。出所後の95年に再審請求し、第1次請求・第3次請求で計3回、再審開始が認められたものの、検察側が不服を申し立て、福岡高裁宮崎支部(第1次)と最高裁(第3次)で取り消された。2020年3月に第4次再審請求を行い、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部に続いて最高裁が25年2月、請求を棄却した。