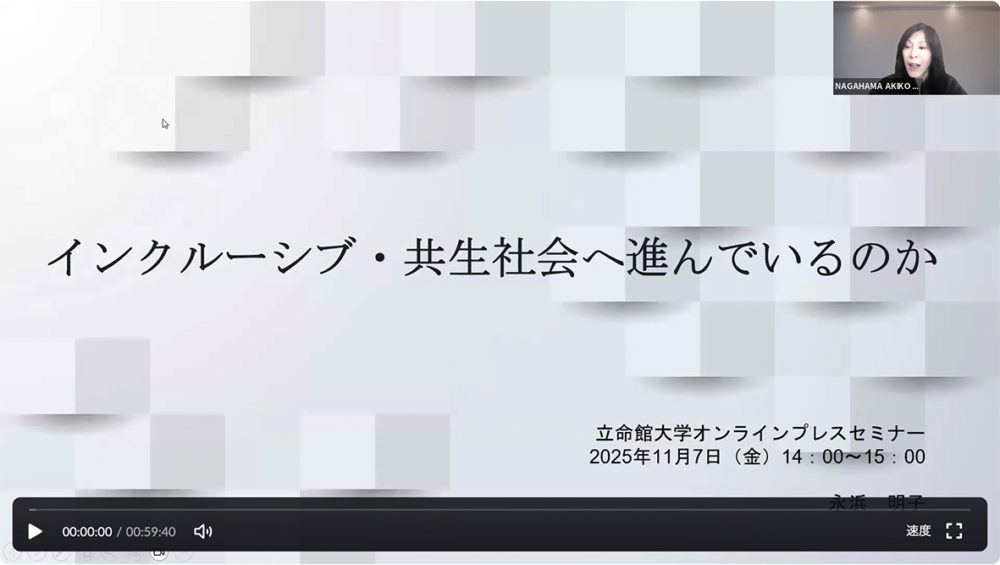読む
「文化時報」コラム
〈83〉「肩書」ってなんだろう
2025年7月2日
※文化時報2025年4月18日号の掲載記事です。
今年もあっという間に1年の4分の1が過ぎ、4月に入った。日本では新年度のスタートである。

新入学、新入社、転勤、転校など、新たな環境で新たな生活をスタートさせた人も多いだろう。人事異動によって肩書が変わり、大慌てで名刺を発注している人も少なくないはずだ。
かく言う私も、4月から日本弁護士連合会(日弁連)での肩書が変わり、慌てて名刺を発注した一人である。今までの肩書は「再審法改正実現本部本部長代行」だったが、今年度から「再審法改正推進室長(会長特別補佐)」となった。これが昇格なのか、降格なのか、本人にもよく分からない。業務の内容もこれまでと変わらないので、なおさらである。
日弁連は、法律に基づき全弁護士が強制的に加入しなければならない特殊な団体ゆえ、組織も複雑で、私のような一介の弁護士の理解を超える「大人の事情」があるようだ。それが今回の肩書変更の背景となっているらしい。
そもそも、「肩書」とはなんなのだろう。古くは、歌舞伎役者の名前の脇に記された「座本(ざもと。劇団の代表や興行元)」を「片書」と呼んだことに由来するようだ。江戸時代の貞享4(1687)年に刊行された『野良立役舞台大鏡(やろうたちやくぶたいおおかがみ)』という、役者や舞台のガイドブックに、「目録の片書に座本をしるす」とある。
もともと「片書」に記されたのは出所や所属だったが、それが次第に職名、官職、社会的地位や身分、企業内での役職にまで広がった。名前の右上に記されることが多いからか、漢字も「肩書」とされるようになった。日本独特の「名刺文化」も大いに影響していると言えよう。
肩書の名称もさまざまだ。企業では「社長」「専務」「常務」「部長」「課長」「係長」といった肩書がおなじみだが、官公庁では「審議官」「参事官」「主幹」「主査」といった名称もみられる。最近では「CEO」「シニアフェロー」「カウンセル」など、横文字系の肩書も少なくない。
人はともすると、相手の人となりを肩書で短絡的に判断してしまいがちだ。だからこそ、相手に少しでも存在感や信頼感を与えようとして、初対面の際にやりとりされる名刺に仰々しく肩書が印刷されるのだ。しかし、肩書は人間を測る物差しではないし、その人が行った努力や成果が必ずしも肩書に反映されているわけでもない。
一方で、人は身の丈を超える肩書を背負わされ、その肩書にふさわしい役割を果たそうと必死で努力することで、大きく成長することがあるのも事実だ。
新しい名刺の、自分の名前の右上に印刷された新しい肩書は、いまの私の使命を如実に示している。しかし、この肩書をいつまでも背負っていては駄目だ。一刻も早く再審法改正を実現させて、この肩書を脱ぎ捨てる日を目指したい。
【用語解説】大崎事件
1979(昭和54)年10月、鹿児島県大崎町で男性の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、義姉の原口アヤ子さん(当時52)と元夫ら3人が逮捕・起訴された。原口さん以外の3人には知的障害があり、起訴内容を認めて懲役1~8年の判決が確定。原口さんは一貫して無実を訴えたが、81年に懲役10年が確定し、服役した。出所後の95年に再審請求し、第1次請求・第3次請求で計3回、再審開始が認められたものの、検察側が不服を申し立て、福岡高裁宮崎支部(第1次)と最高裁(第3次)で取り消された。2020年3月に第4次再審請求を行い、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部に続いて最高裁が25年2月、請求を棄却した。