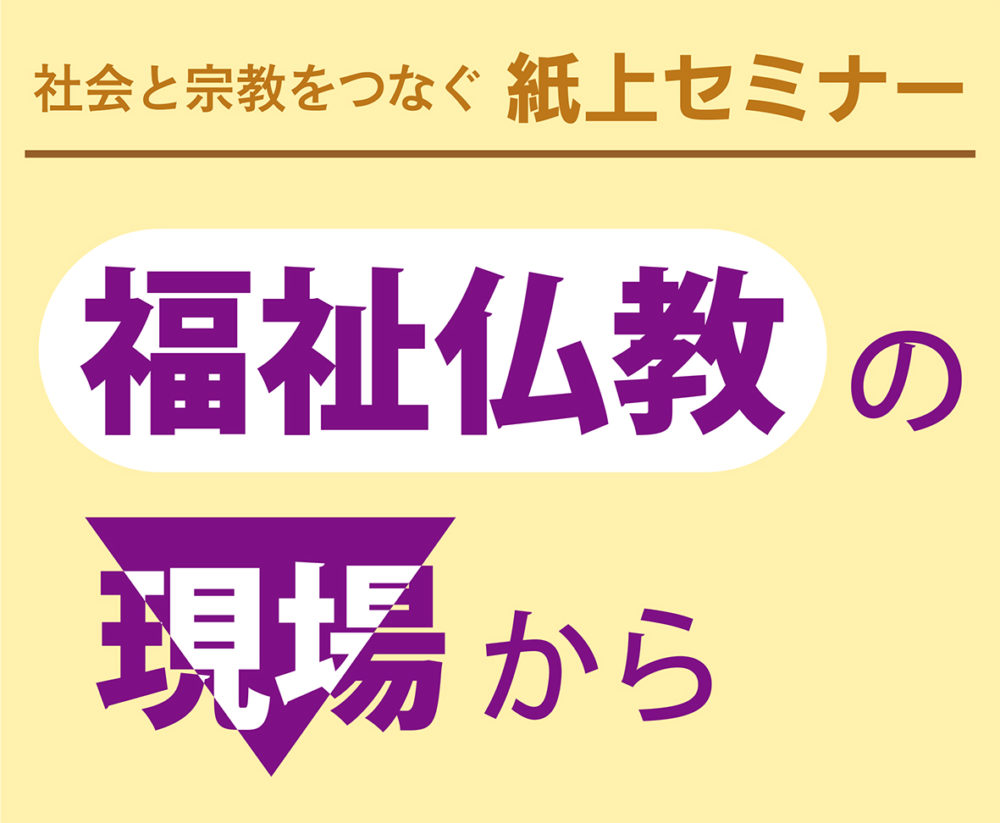読む
「文化時報」コラム
〈72〉過而不改、是謂過矣
2024年12月12日 | 2025年2月12日更新
※文化時報2024年10月18日号の掲載記事です。
袴田事件=用語解説=の再審無罪判決が確定した。10月8日、私は東京から京都に向かう新幹線の車内で「検察官が控訴断念」の一報に接した。事件から58年、死刑確定から44年。無実でありながら、日々死刑執行の恐怖に晒された巖さんと、同じ年月を、人生の全てを懸けて弟を支え続けた姉のひで子さんの、長い長い闘いがようやく終わったのだと思うと、熱いものがこみあげてきた。とにかく良かった。あとは2人でゆっくり平穏な毎日を過ごしてほしい―。

しかし、しみじみとした感慨はわずか数時間後に猛烈な怒りに変わった。怒りの原因は、控訴を断念するにあたり、畝本直美検事総長が公表した「談話」である。
談話ではまず、再審公判において検察官が巖さんの有罪主張を行ったことについて、「改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡地裁における再審公判では、有罪立証を行うこととしました」と釈明した。
そして今回の無罪判決が巖さんを無罪とした理由の中で、捜査機関による「三つの捏造(ねつぞう)」があったと断定したことについて、「本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません」と、判決内容を強い口調で批判している。
その上で談話は、控訴断念の理由について、こう述べている。「本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。しかしながら、再審請求審における司法判断が区々(まちまち)になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました」
要するに、「今回の判決はいろいろおかしいけど、これまで裁判所がてんでばらばらな判断をしたことで袴田さんを長期間不安定な状況に置いたから、このあたりで矛を収めてやることにする」と言っているのである。
再審の長期化を裁判所のせいにしているが、再審手続きの中で30年間も証拠開示に応じず、さらに静岡地裁の再審開始決定に即時抗告し、審理を9年も長引かせたのは、ほかならぬ検察である。何より、捏造された証拠で無実の人間が死刑になっていたかもしれないという、極めて深刻な事態を直視しようとしない検察組織には、もはや「公益の代表者」を名乗る資格はない。
判決を受けて、新聞各紙は巖さんを犯人視した報道を行ったことを謝罪した。「過而不改、是謂過矣(過ちて改めざる、これを過ちという)」という孔子の言葉を、司法に携わる全ての者が、今まさに噛(か)みしめなければならない。
【用語解説】大崎事件
1979(昭和54)年10 月、鹿児島県大崎町で男性の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、義姉の原口アヤ子さん(当時52)と元夫ら3人が逮捕・起訴された。原口さん以外の3人には知的障害があり、起訴内容を認めて懲役1~8年の判決が確定。原口さんは一貫して無実を訴えたが、81年に懲役10年が確定し、服役した。出所後の95年に再審請求し、第1次請求・第3次請求で計3回、再審開始が認められたものの、検察側が不服を申し立て、福岡高裁宮崎支部(第1次)と最高裁(第3次)で取り消された。2020年3月に第4次再審請求を行い、鹿児島地裁は22年6月に請求を棄却。福岡高裁宮崎支部も23年6月5日、再審を認めない決定を出した。
【用語解説】袴田事件
1966(昭和41)年に静岡県で起きた一家4人殺害事件。強盗殺人罪などで起訴された袴田巖さんは公判で無罪を訴えたが、80年に最高裁で死刑が確定した。裁判のやり直しを求める再審請求を受け、2014(平成26)年3月に静岡地裁が再審開始を決定。袴田さんは釈放された。
検察側の即時抗告によって東京高裁が決定を取り消したものの、最高裁が差し戻し。東京高裁は23年3月、捜査機関が証拠を捏造(ねつぞう)した可能性が「極めて高い」として、改めて再審開始決定を出し、検察側は特別抗告を断念した。再審公判で静岡地裁は今年9月26日、袴田さんに無罪を言い渡した。