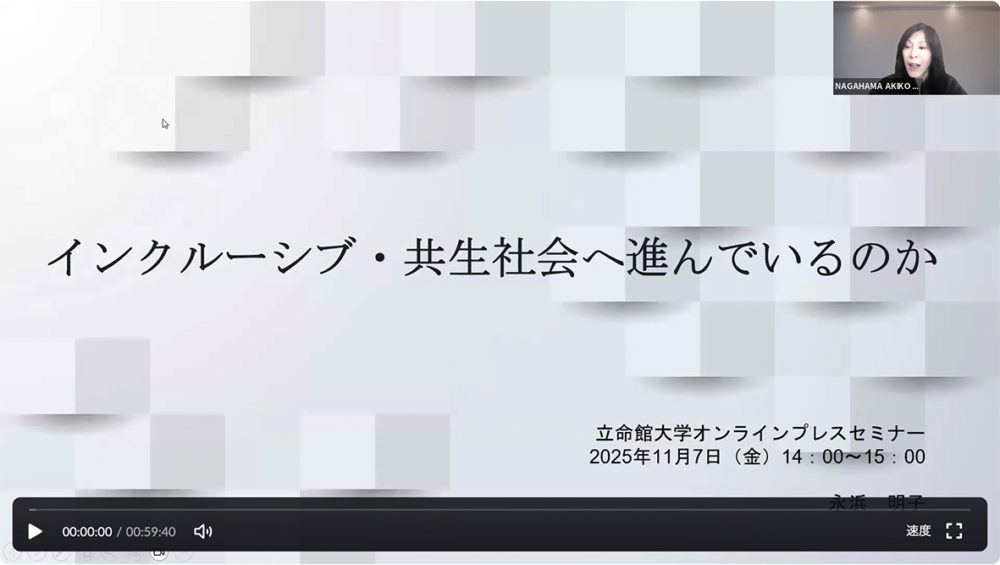つながる
福祉仏教ピックアップ
〈11〉呉服メーカーが供養品販売 大丸東京店「和ぎゃらりい」
2024年12月11日
東京駅に隣接する大丸東京店の10階にある呉服ショップ「和ぎゃらりい」は、着物や帯などのほかに線香、お香、数珠の販売を行っており、よく売れている。特に線香は、供養を目的とした購入が多く、野本純子店長は「ご先祖さまを大事にしている方は、まだまだたくさんいらっしゃるのでは」と語っている。
大丸東京店に「和ぎゃらりい」を出店しているのは、江戸末期の1843(天保14)年に京都で創業したファブリックメーカーの川島織物セルコン。祇園祭の山鉾(やまほこ)の懸装品や、歌舞伎座の緞帳(どんちょう)なども手掛け、和装文化を継承する格調高い会社である。

その同社が、和ぎゃらりぃで線香などを扱い始めた経緯はこうだ。
12年ほど前、大丸東京店が増床して東急ハンズ(現・ハンズ東京店)ができた。和ぎゃらりいは、それまで着物と帯のみ取り扱っていたが、売り場が東急ハンズの隣に位置していたため、大丸側から「和雑貨」も取り扱ってほしいと要望された。
そこで、呉服という日本文化に通じる線香やお香と、線香をあげる場面で用いられることの多い数珠を取り扱うことにした。単に並べておくだけでなく、和服から洋服へという時代の変化で呉服が多くは売れなくなっていたことから、和雑貨の販売に力を入れることにしたという。

線香は月数百箱売れる
最近の月間販売量は、線香とお香はともに数百箱、数珠も数十連となっている。価格帯は、線香3000~5000円、お香1200~1500円。数珠は1万~1万2000円のものが多いようだ。

こうした状況について、野本店長は「ほかの百貨店の状況は分からないが、メーカーさんの話だと、当店はよく売れている方だそうだ。各商品の購入単価も高い。富裕層のお客さまが多いからだと思う」と話す。
野本店長は、大丸東京店の和ぎゃらりいに勤務して12年になるが、これら3商品の売れ行きに変化はあまりなく、コンスタントによく売れているという。
客層や購入目的は、線香で一番多いのが、会社員が仕事関係の通夜・告別式に参列するときの贈答用だ。これは、東京駅周辺にオフィスビルが林立しており、会社員が多いことによる。
このほか、お盆などに東京駅から新幹線に乗って帰省する際に購入する人や、年賀状をやりとりしている人が亡くなったことを知らず、喪中はがきが届いた時に贈る人が多いのだという。
先祖を大事にする人は多い
お香は、自分用として購入する人がほとんどで、「リラックスしたいときとか、ちょっとお部屋の香りが気になる時に、普通に焚(た)いて楽しんでいる方が多いようです」。同店で取り扱っているお香は1メーカーだが、ファンが多い商品もあり、切れそうになると買いに来る常連客も多いそうだ。
数珠は、通夜・告別式に参列するのに持ってくるのを忘れた人や、勤務中に急に通夜・告別式へ参列しなければならなくなり、買いに来る人が多いのだという。
このように、特に供養を目的にした購入が多いのは線香であり、数量も多くなっている。
野本店長に「供養する人が減ってきているという声も聞かれるが、どう感じるか」と尋ねたところ、次のように語った。
「そのような感じはしない。逆に、増えているようにも感じる。コロナ禍では、お盆などに『帰省できないから、線香を贈ってください』という依頼がとても多かった。ご先祖さまを大事にしている方はまだまだたくさんいらっしゃるのだと思う」
【塚本の目】供養はいのちへの感謝
川島織物セルコンでは、帯の供養塔「帯塚」がある日蓮宗常照寺(京都市北区)で帯供養を行っている。1969(昭和44)年から毎年続けており、今年で56回を数える。
供養とは、故人を弔い、想(おも)いを寄せることと考えられることが多いが、帯に対する供養とは、帯が出来上がるまでの、さまざまな生き物のいのちや人の想いに対して感謝することだという。
帯は、さまざまな人の手を経てできており、さらに使っていた人の想いがたくさん込められているため、感謝しながら継承していくものだそうだ。
故人を弔うという意味での供養は、簡略化され、行わないことも増えてきている。筆者は、帯供養の意味・目的を聞いて、弔いにも感謝という意味が含まれているが、いのちへの感謝という表現の方が、人々を引きつけたり考えさせたりするのではないかと思った。
供養業界はファブリック業界からも学べることが、いろいろとある。