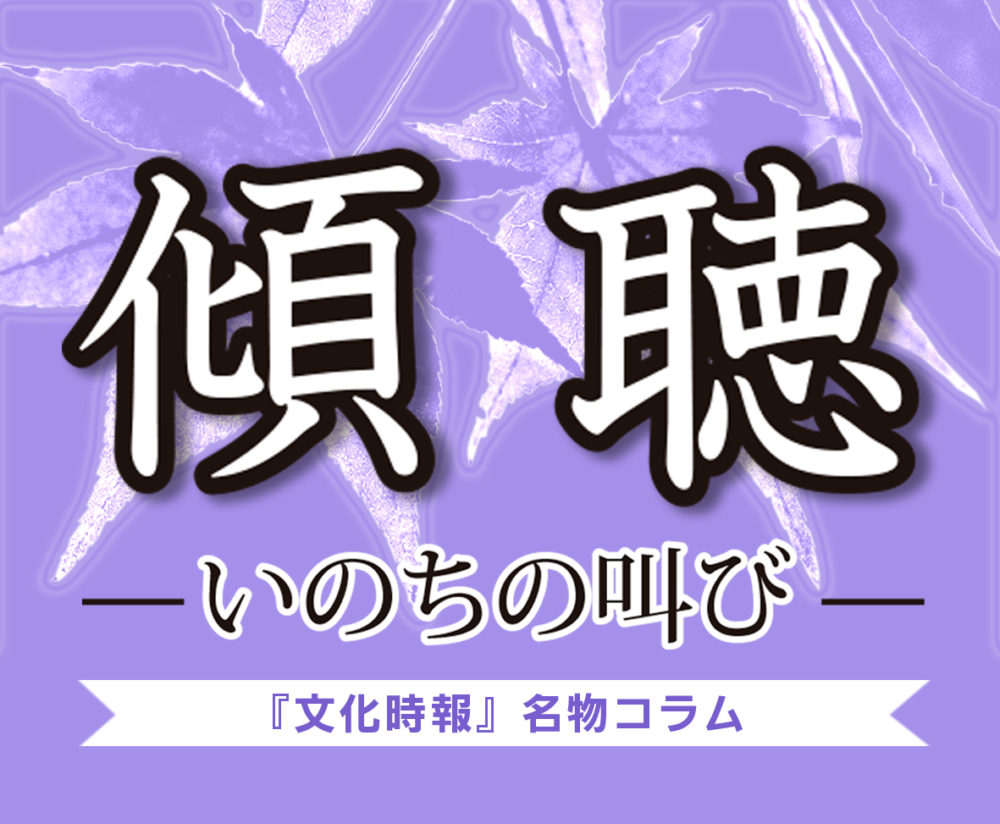読む
「文化時報」コラム
〈85〉悲しみの池
2025年8月2日
※文化時報2025年5月16日号の掲載記事です。
人は誰もが、徹底的に独りだと思っています。
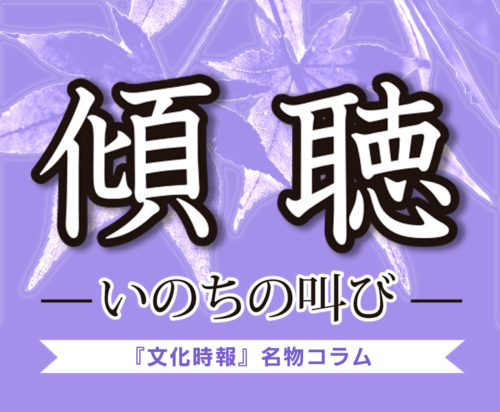
とりわけ「死」という境においては、誰もがその道を独りで歩かざるを得ないのです。私はそのことを繰り返し拝見し、骨の髄まで「人は徹底的に独りだ」と知るようになりました。
だから「寄り添う」「一緒にいる」「独りじゃない」といった言葉に、どこか噓(うそ)くささを感じるようになってしまったのでしょう。それらの言葉を軽々しく使うとき「他者の痛みの隣にいる自分」に酔っているわが姿を見て、その滑稽さに慌てて手を引っ込めるのです。
私の中に、一つの風景があります。
悲しみの池の中に、その人がぽつんと佇(たたず)んでいます。水は全ての色を放棄して鈍色(にびいろ)に沈み、その人の熱を根こそぎ奪っていこうとしています。でも、声をかけて岸に救い出すことも、池の水を全部汲(く)み出してしまうこともできません。私にできることはただ一つ、水面を少しも揺らさぬように注意しながら、その池に静かに滑り込ませていただくことだけです。
そのために、私はしばしば病室のドアの前でじっと立ち尽くします。中から漏れ出してくる音、温度、香り、熱量、リズム、全てに自分を同調させるために。しっかり波動を合わせてこそ、波一つ立てずにそっとその人が今いる世界に滑り込ませていただくことができます。
そして静かに感じるのです。今、その人が何を見ているのか、何を感じているのか、何を嘆いているのか。そこには、余計なエネルギーは必要ありません。何かを「してあげよう」などという執着は水面を波立たせて乱し、かえってその人を苦しめるだけだからです。
一切の執着―助けたい、変えたい、理解したい、良い関係を築きたい、自分を役立てたい―をまずは手放し、ただそこに「在(あ)り続ける」。ただ同じ悲しみの池の水に身を沈めて、静かに呼吸を合わせる。その在り方だけが、時として、何かを変える力を持つことがあるのかもしれないと感じています。