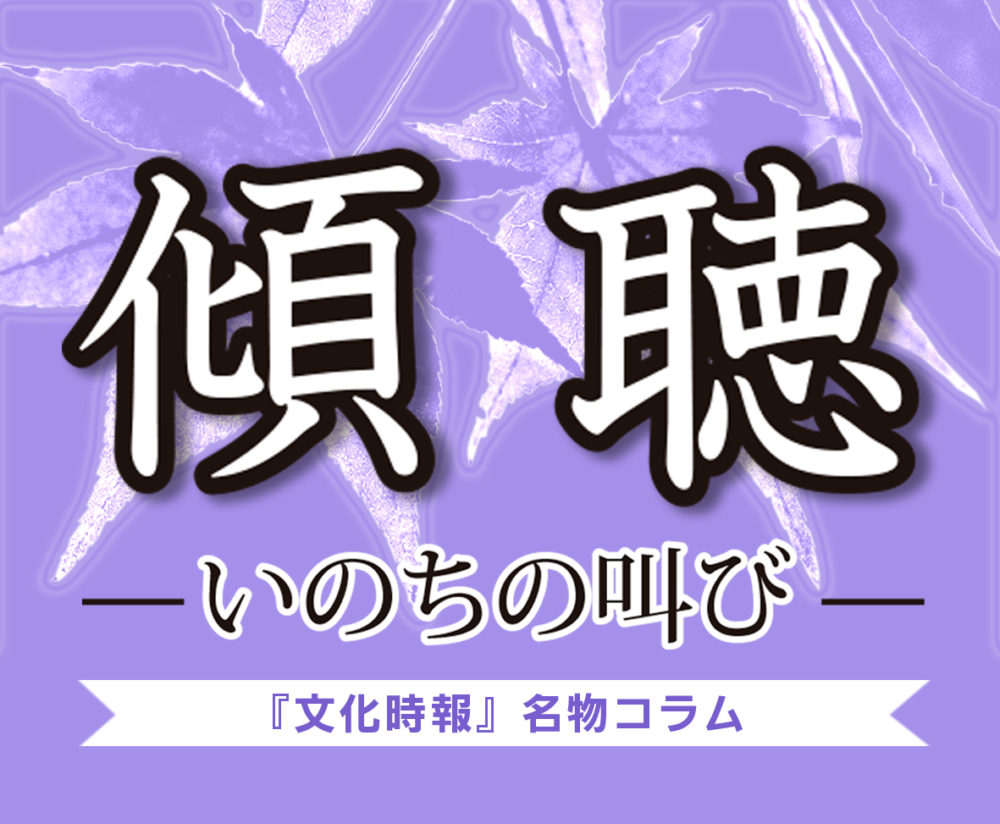読む
「文化時報」コラム
〈92〉手帳とカレンダー
2025年11月12日
※文化時報2025年9月12日号の掲載記事です。
ちらほらと、書店の店頭に来年の手帳が並び始めました。時の速さに舌を巻きながらも、「さて、来年はどんな手帳にしよう。早めに買っておくかな」と考える私がいます。
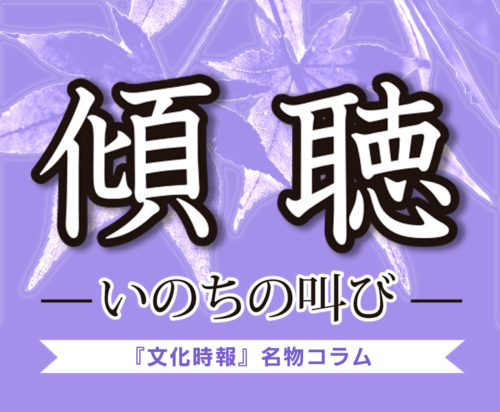
なんと当たり前のように「来年も今の状態のまま生き続けている」と、心の底から信じきっていることでしょう。そのあまりにも一点の曇りもないさまに、われながらあきれるほどです。口では「人間いつ死ぬか分からない」などと言いながら、自分で意識することさえない心の奥底では、まったくそう思ってはいないのです。
もし今、余命3カ月と、己の死を明確に宣告されていたとしたら、どうでしょうか。手帳を手に取りながら「ほとんど使わないのに買うのか」と躊躇(ちゅうちょ)するかもしれない。もしくは、そもそも来年の手帳になんて目がいかないかもしれません。
ある人が話してくれたことがあります。余命を伝えられている夫に、毎日寄り添っていた方です。ある月の最終日の夕方、ふと「もうめくっておこう」と思い立ってカレンダーに手をかけると、それを見ていた夫が言いました─。「やめてくれ。俺は明日、ここにいるかどうか分からないから」
そこはもう、想像するしかないのです。だって、私たちは見えていないから。こうやって何のためらいもなく来年の手帳を買おうとする私には、分かり得るわけがないから。だから、脳細胞を総動員して想像するしかないのです。命の終わりがはっきり見えている人たちの目には、いったいどんな風景が映っているのだろう、と。
それは、どんなに考えても今の私には見ることができない風景です。私の想像は、私の持っている枠組みを超えていくことができないからです。それでも、想像することを止めてはいけない。分からない、分かりたい、でもやっぱり分からない─その円環を回り続ける。だって、分かったような気になった瞬間に、扉は閉じてしまうから。
私よ、分からないままにそばにいるために、謙虚であれ。