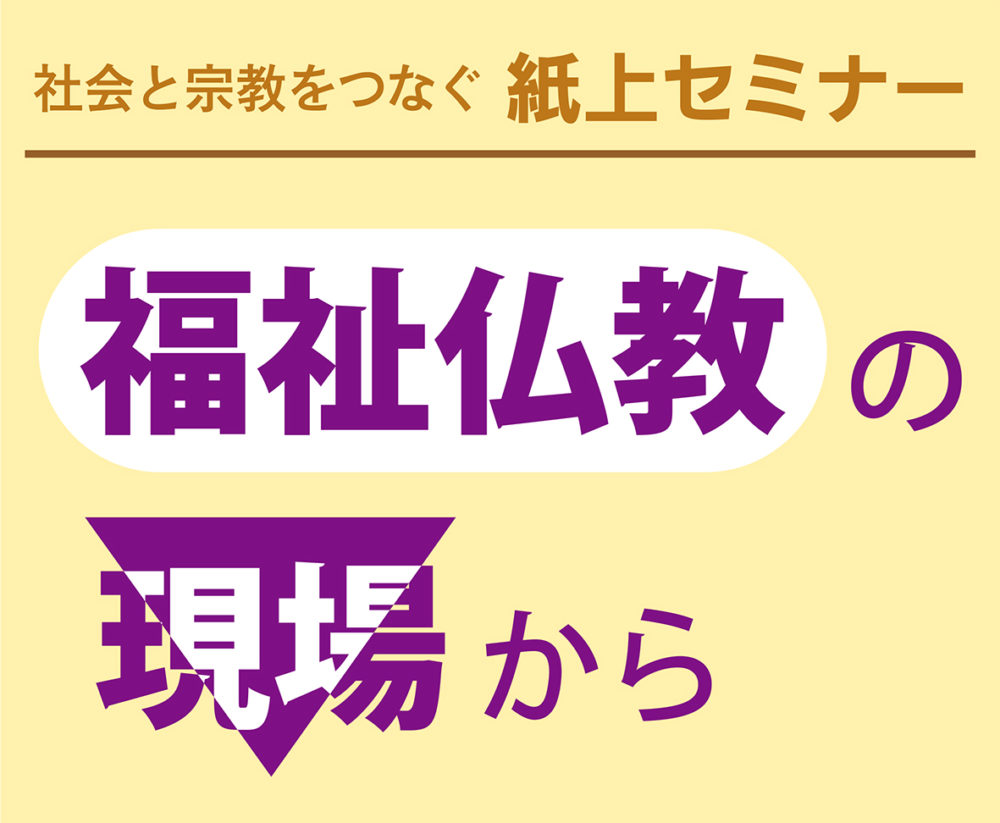読む
「文化時報」コラム
〈17〉埋め合わせ
2025年9月7日
※文化時報2025年6月10日号の掲載記事です。
過去を振り返り、その一つ一つを丁寧に文字で書き続けていった。
幼少期のつらかったこと、少年期のみじめだったこと、たくさんたくさん傷つけてしまった家族や友人、恋人との関わり方。書いても書いても終わらないから、ある程度で見切りをつけて書き終えた。

今度はそうやって書き上げた自分自身のこれまでの記録、棚卸しを人に聞いてもらった。
誰かを前に自分の書いた内容を読むのは、苦しい。案外過去に起こったことは書けるけど、現在進行形の事柄は現在と関連してしまうため、言いにくい気持ちが強くあった。ただ、書いたことを全て話そうと決めて臨んだので、急いで、でもとにかく話し切った。
聞いてくれた人から、いくつか尋ねられた。
「洋次郎が話してくれた小学校のころの話。洋次郎が理由は分からないけどしんどくなって、登校してもすぐに仮病を使って保健室にこもって眠り続けたって話。当時は『同級生が弱っている自分を見下しにきた!本心から心配してきてくれたのではなく、担任の先生にいい顔をしたくて、来ていたに決まってる』って思った話。今の洋次郎は、それをどう思うの?」
「中学を卒業してしばらくしたとき、たまり場に何十人もの不良少年が集まってシンナーを吸ったりバイクを乗り回したりしたとき、犬を連れてやってきたお母さんに『カッコ悪いやんけ!気持ち悪い!』って怒鳴りつけたって話。今の洋次郎は、それをどう思うの?」
確かに何も思っていなかったら人は行動に移さないだろうから、小学校のころの同級生もたまり場にきた母親も、それぞれに心配してくれていたのかなって思うかな。
そのときは「自分がこうしてほしい!」という気持ちや考え、価値観が強くあったから、それに当てはまらないことは全て切り捨てていた。言い換えれば自分がこうやって愛してほしいという愛し方以外は、愛とは認めない。自分の望んだ通りのことをしてくれることだけが、自分を大切にしてくれていると思ってきた。
でも、少し距離を置いて見られたとき、確かにそこには愛があった。自分が望んだ形ではなかっただけで、愛情があったのだと思った。
私のそばからいなくなった人たちも、当時は「裏切り者」「偽善者」とさんざんののしっていたけど、本当は心を持って、愛を持って私と向き合ってくれていたのかもしれない。だからこそ傷ついて、離れる決断をしたのかもしれない。
そう思えたとき、愛なんてないんだと思ってきた自分の生きてきたこれまでの人生の至る所に、本当は愛があったんだと感じた。
こんなにもたくさんの人たちに愛されて、自分自身は生きてきた。