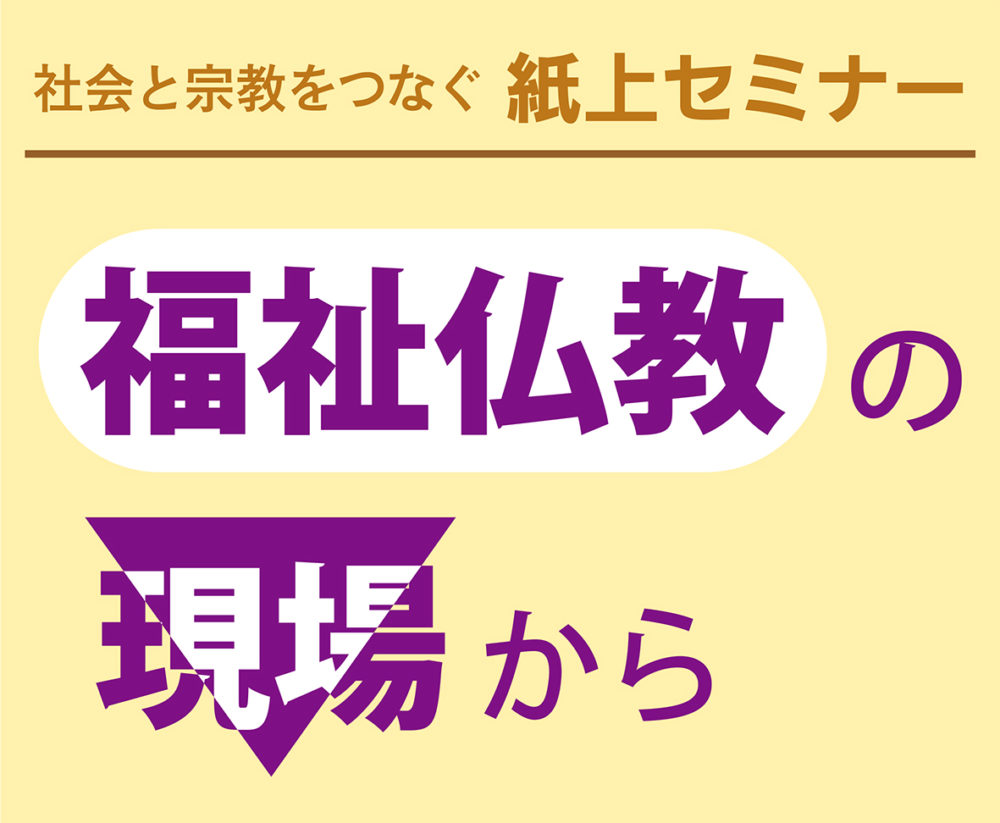つながる
福祉仏教ピックアップ
〈文化時報社説〉「家族じまい」の正体
2025年8月1日
※文化時報2025年4月11日号の掲載記事です。
お笑いコンビ・麒麟(きりん)の田村裕さんの自叙伝『ホームレス中学生』(2007年)は、田村さんが中学2年のときに父親が突然「家族解散」を告げ、蒸発するところから物語が始まる。やむなく公園で一人暮らしを始めたという衝撃的な実話が反響を呼び、225万部のベストセラーとなった。

それから18年が過ぎて最近、話題になっているのが「家族じまい」である。檀家制度に立脚するお寺はもちろん、社会としても看過できない言葉だ。
「家族じまい」は、桜木紫乃さんの小説のタイトルでもあるが、終活業者が手がける家族代行サービスのことをいう。日常生活の見守りや介護、看取(みと)り、葬儀や死後のさまざまな手続きを終活業者が担う。「親の面倒は子が見る」という価値観の対極で、家族関係を金銭に置き換える仕組みである。
細かく見れば、一つ一つのサービスはすでに普及している。本人の老後に備えるため、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を結んでもらう。あるいは入院や施設入居の際、身元引受人になる。こうした分野に着目する終活業者や法律関係の専門家が増えている。
多くは身寄りのない高齢者自身が依頼するこうした内容を、家族が依頼することによって、意図的に身寄りのない状態をつくり出すことが家族代行サービスの正体ではないか。それが「家族じまい」というどぎつい言葉をまとうことで、耳目を集めているのだろう。
悩ましいのは、「家族じまい」という言葉に救われる人がいることだ。
たとえば、子どものころに虐待を受けたり「毒親」に支配されたりして親と疎遠になっていた人が、急に「親の介護が必要になった」と言われたとき、「もう関わりたくない」と思ったとしても不思議ではない。
だが、親の面倒を見ないことと、家族関係を清算することは異なる。先祖から生命のバトンを受け継いで血を分けた親きょうだいとの間柄は、心情的にも法律的にも、そう簡単に切れるものではない。だからこそ、家族関係に苦しむ人に対し、安易に「家族じまい」ができると勧めることは誠実とはいえない。
日本の福祉制度が家族ありきで設計されていることを鑑みれば、終活業者がどこまで責任を持って家族を代行できるのかも心配である。孤立を助長する結果にならないかも気がかりだ。
公園で暮らしていた田村さんはその後、周囲の大人たちの手助けでアパートに住めるようになったという。私たちの社会には、支え合いによって互いの苦を和らげる力があることを、忘れてはならない。