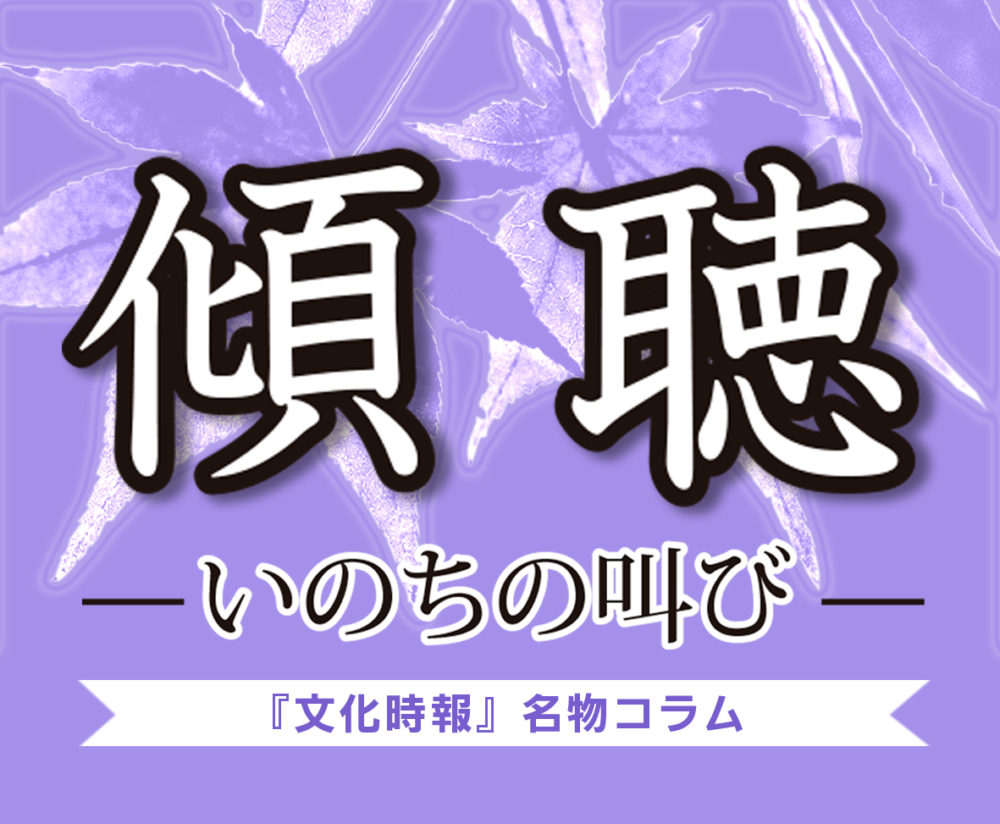読む
「文化時報」コラム
〈88〉孤独
2025年9月15日
※文化時報2025年6月27日号の掲載記事です。
人は、本当に弱いものです。
この皮膚は熱いものにわずかでも触れれば焼けただれ、冷たいものに触れれば凍(い)てついて崩れます。骨は数メートルの高さから落ちただけでも砕け散り、指先の爪で岩をつかんで登ることすらできません。暑さ寒さにも耐えられず、他の獣を攻撃するどころか、襲われれば逃げることさえままならない。まるで絹豆腐のように軟らかく壊れやすい存在です。
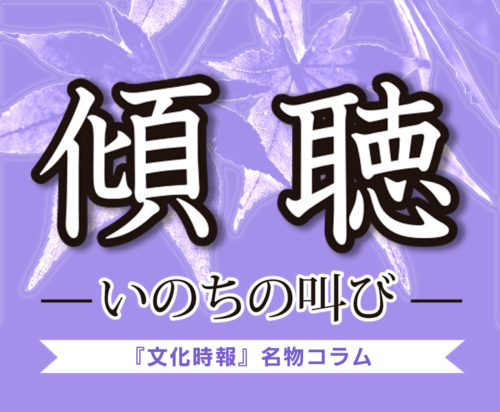
だからこそ人は、自分を守るために人の中にいるのだそうです。周りに人がいるというだけでどこか安心できる。その感覚に、人は救われるのでしょう。
けれど、たとえ周囲に人がいても、ふと「独り」を感じる瞬間があります。これが「目に見えない孤立」です。自分を守れなくなってしまっている状態です。この状態は本人にとってとても苦しく、「孤独」という静かな悲鳴が上がりはじめます。
社会はその「孤独」をなんとかしようと動きます。仲間づくりのためのコミュニティーを立ち上げたり、関心を引くイベントを企画したり。けれど、そうした表面的なサポートだけでは、どうしても届かないものがあるように思うのです。
その人にまとわりついている「孤独」は、おそらく外からの働きかけでは消えないでしょう。「孤独」であることの苦悩を本当に手放すには、「人は、もともと徹底的に孤独な存在なのだ」と、その人自身が心の底から納得することが必要なのではないでしょうか。
どんな人も、独りで生まれて、独りで死んで逝くのです。どんなに愛し合っていても、どんなに大切に慈しんでいても、一緒に生まれて一緒に死んで逝くことはできない。その真理が胸に灯(とも)れば、たとえ周囲に誰もいなくとも、揺るがない安心感が生まれてくる気がします。
こうしていま自分が存在しているということ自体が、すでに大いなる何かに守られている証しなのだと、信じられるようになると思うのです。