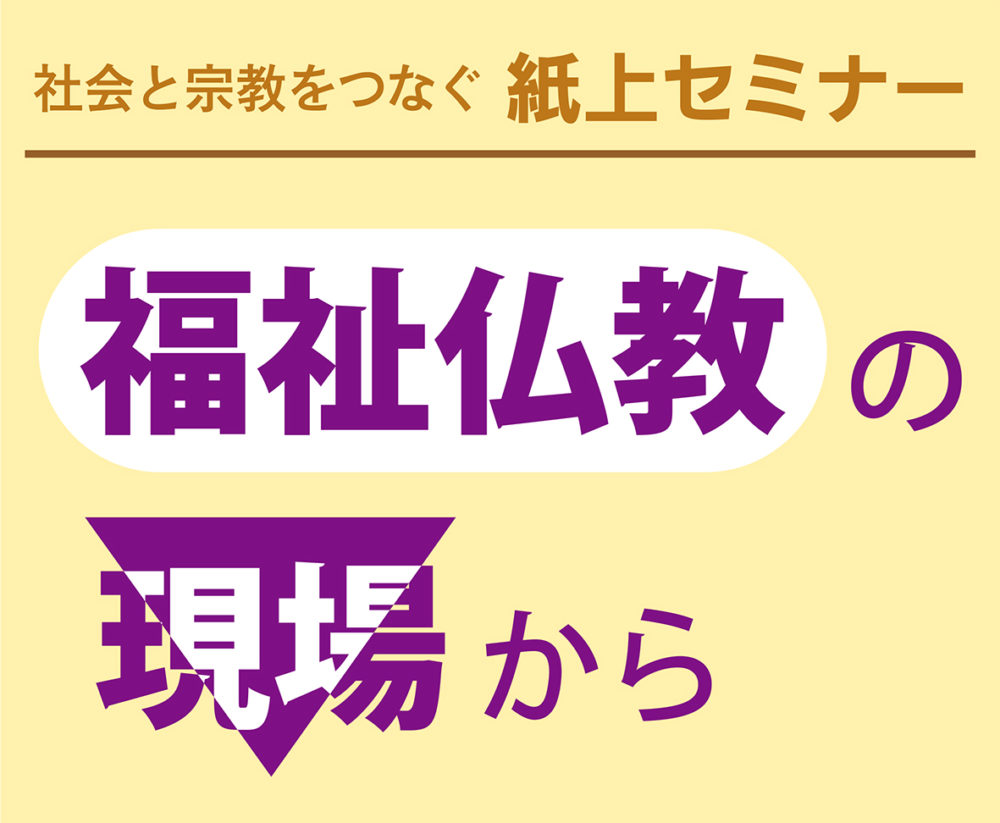読む
「文化時報」コラム
〈8〉命の灯が消えても
2022年10月25日 | 2024年8月28日更新
※文化時報2021年11月18日号の掲載記事です。
弁護士という職業は、人の死に関わることが比較的多い仕事である。相続や遺言をめぐる紛争や交通死亡事故で代理人として関与することは珍しくない。殺人、傷害致死などの刑事裁判では弁護人の存在が不可欠であり、さらに被害者(遺族)側に弁護士が就くこともある。

ただでさえ近しい人を亡くし、悲嘆に暮れている当事者が、いや応なしに煩雑な法的手続きに巻き込まれ、神経を逆なでされたり、心の傷を広げられたりする。そのような当事者に寄り添い、法的な援助を行うことで、当事者の負担を少しでも軽くすることこそが弁護士の使命と心得て活動してきた…つもりだった。
私事になるが、ひと月ほど前の10月22日未明、31年連れ添った夫がこの世を去った。2年前に末期の大腸がんと診断され、切除手術を受けたが、肺にも転移していた。以来、抗がん剤治療を続けていたが、6月に急変、再入院したときには脳に転移していた。放射線治療も行ったが、もはやそれ以上打つ手がなくなったとき、夫は家に帰ることを強く望んだため、私は在宅医療・訪問看護を利用して鹿児島の自宅で夫を看取(みと)る決意をした。それぞれ別の会社に勤務する東京の息子夫婦もリモートワークを活用し、3人で夫の終末期ケアに対応した。
痛みで一晩中咆哮(ほうこう)する夫の横でひたすら夜明けを待ち、転倒のリスクからトイレの往復も目が離せず、「今日はご飯を食べた」「食べられなかった」と一喜一憂しながら過ごした2カ月間は、しかし家族水入らずの奇跡のような時間だった。最後は眠るように息を引き取る夫を家族で見送った。
押し寄せる不安を超えて穏やかな看取りができたのは、在宅医療、看護、介護のエキスパートたちの連携による的確な助言とサポートのおかげだった。何より、常に患者と家族に共感を持って接する姿に、多くのことを教えられた。
われわれ法律家は、「死」を一つの同じ事象として捉えてはいないか。実際には、命の数と同じだけ多様な死がある。だから差し伸べる手も多方向から幾重にも重ねられなければならない。
命の灯(ともしび)が消えてもなお、夫は私の進むべき道を照らしてくれている。
【用語解説】大崎事件
1979(昭和54)年10月、鹿児島県大崎町で男性の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、義姉の原口アヤ子さん(当時52)と元夫ら3人が逮捕・起訴された。原口さん以外の3人には知的障害があり、起訴内容を認めて懲役1~8年の判決が確定。原口さんは一貫して無実を訴えたが、81年に懲役10年が確定し、服役した。出所後の95年に再審請求し、第1次請求・第3次請求で計3回、再審開始が認められたものの、検察側が不服を申し立て、福岡高裁宮崎支部(第1次)と最高裁(第3次)で取り消された。2020年3月に第4次再審請求を行い、鹿児島地裁は22年6月に請求を棄却。弁護団は即時抗告し、審理は福岡高裁宮崎支部に移った。