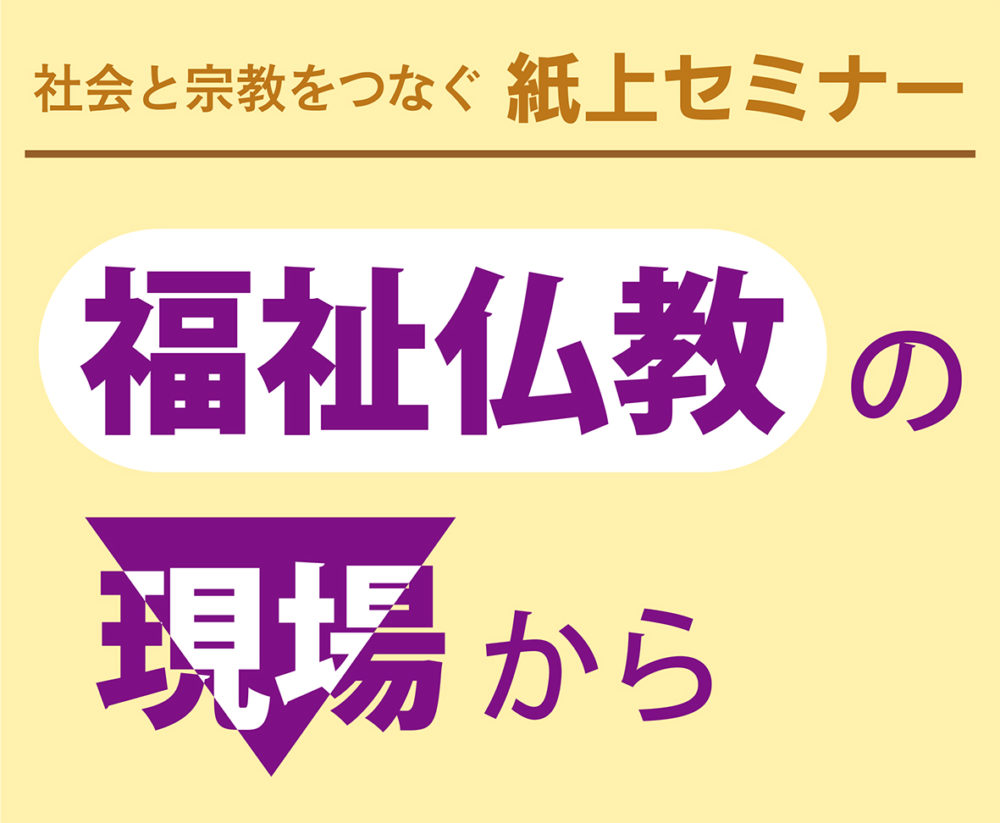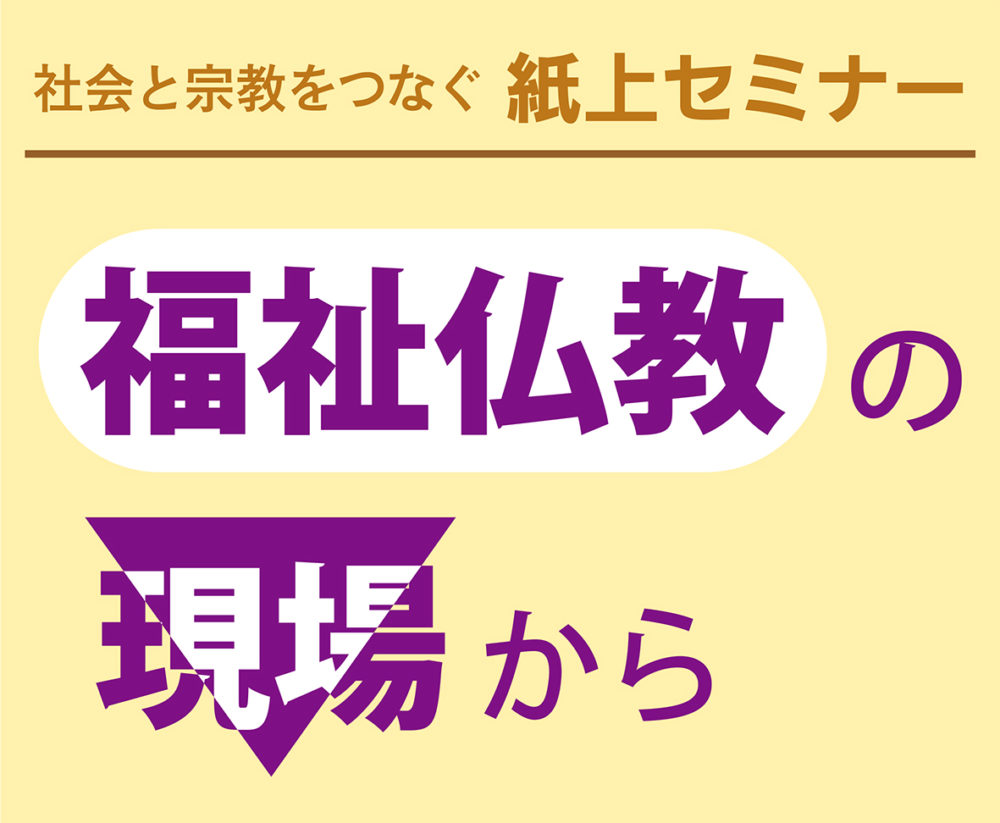読む
「文化時報」コラム
〈79〉灯台もと暗しのお寺
2024年7月11日 | 2024年10月2日更新
※文化時報2024年4月23日号の掲載記事です。
今年は桜が遅かった。
昨年より復活した春のバスツアー。瑞興寺(筆者の所属寺)のご門徒さんと一緒にお花見に出かける。毎年4月の第1週に行く。今年のように咲き始めなのは珍しい。大阪より北に位置する彦根城へ向かったのでなおさらだった。
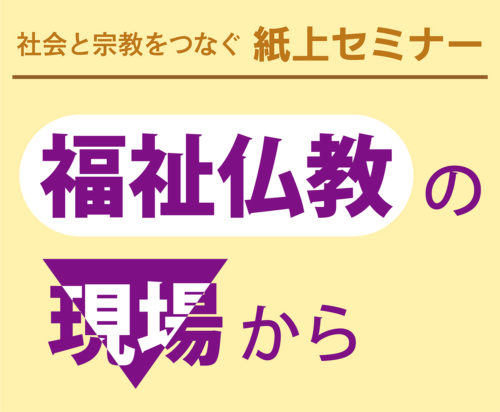
それでも雨に降られることもなく、とてもおいしい近江牛をご門徒さんらと一緒に堪能した。参加したのはご門徒さんだけではない。地域コミュニティーとして機能している安住荘へ集う人も20人ほど参加してくれた。おかげでバスは満席状態。昨今の物価高で参加費は大幅にアップされた。それでもたくさんの人が参加してくれたことが素直にうれしかった。
ご門徒さんの中には、夫が大病を患い不安と苦悩を抱える女性がいた。バスツアーにお誘いするとご夫婦で参加してくれた。夫の顔色もよく、お元気そうには見えた。バスが瑞興寺へ戻ってきた時「ああ、疲れた」と言われたが笑顔ではあった。
先日、ある坊守さんから相談を受けた。「終末期の患者さんに寄り添ってケアするような活動をしたいが何から始めたらいいのか?」ということだった。「ご門徒さんのおうちから始めたらどうですか?」とお答えしたが、「いやいや、ご門徒さんだと(お寺の出番は)まだ早いと言われちゃいますよ」とのこと。
でも、お檀家やご門徒さんへの寄り添いもできないのに、全く縁のない人に寄り添えるとは思えない。「ご門徒さん一軒一軒をよーく思い返してみてくださいな」と投げ返した。
「心のケア」が大流行している。心理系の国家資格も目立つようになってきた。それも大事だとは思う。しかし、それ以上に大切なことがある。お寺と何十年、いやそれ以上の結びつきがあるお檀家・ご門徒さんとの「関係性」だ。そこができないのに資格取得にばかり気を取られるのはおかしいと思う。灯台もと暗しになっていないか今一度振り返ってみてはいかがだろうか。