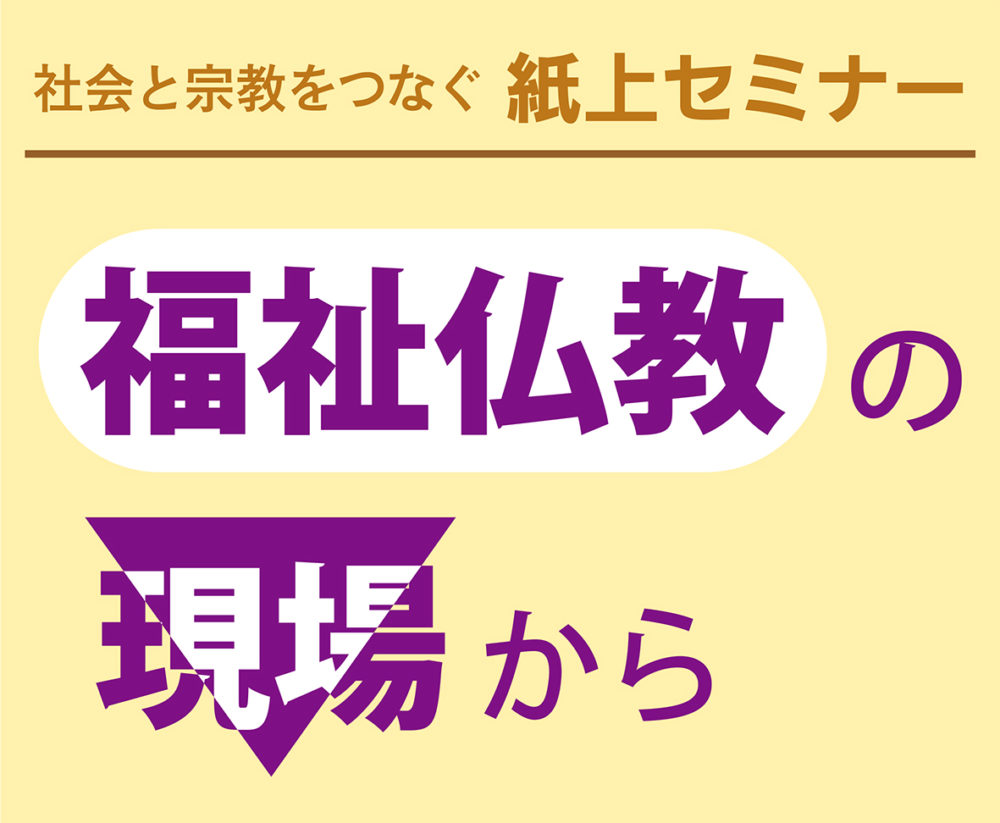読む
「文化時報」コラム
〈9〉「長谷川君」と向き合おう
2022年11月1日 | 2024年8月28日更新
※文化時報2021年12月2日号の掲載記事です。
わが国には死刑制度がある。死刑判決や死刑執行は必ずニュースとして報道される。例えば家族で夕飯の食卓を囲んでいる時間にそのニュースを聞いた人々は、どのように感じているのだろうか。

世論調査などによれば、日本国民の8割以上が死刑制度に賛成しているという。「人の命を奪った以上、命をもって償うのが当然」「被害者遺族が死刑を望む以上、死刑を廃止すべきではない」という意見が大勢だろう。
他方で、先進国で死刑制度を維持しているのはアメリカの一部の州と日本だけ、という現状もある。
私は再審弁護人として、日本の刑事裁判があまたの冤罪(えんざい)を生み出してきた実情を知っている。1980年代、一度は死刑判決が確定した4事件で、再審無罪となった4人の冤罪被害者が死刑台から生還した。これらの事件の記録を見ると「なぜこんないい加減な証拠で死刑が言い渡されたのか」「もしこのまま死刑が執行されていたら…」と背筋が寒くなる。無実の人を死刑にしてしまったら、もはや取り返しがつかないという事実は、死刑制度を考える上で決して目を背けてはならない問題である。
強盗殺人罪で無期懲役刑に処せられ、後に再審無罪となった布川(ふかわ)事件の櫻井昌司さんの死刑廃止論はシンプルだった。「国っていうのはその国の国民を幸せにするために作られた制度だよね。その国が国民を殺していい、というのはどう考えてもおかしいよ」
11月23日に浄土真宗本願寺派野洲組主催のシンポジウムに登壇した原田正治さんは、自分の弟を殺した男性を、「加害者」という抽象的な存在ではなく、一人の人間として「長谷川君」と呼んだ。長谷川君との対話のために何度も拘置所に赴いた原田さんは「長谷川君を許したから彼の死刑をやめて欲しいのではない。許せないからこそ、直接会ってお互いを知ることでしか心の平穏を取り戻すことはできない。死刑になってしまったら、永久に対話の機会が失われてしまう」と、長谷川君の死刑が執行された後も死刑制度の見直しを訴えている。
存続か廃止かの結論の前に、死刑を巡る現実やさまざまな議論を踏まえて考えてほしい。重いテーマであるが、だからこそ宗教者からの発信が待たれる。
【用語解説】大崎事件
1979(昭和54)年10月、鹿児島県大崎町で男性の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、義姉の原口アヤ子さん(当時52)と元夫ら3人が逮捕・起訴された。原口さん以外の3人には知的障害があり、起訴内容を認めて懲役1~8年の判決が確定。原口さんは一貫して無実を訴えたが、81年に懲役10年が確定し、服役した。出所後の95年に再審請求し、第1次請求・第3次請求で計3回、再審開始が認められたものの、検察側が不服を申し立て、福岡高裁宮崎支部(第1次)と最高裁(第3次)で取り消された。2020年3月に第4次再審請求を行い、鹿児島地裁は22年6月に請求を棄却。弁護団は即時抗告し、審理は福岡高裁宮崎支部に移った。