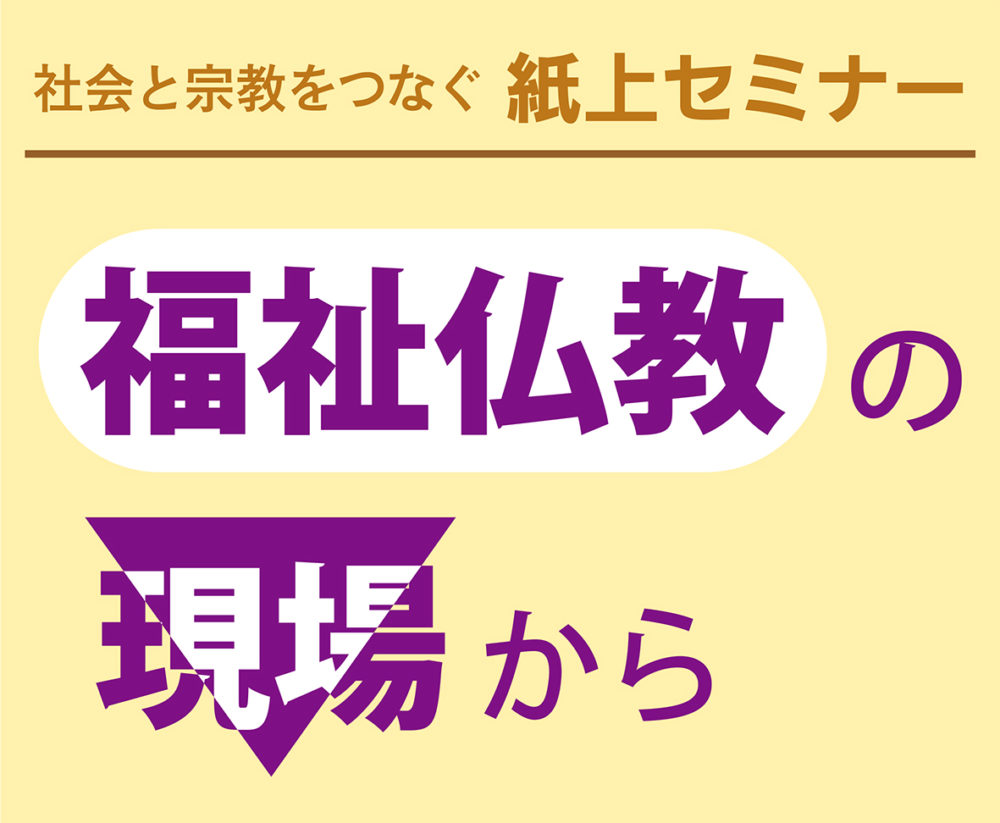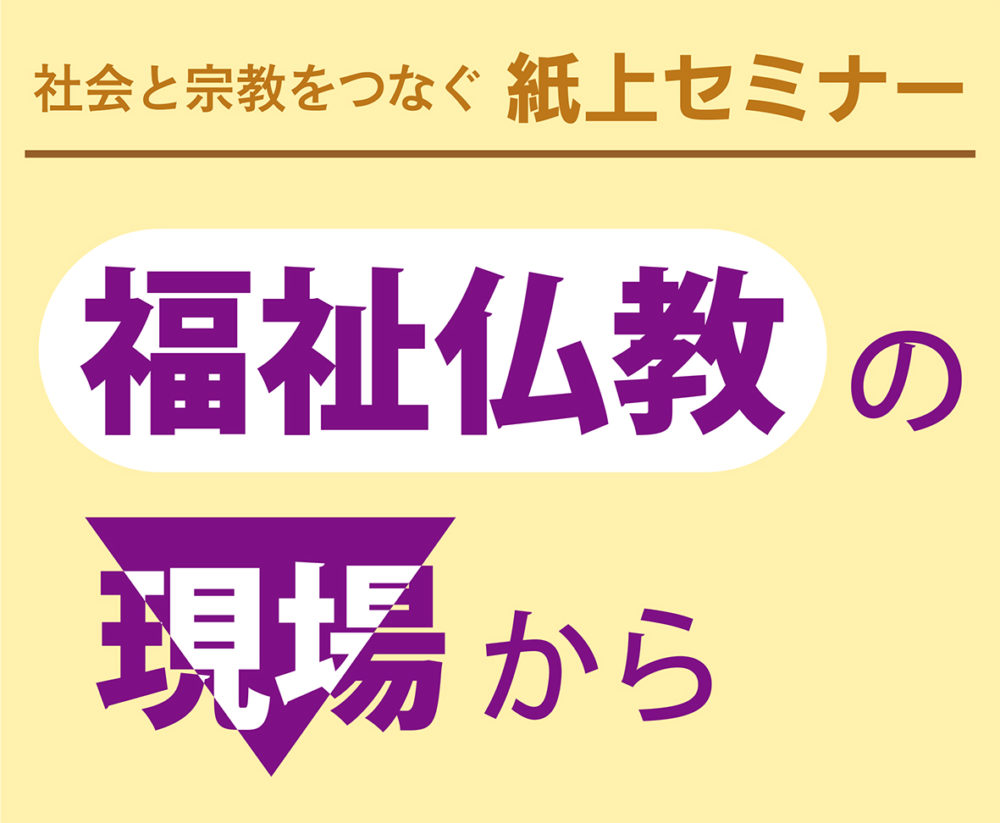読む
「文化時報」コラム
〈93〉報恩講に思う伝え方
2025年3月25日
※文化時報2024年11月26日号の掲載記事です。
旧暦11月28日は浄土真宗の宗祖・親鸞聖人のご命日である。そのご命日を縁として勤まる法要が報恩講である。浄土真宗では最も大事な法要とされている。
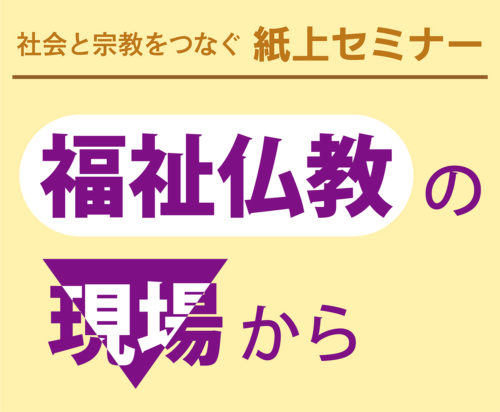
今月初め、西弘寺(伊東恵深住職、三重県松阪市)さんの報恩講に招かれ出講した。西弘寺さんは安住荘にとっては大恩人のお寺である。
安住荘が聞法道場として開かれてから約40年にわたりご法話、ご講義をしてくださったのが故・伊東慧明先生であった。松阪市から大阪市平野区まで毎月欠かさずお出ましいただいていたのである。その大恩人のお寺で法話をさせていただくことは、安住荘関係者の皆さんも大変喜んでくれた。
西弘寺さんの報恩講は、住職ご一家とご門徒さんたちが文字通り協力をして勤められていた。なかでもご門徒さんたち手作りのお斎(とき)(法要の際の食事)は、どんな高級料亭も及ばない上品な和食であった。また、法要の準備や後片付けもご門徒さんたちが手分けしてされていた。現代ではおそらく稀有(けう)なことではないかと思った。それを守り続けている住職さんのご苦労も並大抵ではないだろう。
医療の発達とともに、生を善とし死を悪として忌み嫌う人々の苦悩もますます顕著になっている。それを親鸞聖人は「生死の苦海」と表現された。そんな社会に「出離生死の道」を伝えるのが僧侶の仕事だろうと思う。
筆者は親鸞聖人の「大ファン」の一人である。だから真宗大谷派僧侶と名乗り、自身が出会い味わった体験を人前で語る。報恩講は最大級の「ファンの集い」であろう。最高の舞台である。その場にいる皆さんと一緒に喜びを分かちあいたいものである。
報恩講が勤まるというのは、関係者の皆さんには大変な労力だと思う。それでも毎年毎年勤まっていくパワーはどこにあるのだろうか? 疲弊しながらの義務感だけなんだろうか? そんなことを考えながら、次に呼ばれているお寺に参ることになる。伝え方をもっともっと勉強しなくてはならない。