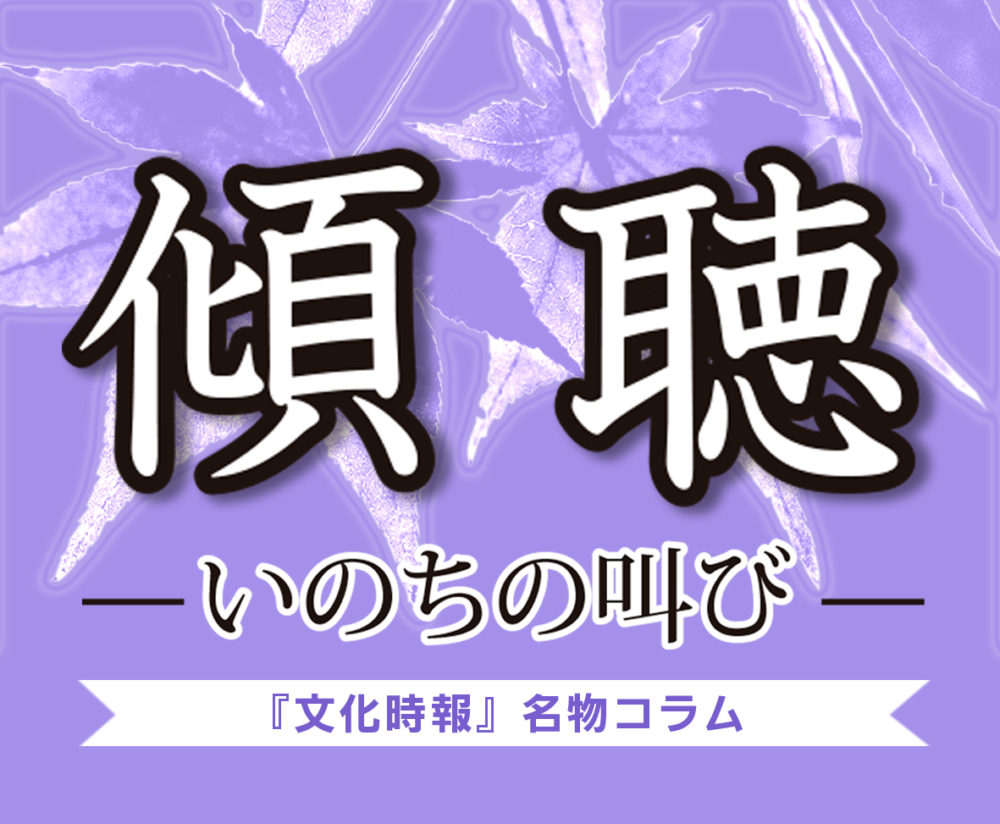読む
「文化時報」コラム
〈94〉「普通」に憧れて
2025年12月7日
※文化時報2025年10月10日号の掲載記事です。
どうしてもハト組がいいカメさんが、なんとかハト組に入りました。もちろん、カメ組も用意されているのですが、やっぱり「普通」に見えるハト組に入りたかったのです。
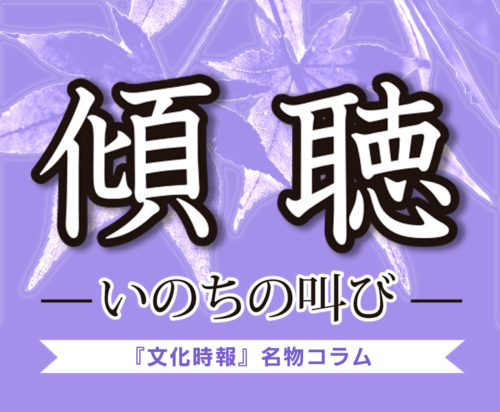
「すごいね、ハト組に入れたなんて」と、一部の人は称(たた)えました。けれどその日から、カメさんは思い知らされることになります。
ハトたちが青空へ悠々と舞い上がるとき、カメさんは地面にとどまり、ただ見上げるしかありません。
ハトたちが小さな豆をついばみ、にぎやかな輪が広がるとき、カメさんは固い殻を前に手も足も出ません。
ハトたちの追いかけっこが始まれば、カメさんも足を動かしてみるのですが、誰も振り返ってはくれませんでした。
カメさんは「普通」に憧れていました。だから、「普通」だと思われているハト組に入りたかったのです。けれどそこでの日々は、カメさんが「ハトではない」という事実を、何度も突きつけられる毎日でした。
「普通」ってなんでしょう。どんな形で、どんな匂(にお)いで、どんな色をしているのでしょう。誰も見たことがないのに、みんなが口をそろえて「普通がいい」と言います。
けれど、本当は、「普通」はたくさんあるのではないかしら。ハトにはハトの、カメにはカメの、それぞれにそれぞれの「普通」があるような気がしてなりません。
ハト組、カメ組は、決して差別ではないのです。むしろ、その命の「普通」を守るための仕組みです。ハトには空の風があり、カメには土のぬくもりがあります。ハトは風を満喫し、カメは大地を歩む―。そこに、それぞれの「普通」があるのです。
一方で、ハト組のハトたちも、実は困惑しているかもしれません。でも、声には出しません。「面倒だな」「うるさいから関わらないでおこう」「少し我慢すればやり過ごせる」―そんな気持ちで沈黙を選びます。それこそが「沈黙の差別」なのです。
カメさんが、一日も早く自分の「普通」に気付けますように。