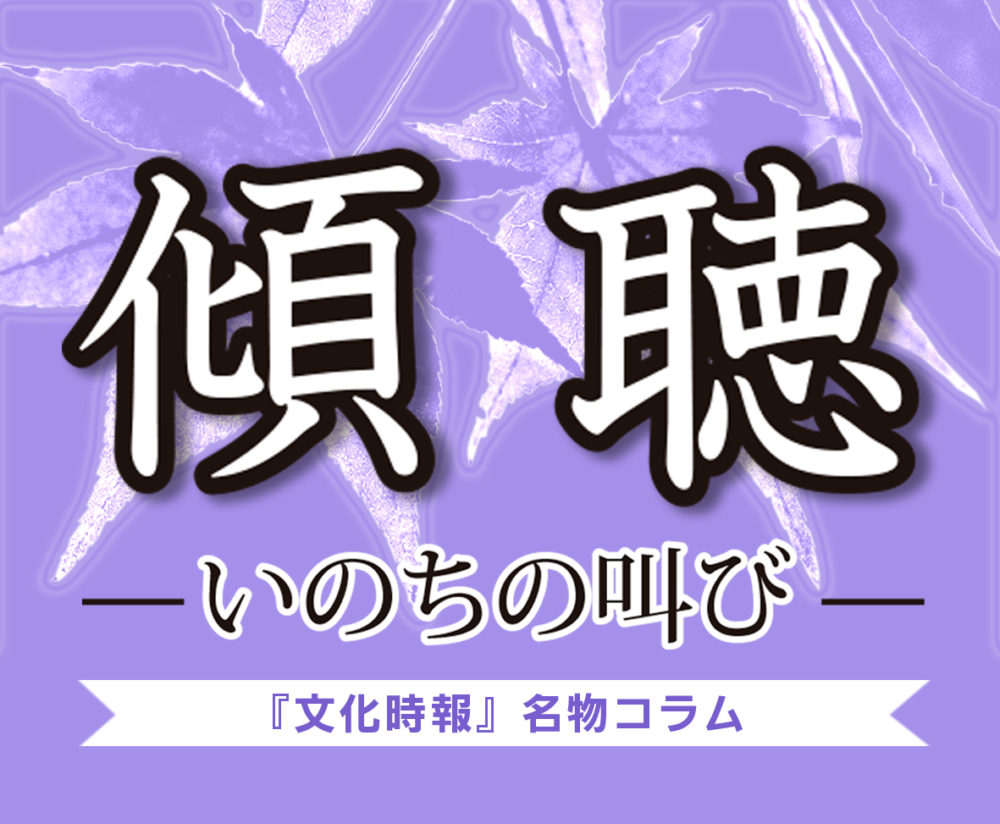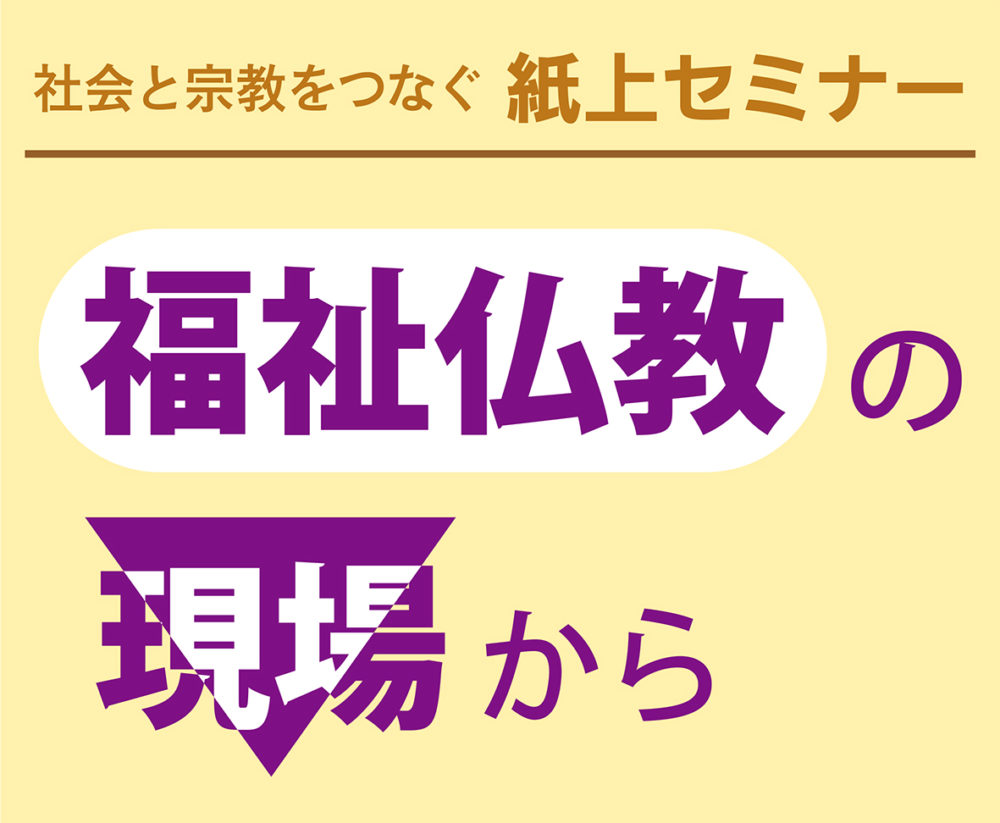読む
「文化時報」コラム
〈98〉血のつながり
2026年1月31日
※文化時報2025年12月5日号の掲載記事です。
ご長男を自死で亡くされた方がいらっしゃいました。
その悲しみの深さは、私の想像などとうてい及ばないほどで、近づくことすらできません。ぽつりぽつりと吐き出される言葉の断片から、今では次男さんとも絶縁状態になってしまっていることが分かりました。
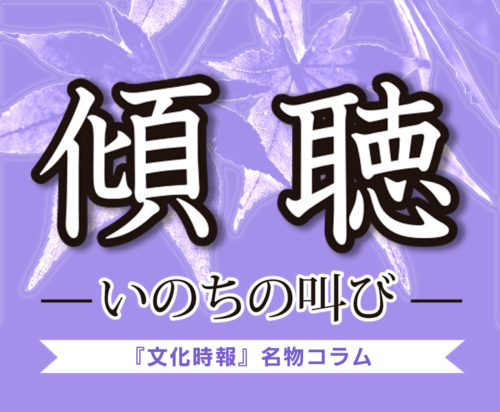
「冷たい子なんです。お兄ちゃんが亡くなったというのに、涙ひとつこぼさない」
悲しみの渦の傍らに立つ私には、手に取るように見えてくるものがあります。それは、「血のつながり」です。きっとそれが、次男さんの涙を堰(せ)き止めてしまったのでしょう。
兄の死を嘆き悲しみ、母が慟哭(どうこく)すればするほど、次男の心は引き裂かれていきます。
――カアサン、ボクヲミテヨ。ボクハココニイルヨ――。
兄が突然この世を去った当初、次男は母の肩を抱き、支えようとしました。もちろん、兄を失ったことは次男自身にとっても大きな悲しみです。母と共に、兄を悼みました。
けれども、いつまでたっても泣き止まない母の深い悲しみを見続けるうちに、次男の頭の芯は、すうっと冷えていきます。心の奥底で、こうつぶやかずにはいられないのです。
――カアサン、ボクヲミテヨ。ボクハココニイルヨ――。
長男を亡くした母の悲しみが深ければ深いほど、母と次男の溝は深まり、やがて断絶へと向かっていきます。これもまた、「血のつながり」の一つのあらわれなのです。
もし、これが赤の他人であったなら、嘆き悲しむ背中を根気よくさすり続けることができるでしょう。繰り返される後悔の言葉にも、耳を傾け続けることができるでしょう。しかし、あまりにも近すぎる関係にある者には、それが難しいことがあるのです。
血のつながりは、一度ねじれると、お互いを縛りつけ傷つけ合う枷になります。そこから完全に自由になることは、ほとんどの人にはできません。私たちはこのわずらわしい絆に絡めとられたまま、それでもなお誰かを愛さずにはいられない、哀(かな)しい生きものなのだと思います。