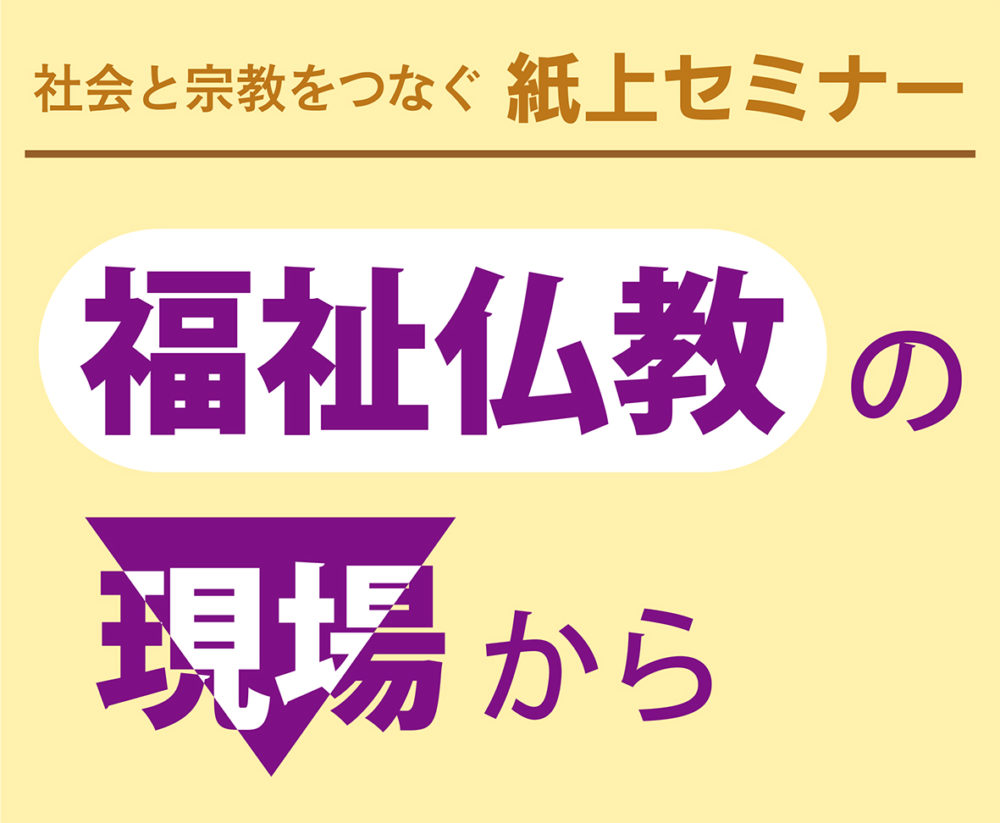つながる
福祉仏教ピックアップ
防災はお寺主導で むつ市・大安寺の先進性
2025年3月8日
※文化時報2024年11月12日号の掲載記事です。
青森県むつ市の曹洞宗大安寺(長岡俊應住職)が、行政や地域を巻き込んだ防災に取り組んでいる。長岡俊成副住職(49)が防災士の資格を取り、お寺で住民向けの学習会を開催。災害時に本堂などを避難所として使用する協定を、市と結んだ。「東日本大震災の教訓を人ごととして捉えていたという強い反省が根底にある」。長岡副住職がそう力を込める背景には、3年前に地元を襲った知られざる水害があった。(主筆 小野木康雄)

知られざる大雨
2021年8月9日。台風9号から変わった温帯低気圧の影響で、青森県下北半島は記録的大雨に見舞われた。24時間雨量が観測史上最大の369ミリに達し、大安寺が立地するむつ市大畑地区の大畑川が氾濫。標高15メートルと周囲に比べ高台にあるお寺に翌10日早朝、住民3人が避難してきた。
「誰か駆け込んでくるかもしれないと思って、鍵は開けてあった。だが実際に避難してこられると、おろおろして何もできなかった」。長岡副住職は振り返る。

長岡副住職は東日本大震災直後の11(平成23)年6月、全国曹洞宗青年会(全曹青)の広報委員として、岩手県山田町の龍昌寺を訪ねた。辛うじて津波や火災を免れ、多いときで地域住民約70人が避難していた。指定避難所でなかったため、行政から支援物資は来なかったが、普段からつながりのあった人々が食料を届けてくれた。
発災直後からの様子を清水誠勝住職に取材し、全曹青の広報誌に記事も書いた。何が役に立ち、他にどのような備えがあればよかったのか、教訓を学んでいたつもりだった。
それが、いざ自坊が水害に直面したとき、自分で備える「自助」、地域で助け合う「共助」、そして行政の「公助」がいずれも不十分だったことに気付かされた。
稲場教授が助言
記録的大雨から8カ月後の2022年4月、大安寺はむつ市に申し出て指定避難所となった。7月には長岡副住職が防災士の資格を取得。直ちに大安寺で防災学習会を開き、地域住民30人以上が集まった。「鉄は熱いうちに打て」と、大雨から1年以内に実現しようとした熱意が実った。

23年9月には、避難所運営に係る協定をむつ市と締結。民間施設との協定は、同市にとって初のケースだった。宗教施設の防災に詳しい大阪大学大学院の稲場圭信教授(宗教社会学、共生学)の助言を受けながら、避難所の開設手順や管理運営責任などを取り決めた。
大安寺は災害時、本堂と広間で最大120人を受け入れる。想定しているのは、日本海溝・千島海溝沿いを震源とした巨大地震だ。太平洋に面したむつ市大畑地区には最大10メートル超の津波が到達すると予想され、21年の大雨同様、高台へ逃れようとする人々が避難してくる可能性が高いという。
住民の主体性促す
今年2月、大安寺で静岡県が開発した避難所運営ゲーム「HUG」の体験会が行われた。長岡副住職が所属する青森県防災士会むつ支部が主催し、地元の町内会長ら約20人が参加。大人数が一斉に避難してきたら、ペットの鳥が持ち込まれたら―などのケースを想定し、意見を出し合いながらシミュレーションをした。

避難所を開設した経験がないことがHUGを行った理由だったが、長岡副住職にはもう一つの狙いがあった。住民に主体性を促すことだ。
「効率的に避難できて命が助かる仕組みは、行政の押し付けでなく、住民の手でつくるべきだ。さもないと、万一犠牲者が出たときにしこりを残す」
今月17日には、地区防災計画づくりの機運を高めようと、改めて防災学習会を開催する。東日本大震災の犠牲者の行動や人となりを遺族から聞き取る岩手県大槌町の「生きた証(あかし)プロジェクト」に参画した青森公立大学の野坂真准教授(災害社会学)を招く。
長岡副住職は「お話を聞き、災害を身に染みて感じることができれば、危機感が高まる。必ずしも公助が働くとは限らないことを見越し、共助の力を高めたい」と話している。