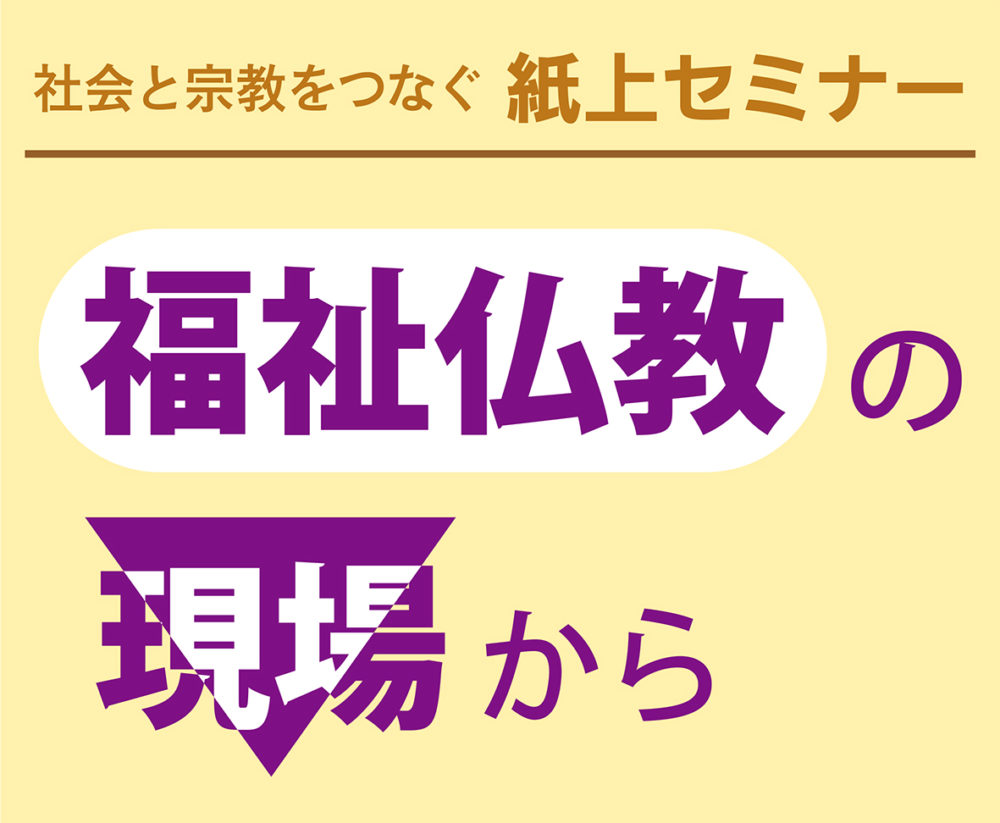つながる
福祉仏教ピックアップ
命への思いは同じ 僧侶と看護師、連携へ勉強会
2023年1月15日
※文化時報2022年11月11日号の掲載記事です。
浄土真宗本願寺派に所属する茨城県内の若手僧侶らが、福祉施設を運営するNPO法人「わ」(千葉県九十九里町)の副理事長で看護師の潮礼佳(うしお・あやか)さん(41)と交流を深め、連携を模索している。僧侶が医療者と手を取り合い、共に社会貢献を目指す取り組みだ。「看仏連携」をテーマにした勉強会を開くなど、高齢者や障害者を支える活動に乗り出す。(山根陽一)

9月7日、安楽寺(澤田唯(ただし)住職、水戸市)。本願寺派茨城東組(とうそ)に所属する若手僧侶を中心に、7人が看仏連携の勉強会に臨んだ。
まず、潮さんが長年携わっている脊髄小脳変性症の患者、佐久間勇人さん(47)がオンラインで登壇し、自らの病状や生活を語った。歩行障害、発汗障害、ろれつが回らないなどの症状が進行する難病だが、スキューバダイビングに挑戦し、電動車いすに乗って身障者スポーツの全国大会に出場している。
「障害がなかったら、全国大会に出場することはない」「新しいことへの挑戦は『できるかできないか』ではない。『やるかやらないか』だ」。前向きに生きる佐久間さんの言葉の数々を、僧侶たちは熱心に聞き入った。
参加した清心寺(茨城県ひたちなか市)の増田廣樹副住職(44)は「もがきながらも生きることの尊さを教えられた。救うことはできないが、そばにいて共に喜び、悲しむことはできるかもしれない」と感想を語った。
読経と袈裟、空気変える
次に潮さんが、僧侶とタッグを組もうと思った理由を明かした。看護師として、終末期の患者のケアに限界を感じていたのが、直接のきっかけだったという。
治らない病気にかかった患者には、医療的な措置とともに心のアプローチも必要だと考え始めた。そんな時、「お坊さんは人が亡くなっても近くにいることが許される唯一の職種だ」と思い付いた。
「心に寄り添うことが仕事である僧侶なら、心にダメージを負った障害者や高齢者の支援に必ず役立つ」。潮さんはそう強調する。

潮さんは、2018(平成30)年に僧侶が行ったイベントで増田副住職らに出会った。新型コロナウイルスの影響で連携の動きは止まっていたが、今年8月に千葉県内の有料老人ホームに増田副住職らを招き、仏壇の整理や短いお経を唱えてもらった。
当初はスタッフから「葬式でもないのに…」「宗教色が強い」との不安も聞かれたが、入居する高齢者たちは「心がスーっとした」「みんなが同じ気持ちになれた」と好評だった。
潮さんは「読経と袈裟(けさ)で場の空気を変え、患者さんの心を和ませてくれた。僧侶の存在は想像以上に大きい」と実感し、「命を大切に思う気持ちは、僧侶も看護師も同じ。連携を進めよう」と決意したという。
曖昧にして歩み寄る
2020年の国内の死亡者数は137万2648人。20年後の40年には166万人と予想され、今以上の「多死社会」を迎える。緩和ケアや家族ケアへの需要は、今後も高まるのが必至だ。
潮さんは「多様化する社会では、さまざまな死生観が生まれる。心のケアを担う人材は必要不可欠」と指摘。「一人でも多くの僧侶にサポートしてほしい」と語る。
勉強会に参加した敬西寺(群馬県高崎市)の松岡晃徳副住職は「ビハーラ活動=用語解説=の重要性は、痛感している。ただ、押しかけるのは避けたい。円滑に実践するためにも、潮さんらと今後も協調したい」と話した。
増田副住職は「治療を目的とする看護と、死のイメージが強い仏教の連携は、双方からタブー視される向きがある」と現状を指摘しつつ、「生と死はつながっており、医療と仏教の隔たりはケアされる者にとって利益にならない」と語った。
その上で、「死を境に看護から仏教へバトンタッチするのではなく、その間を曖昧なままにするのも一つの方法では」と提案。「曖昧だからこそ、互いに歩み寄って協調する。仏教が医療・介護に貢献する可能性が生まれる」と将来を見据えた。
明日を担う若手僧侶と看護師が、手探りながらも意気投合し、スタートを切った。
【用語解説】ビハーラ活動(浄土真宗本願寺派など)
医療・福祉と協働し、人々の苦悩を和らげる仏教徒の活動。生老病死の苦しみや悲しみに寄り添い、全人的なケアを目指す。仏教ホスピスに代わる用語として提唱されたビハーラを基に、1987(昭和62)年に始まった。ビハーラはサンスクリット語で「僧院」「身心の安らぎ」「休息の場所」などの意味。