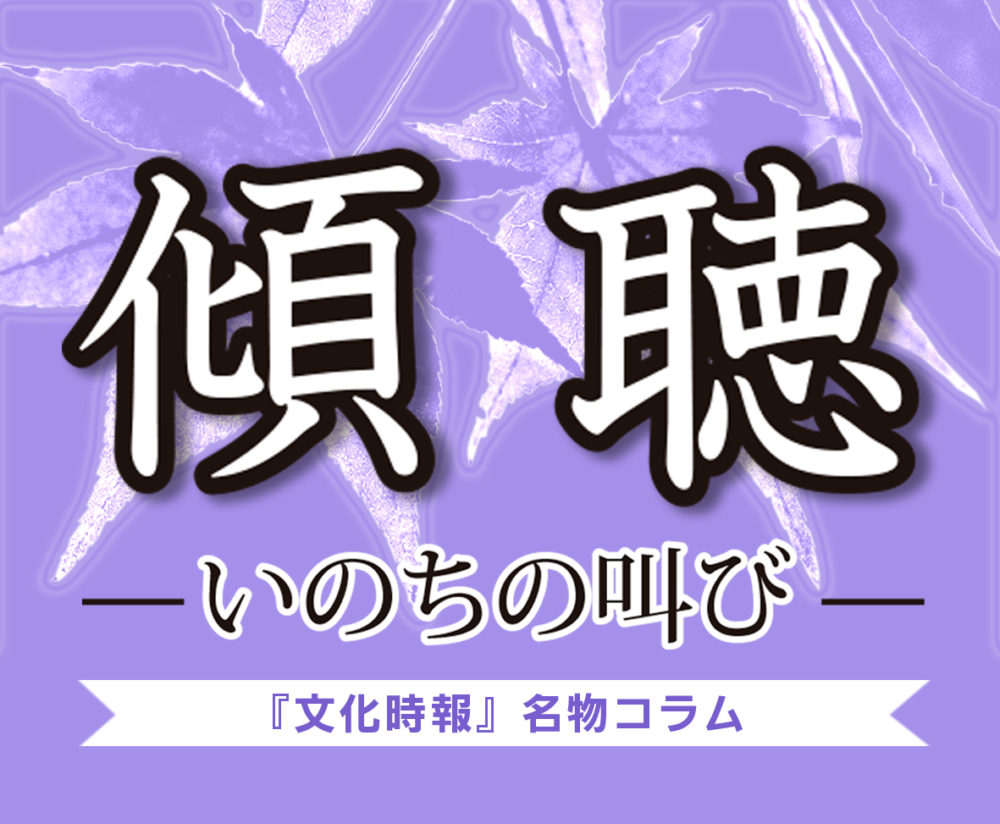つながる
福祉仏教ピックアップ
看仏連携、修士論文に 熊本地震・コロナ禍越え
2023年3月29日
※文化時報2023年1月31日号の掲載記事です。
医療・福祉の現場で看護師と僧侶が協働する「看仏連携」に着目して修士論文を書き進める若き僧侶がいる。龍谷大学大学院実践真宗学研究科3年、保々光耀(ほぼ・こうよう)さん(25)。真宗大谷派の僧侶でありながら浄土真宗本願寺派の宗門関係校に入り、宗派や職種、年代を問わず、さまざまな人々と縁を結んできた。故郷を襲った2016年の熊本地震やコロナ禍の苦難を乗り越え、今春、新たな道へと進む。(主筆 小野木康雄)

「寺院での『まちの保健室』の可能性についての一考察―寺院・僧侶の役割に着目して」。保々さんの修士論文のタイトルだ。看護師が病院の外に出向いて地域住民の健康チェックや相談に乗る「まちの保健室」を取り上げ、開催している全国4カ寺を調査した。
元々ビハーラ活動やその周辺領域に関心があり、臨床宗教師=用語解説=の研修も受けていた。龍谷大学大学院で非常勤講師を務める看仏連携研究会の河野秀一代表の講義を聴講し、研究テーマにすると決めた。
調査した4カ寺の一つ、本願寺派妙行寺(鹿児島市)での取り組みを昨年3月に見学した時のこと。来場者と話していた保健師に「ちょっと」と声を掛けられ、会話に加わった。何げない話題から、ふと「お勤めで上げたお経の意味を教えてほしい」と頼まれた。身内を亡くしたばかりで、グリーフ(悲嘆)を抱えていた。
「まちの保健室は、相談事がお寺に集まるコンテンツの一つになる。お寺になら、日常にはないごちゃまぜの場がつくれる」。そう考えるようになった。
「話す」から「聴く」へ
実家は大谷派光行寺(熊本県大津町)。住職を務める父から「僧侶にならなくてもいいが、人生の中で仏教に触れてほしい」と言われて育った。進学先に選んだのは、父、祖父、そして兄も進んだ宗門関係校の大谷大学ではなく、龍谷大学。「せっかくなら、違う道を通って仏教を勉強したい」と考えた。
16年4月1日の入学式から2週間後、熊本地震が起きた。大津町は14日の前震で震度5強、16日の本震で6強を観測し、自坊も被災。本堂は全壊と認定され、基礎を残して建て替えを余儀なくされた。
ゴールデンウイークに帰省し、片付けを手伝った。大変な状況でも、家族は「勉強してこい」と背中を押してくれた。つらい思いをしたはずの友人からは「京都にいて、よかったと思うよ」と明るく励まされた。返す言葉が見つからなかった。

そうしたとき、九州臨床宗教師会のメンバーらが、被災者の傾聴に取り組んでいることを知った。「僧侶は法話や説教をしたりお経を読んだりして『話す』というイメージがあったが、『聴く』僧侶がいることに驚いた」
自分も学びたい、と強く思った。
鹿児島の本願寺派寺院に就職
実践真宗学研究科に進んだ20年は、コロナ禍が全国を覆った年だった。授業はリモートに、実習は相次ぎ中止や延期に。学内に入ることさえままならず、図書館は予約しなければ行けなかった。行動制限がある時でも、学ぶことは怠らなかった。
オンラインで、普段は聴聞に行けない遠方の僧侶の法話を聴いたり、学外の人々と職種や年代を超えて交流したり。文化時報の「福祉仏教入門講座」も受講し、「『伴走型支援』という言葉を初めて知った。僧侶とは何かを問い直すいい機会になった」と語る。
修士論文でお世話になった妙行寺に、4月から僧侶として就職する。地域包括ケアシステム=用語解説=の中心に寺院があるという感覚を持ち、グリーフケアに携われる僧侶が必要だから―と、井上從昭住職に誘われた。
「宗派は違っても、同じ教えを頂いているので抵抗感はない」。まず自分自身が仏法を大切にして、困り事を抱える門徒や地域住民と共に悩み、少しでも力添えをしていこうと考えている。
「人知れず熱心に社会活動をする方や、生活者として布教や法話に力を入れている方など、尊敬できる僧侶たちに大勢出会ってきた。自分もいいバランスを持って、仏教に生き、社会と関わりたい」。希望を胸に、鹿児島へ旅立つ。
【用語解説】臨床宗教師(りんしょうしゅうきょうし=宗教全般)
被災者やがん患者らの悲嘆を和らげる宗教者の専門職。布教や勧誘を行わず傾聴を通じて相手の気持ちに寄り添う。2012年に東北大学大学院で養成が始まり、18年に一般社団法人日本臨床宗教師会の認定資格になった。認定者数は21年9月現在で214人。
【用語解説】地域包括ケアシステム
誰もが住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らせる社会を目指し、厚生労働省が提唱している仕組み。医療機関と介護施設、自治会などが連携し、予防や生活支援を含めて一体的に高齢者を支える。団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに実現を図っている。