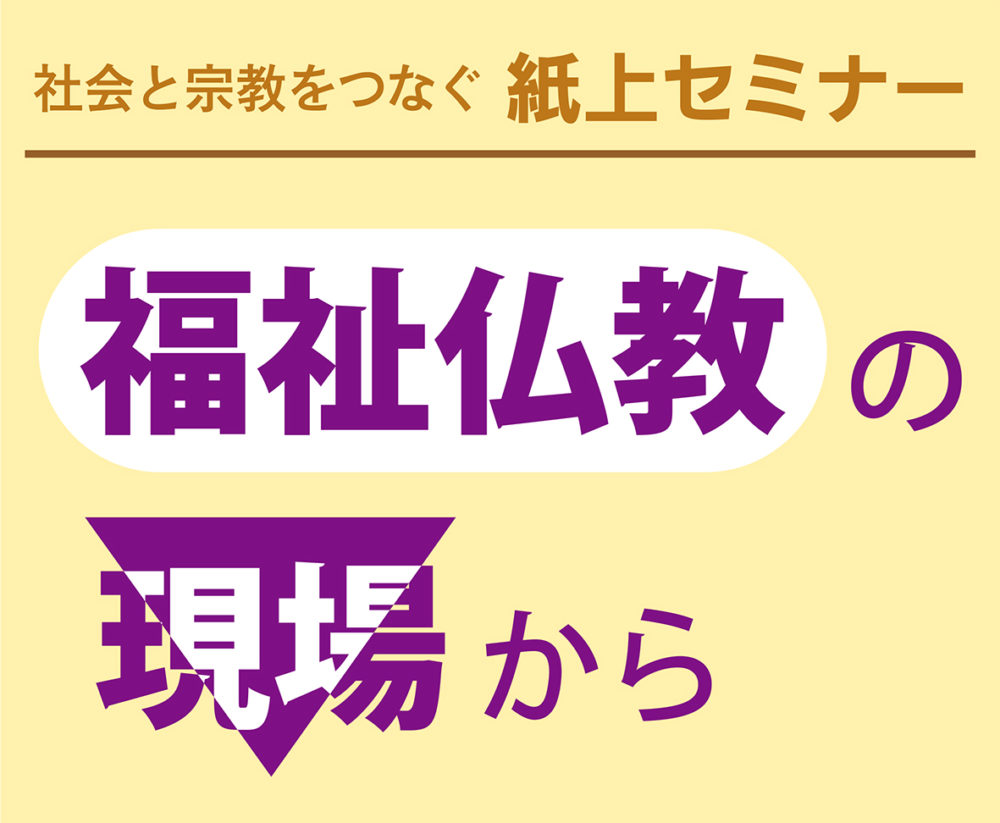つながる
福祉仏教ピックアップ
〈文化時報社説〉高等教育は全面無償化を
2024年8月15日
※文化時報2024年6月14日号の掲載記事です。
文部科学省の審議会で伊藤公平・慶應義塾長が、国立大学の学費を年間150万円に引き上げてほしいと提案したことが波紋を広げている。妥当な意見かどうかはともかく、高等教育にかかる費用は誰が負担すべきなのか―という議論の入り口にはなった。私立大学を持つ宗教教団にとっては、国立大学との公平な経営環境という観点からも関心の高い話題だろう。

伊藤塾長が学費値上げを提案したのは、3月27日に行われた中央教育審議会(中教審)の特別部会の会合だ。特別部会は、2040年以降の社会を見据えて目指すべき高等教育の姿を議論する場である。
委員である伊藤塾長は、高度な大学教育には学生1人当たり年間300万円が必要とした上で、国立大学ではこのうち半分の150万円を家計が負担すべきだと主張した。これは、文部科学省令による国立大学の授業料標準額53万5800円の約3倍という水準だ。
この提案が報じられると、「低所得層が進学を諦めるケースが増える」といった懸念の声が相次いだ。
経済協力開発機構(OECD)が23年に公表した調査によれば、日本では高等教育段階での私費負担の割合が64%に上る。加盟国平均(30%)と比べ突出して高く、公的支出全体に占める教育支出の割合が低いことが原因なのだという。
伊藤塾長の提案通りなら、私費負担の割合はさらに高まることになる。結果、裕福な家庭しか子どもを大学に進学させられない事態に拍車を掛ける。教育の機会均等を定めた教育基本法の理念に反するのではないか。
保護者の年収と大学進学率には相関関係があることが知られている。進学を諦めた子が家庭を持つと、大卒者より収入が低いため学費を賄えず、わが子の進学をも断念せざるを得なくなる―といった負のスパイラルに陥る。
こうした格差の固定化を打開する政策が、高等教育の無償化だ。国は高等教育の無償化を20年度から始めているが、現状では住民税の非課税世帯や子どもが3人以上の多子世帯などに対象が限られている。これらの条件を撤廃し、あらゆる学生の学費を無償化すべきではないか。
「富裕層までタダにすることはない」「受益者負担が必要だ」との指摘はあるだろう。だが、所得制限はどこで線引きしても不満を生み、分断と対立を招く。
そもそも、教育における受益者とは誰なのか。
思想家の内田樹氏は著書『コモンの再生』(文春文庫)で「本当に必要な政策は『教育の全部無償化』」だと唱えた。最初の受益者は好きな学問ができる子どもたちだが、ひいては「日本社会そのものが受益者になる」と看破した。無駄に見える研究に打ち込んだ先人たちがイノベーションを起こしたり、ノーベル賞級の発見をしたりした事例は、枚挙にいとまがない。極めて妥当な意見である。
高等教育の受益者負担を訴えるなら、国民全体すなわち公費負担がふさわしいということになる。完全無償化が実現して初めて、私立大学も国立大学と同じ土俵の上で競い合えるはずだ。