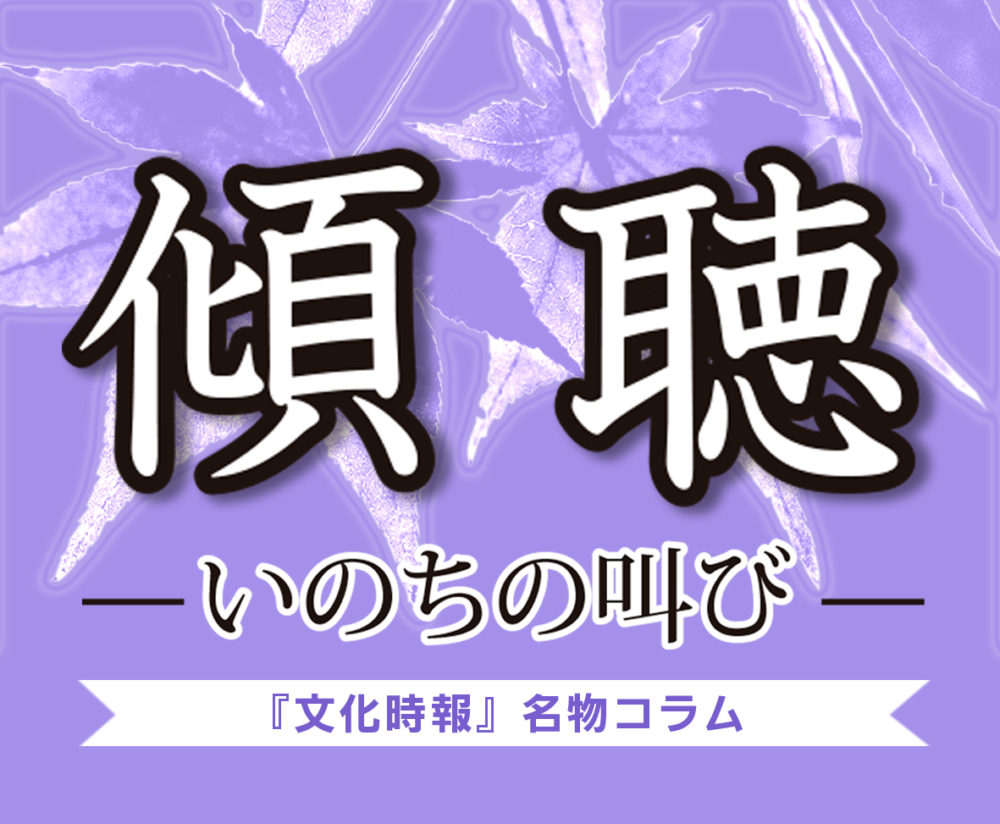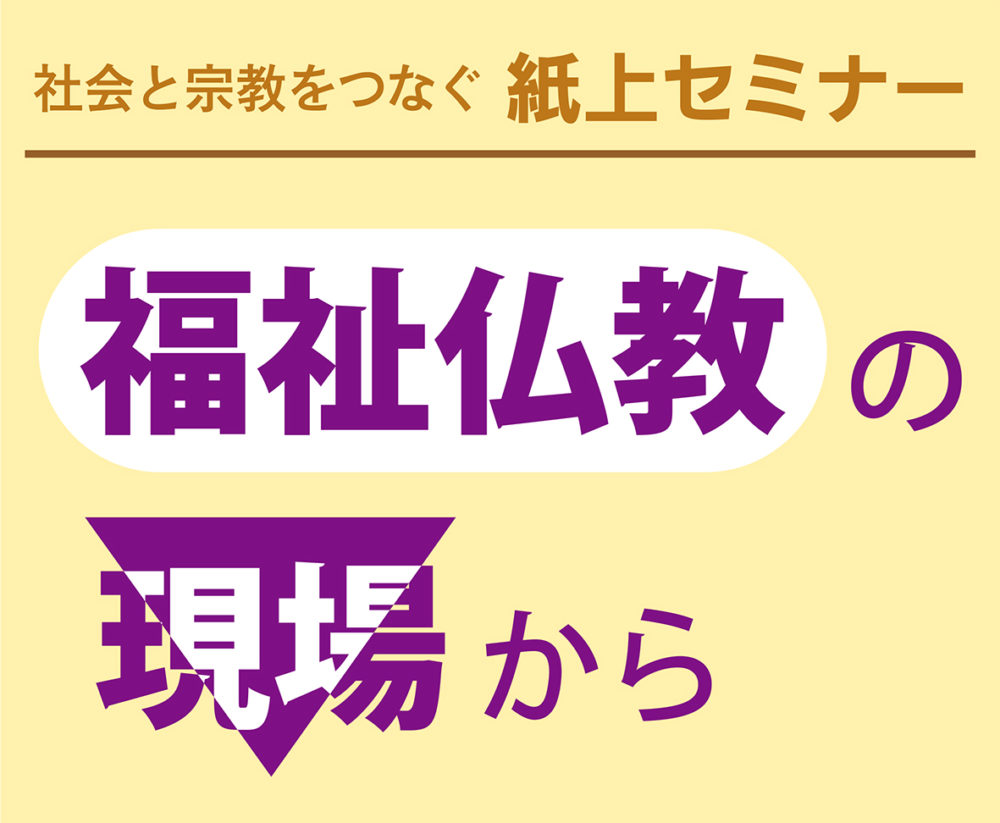読む
「文化時報」コラム
〈76〉「自分」の髪の毛
2025年3月21日
※文化時報2024年12月6日号の掲載記事です。
修行中、女性ばかり十数名の修行僧のうち、半分は剃髪(ていはつ)し、残りの半分は有髪でした。
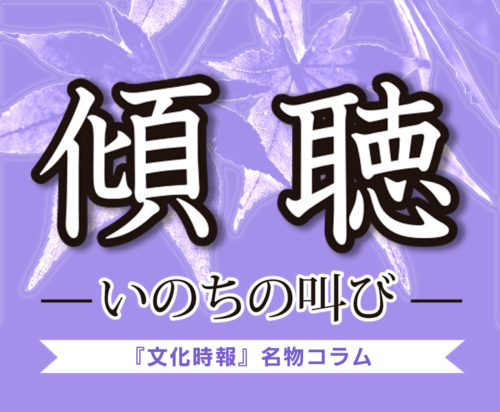
修行僧の役割は、まずは下座行。塵(ちり)一つないように磨き上げるのですが、落ちるんですよね、髪の毛が。洗面所に、浴室に、廊下の隅に、パラリと落ちているわけです。それが見つかると連帯責任で初めからやり直しですから、おのずと皆の神経もピリピリしてきます。
ある日、いったい誰の仕業だという話になりました。その時、寮監さんがこんな話をしてくださったのです。
「髪の毛が頭から生えている。それを誰かに引っ張られたら『私の髪を引っ張らないでください』と言うでしょう。その髪が抜け落ちて肩に乗っていた。誰かにそれを『あなたの髪が肩についていますよ』と指摘されたら『ああ、ありがとうございます』と言って払うでしょう」
「さて、その髪が床に落ちて廊下の隅に吹きだまっているのを見た人に『あれはあなたの髪だから片付けなさい』と言われたら、『いや、あれは私の髪ではないです』と言いたくなるのではないですか? このことをよく考えてみなさい」
私が、この貧相な脳みそでよくよく考え見つけだしたことは「どこからが『自分』で、どこまでが『自分』なのか、その境は実に曖昧だ」ということです。
どうやら「自分」というのは、まるでドーナツの穴のように、周りに集まってきたものによって、さもあるかのように見えるだけのもののようです。
ある患者さんが「寝たきりになって散歩もできない。こんなのは私じゃない。もう死んだ方がましだ!」と嘆いていました。さぞおつらいでしょう。でも、こんなふうに考えてみることもできませんか。
まるで幻のような「自分らしさ」にいつまでもしがみついているのはやめて、流れに乗ってどんどん変わっていく。その変わっていく自分を楽しむ。だって、そもそも、この世は「諸行無常」なのですから。