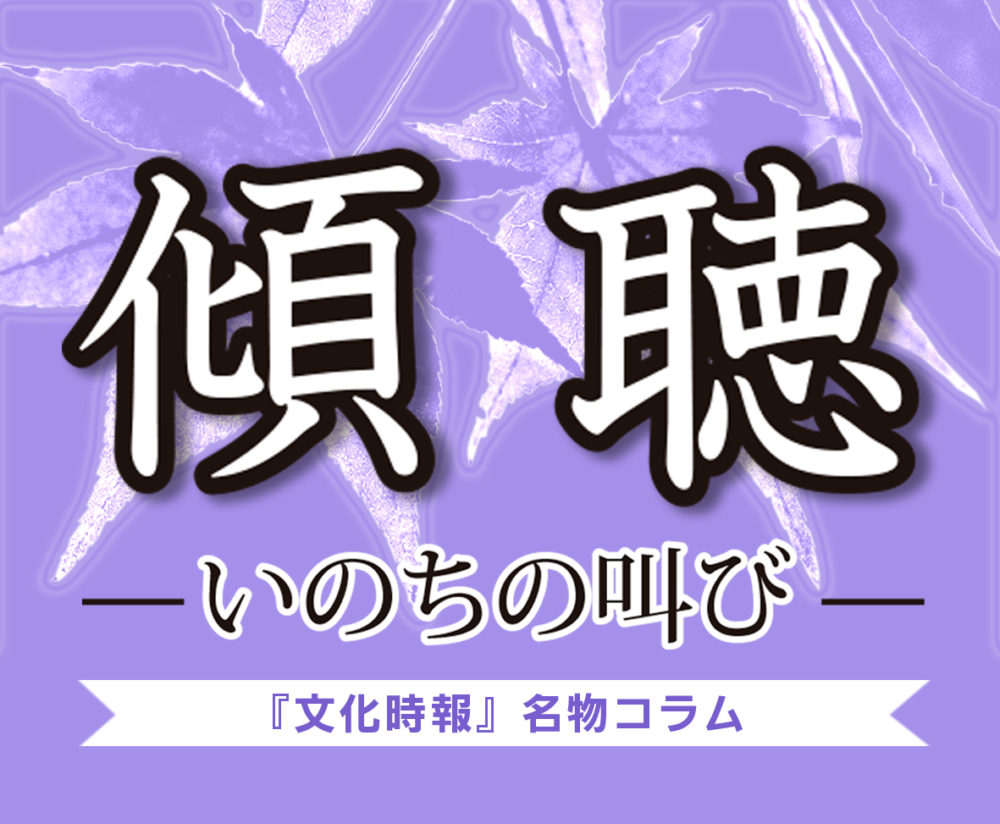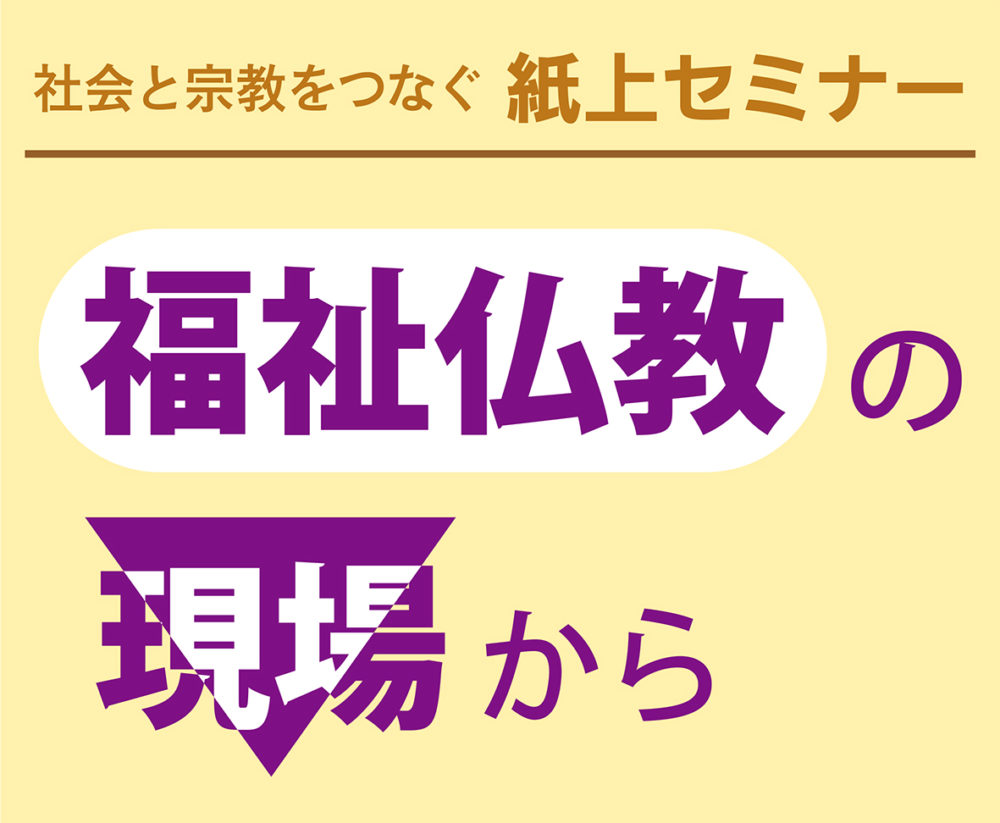読む
「文化時報」コラム
〈77〉お伊勢参り
2025年4月3日
※文化時報2024年12月20日号の掲載記事です。
先週末、仕事の関係で三重・松阪にお邪魔させていただいたので、ついでと言ってはなんですが、少し足を延ばして伊勢神宮を参拝しました。年末詣で活気づく境内を歩いていると、ふいに、あの時の一場面が鮮やかによみがえってきました。
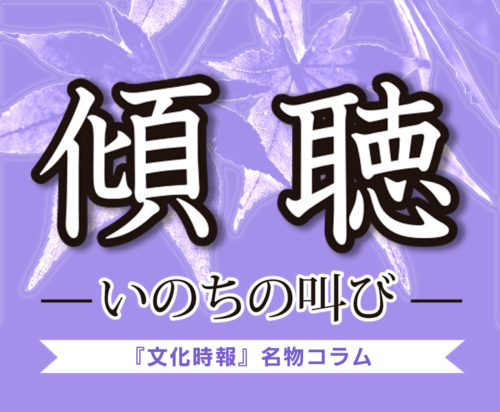
10年ほど前になるでしょうか。たまには家族サービスをしようと思い立ち、両親を誘い子どもたちも連れてお伊勢参りに出かけたのです。
その頃、今は亡き父は、年相応に足元がおぼつかないところもあったので「気をつけて」と声をかけながらの参拝でした。
ところが、正宮に続く石段を上る途中、ちょっと目を離した隙に父が転び、石段に胸をしたたかに打ちつけたのです。
慌てて駆け寄り父の体を起こしました。痛さにゆがんだ顔を見て、その後の予定を中断するか迷いましたが、最終的には「大丈夫、大丈夫」と繰り返す父の言葉をうのみにして、そのまま行程を進めました。
しかし、その夜の宿で打ったところを見せてもらうと、青紫色のあざが広がっているではありませんか。驚いて「病院に行こう」と提案しましたが、父は笑って「大丈夫だこれくらい」と言うばかり。結局そのときも押し切られて、最後まで計画通りに旅を続けたのでした。
今になって思い返せば、おそらく肋骨(ろっこつ)の一本くらいは折れていたのではないかと思います。それでも父は「痛い」の一言も漏らさず、旅の終わりまで機嫌良く私たちに付き合ってくれました。
最近、自分も肋骨骨折を体験して、息をするだけでも痛み、横になるのも起き上がるのも痛い不便さを味わいながら、しみじみ思うのです。父もさぞかし痛かったに違いないと。そんなそぶりを一切見せなかったのは、きっと私が奮発した旅を台無しにするまいと思ってくれたのでしょう。
なぜ、もっと見ていなかったのか。
なぜ、もっと気遣えなかったのか。
今日、あの日と同じ石段で悔やむ私の肩に、まるで声をかけてくれるかのように、木の葉がはらはらと落ちてきました。