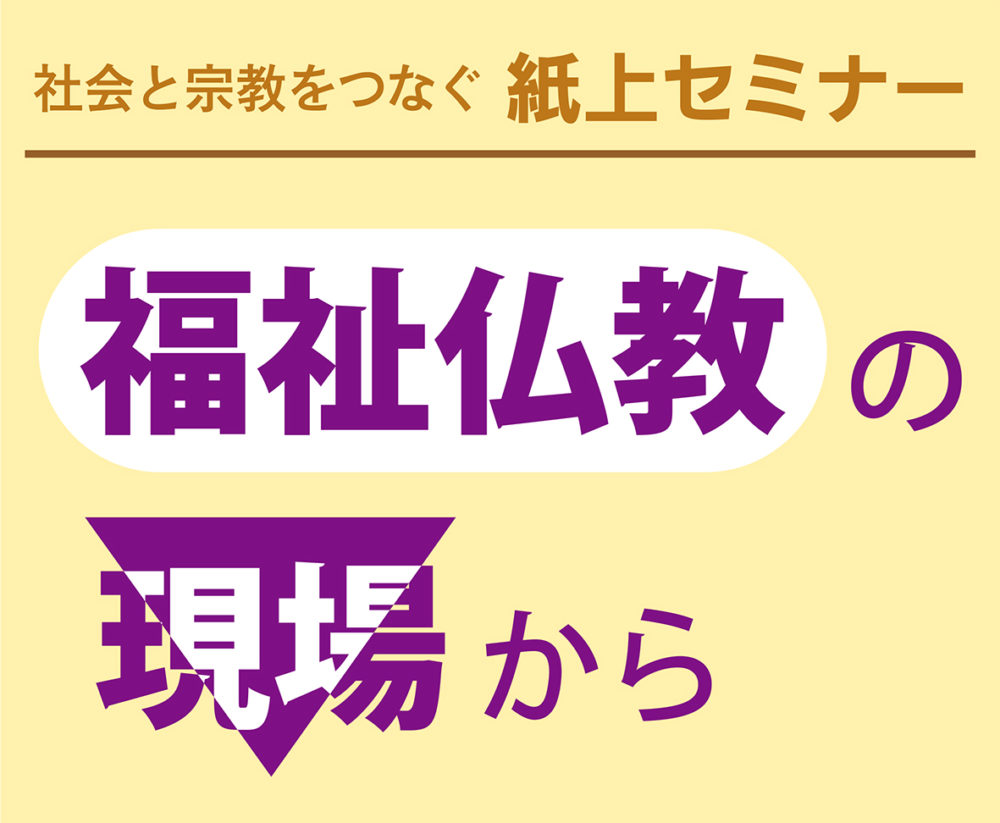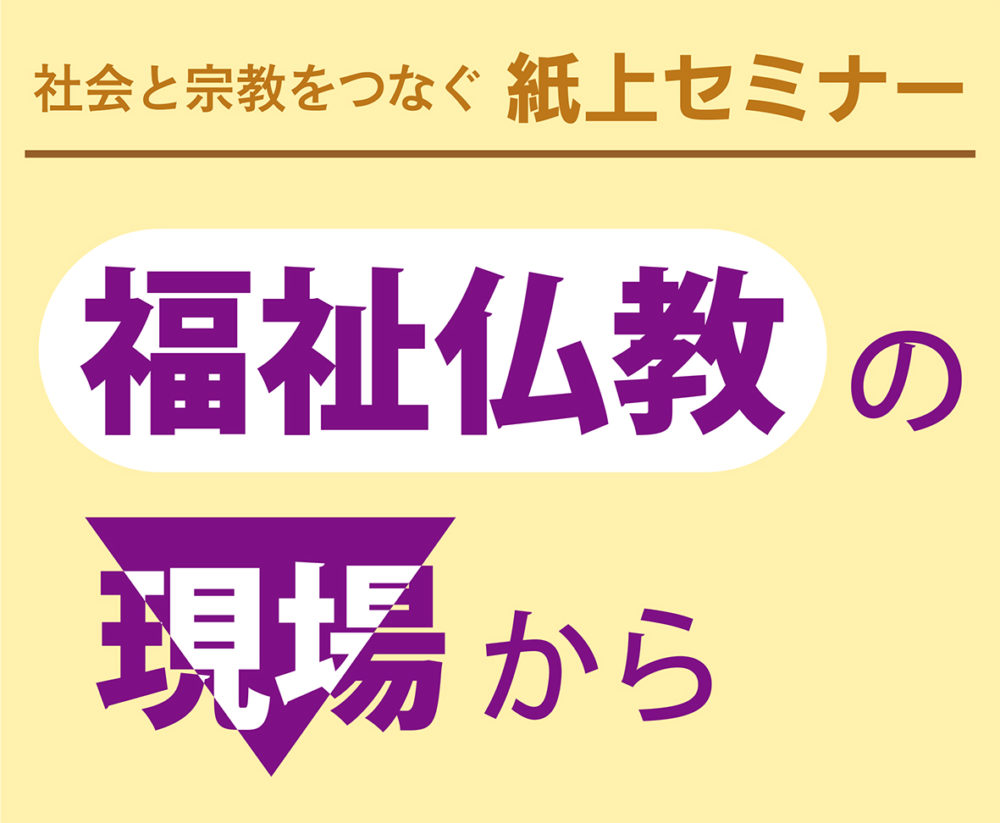読む
「文化時報」コラム
〈94〉「私ならこうする」
2025年4月6日
※文化時報2024年12月10日号の掲載記事です。
「文化時報 福祉仏教入門講座」第6期が全ての日程を終えた。最終の第7講はケーススタディーとして、実際に相談があった事例を元に「私ならこうする」を話し合っていただいた。架空の話ではないので顚末がある。それは筆者の「私ならこうする」であって正解ではない。正解はそれぞれの現場(お寺や教会)にある。
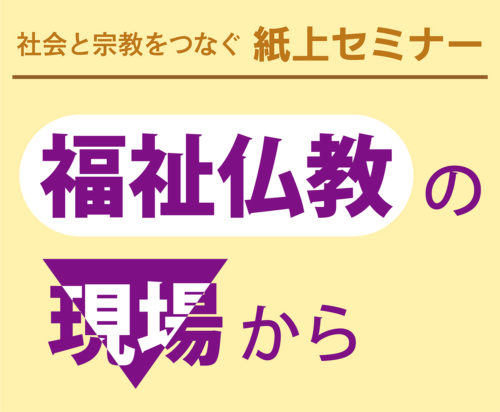
筆者は主に医療や司法と連携する福祉仏教を展開している。医療に関わる人、司法に関わる人それぞれが苦悩している。医療や司法には人間が生きていく苦悩が集約されている。苦悩に一緒に向き合い、親鸞聖人のお言葉を伝えるのが筆者の「私ならこうする」である。
人生100年時代といわれる少子超高齢社会は、「死」よりも「老病」とどう向き合うかという課題が突きつけられている。お寺や教会が「葬儀からが出番」のような時代ではもうない。「介護から寄り添う」という姿勢が必要だろう。それが福祉仏教である。
葬儀は「家族の死」を機縁に如来に出遇う大事な仏事であった。昨今は葬儀社のCMがテレビやインターネットで流れセレモニービジネス化している。それでは、多くの人が如来と出遭(あ)う機会が奪われてしまう。「百千万劫(ひゃくせんまんごう)にも遭遇(あいあ)うこと難(かた)し」をもう一度かみしめたいと思う。
「福祉仏教入門講座」第7期は来年2月から開講され、月1回全7回の講義がある。人々の苦悩に寄り添い耳を傾けるということはどういうことなのかを、一緒に考えていただけると幸いである。そして「私ならこうする」を見つけてほしいと期待している。
医療従事者から仏教への期待の声は年々高まっている。小欄で再三お伝えしている通りである。「お坊さんがやってくれないなら、私が仏教を勉強して…」という医師や看護師も多い。仏教を勉強していただくのはとても尊いことだとは思うが、それを伝える役目は何十年もの経験を積んでいる僧侶に任せた方がいいだろう。
本で読んだ知識を伝えるだけなら、みんなが本を読めばいい。仏教は知識だけではないように思うが、いかがだろうか?