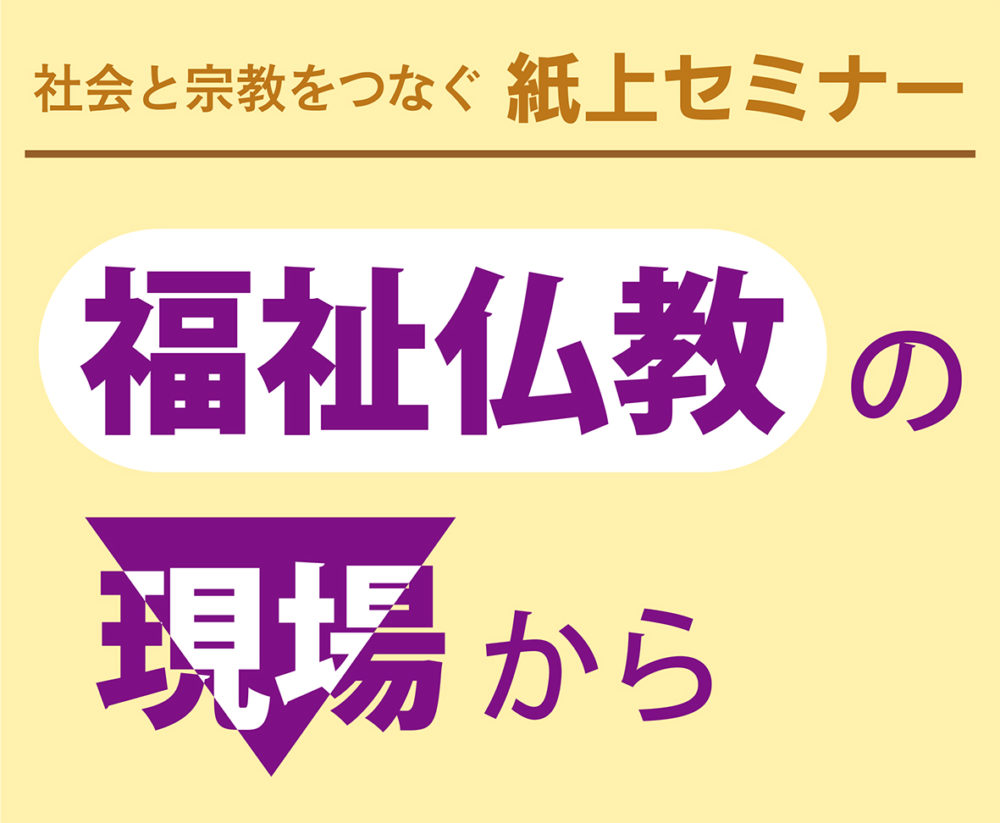読む
「文化時報」コラム
〈10〉今日この日はあなたのためにある
2025年5月20日 | 2025年5月20日更新
※文化時報2025年2月18日号の掲載記事です。
刑務所での生活を送る日々、私は必死でノートに何かを書き続けていた。過去の思い出や日々のたわいのない出来事、感じていることやみんなへの思い。とにかく書き続けた。

ペンを走らせ続けたのは、何かを表現したいという思いからではなかった気がする。ずっと怖かった。私という人間が懸命に生きてもそれを知るのは目の前に時々やってくる刑務官くらい。2008年、2007年の何月何日、私は確かにここに生きていたけど、誰とも会えない日々は全ての人たちの中から私を忘れさせていくとしか思えなかった。
もし唯一の自分の記憶が忘れ去られたら、その事実を知る人はいなくなる。本当にここに自分の生きた一日があったのかさえ、誰にも証明できなくなる。たとえちっぽけであまりにも貧弱で無意味にしか思えない一日でも、その日を確かに生きた自分をせめて自分だけは忘れたくない。苦悩だらけで何の生産性もない一日だったとしても、自分だけはちゃんと知っていてあげたい。
刑務所という獄舎にいる孤独感や絶望感以上に、誰からも何からも、自分という存在とここで生きた事実が忘れ去られていく恐怖でいっぱいだった。周囲の全てから忘れ去られたら、本当にここに自分が生きた一日があるのかさえ分からなくなる。ないに等しいんだと痛感した。
だから、自分だけはちゃんと知っているよ。確かに洋次郎はここに生きていたね。数千年の時の流れの中のほんの一瞬の今日かもしれないけど、私はここに生きていたんだ―。私は証しのように書き続けた。
刑務所に限らず、いろいろな環境下において苦しい生活を強いられる人たちがいる。確かにそこに生きる人たちが、社会から忘れ去られる事実。いる人をいる人としない社会を感じる。そこにある恐怖を思う。
あるドキュメンタリー映画で、受刑者に向けて刑務官が一人一人の部屋の前に行き、「今日は君のためにある! 今日はあなたの一日だ!」と声をかけていく場面があった。
社会から隔離された刑務所で、誰からも忘れ去られる。ここに生きていた事実さえ誰にも知ってもらえていない。その苦悩や恐怖を知っているからか、そのシーンに涙があふれた。