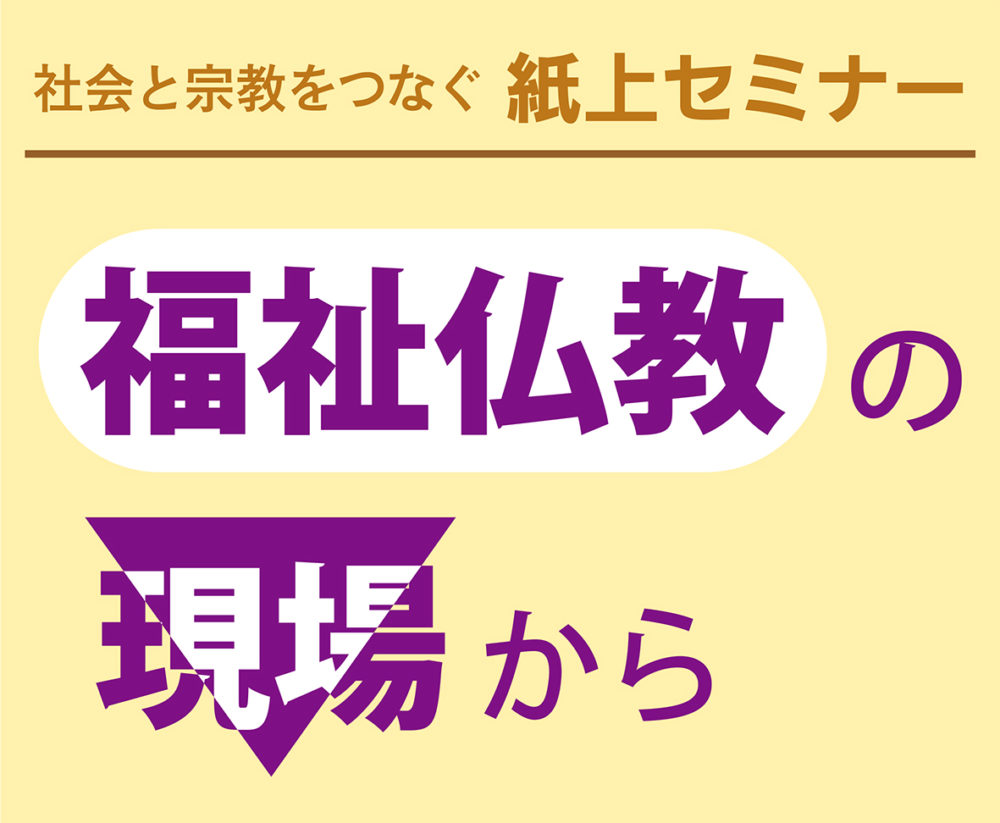読む
「文化時報」コラム
〈12〉家族への手助け(下)
2025年6月29日
※文化時報2025年3月18日号の掲載記事です。
私は20歳から精神科病院への入退院を繰り返した。

入院生活をしている間も、母親はやれ小遣いをくれ、やれ外出したいから迎えに来い、と息子から散々言われる。母親はペットボトルを使い回して家でお茶を入れて凍らせ、真夏の炎天下に持参してきているのに、息子はまっさらの缶コーヒーや缶ジュースを当たり前のように買って飲んでいた。
刑務所服役中もいろいろ言い合いがあった。息子の身元引受人になる、ならないをずっと話し合っていた。しかし途中で母親からはっきりと「身元引受人にはなれない」と告げられた。
その頃は知らなかったが、母親は薬物依存症者を家族や友人に持つ人の「ナラノン」という自助グループに参加するようになっていた。どんな仲間が来ていて、どんな活動をしていたのかは分からないが、とにかく足しげく参加していたようだった。
ある日、母親と話していた際、不意に聞いたことがとても強く心に突き刺さった。
「あなたのことを小さいときから『ちゃんと育ててあげなさい!』『愛情が足りない!』とたくさん言われ続けた。少年院から出るときも、精神科病院に医療保護入院で入っていたときも、私が何とかしないとあかんって思っていた」
「お金も時間も体もかけて、この子のために何とか私がやらないとあかん!って思いつつも、私の人生はどこにいったのか、私は奴隷じゃないねん、っていう気持ちを持っていた。いっそのこと、死んでくれたらいいのにと思うくらい、恨んでいた」
「だけど、実の子を殺したいと思っている、殺したいくらい恨んでいる自分を、母親として許せなかった。ずっと自分を責め続けていた」
薬物依存症者を家族に持つグループに出会って初めてそのことを話したところ、そこに参加していたみんなが自分たちも一緒だよって笑って受け入れてくれたという。
母親は、家族では母親や私の親という役割があるけれど、その前にまず一人の人間だ。きっと母親は、同じような境遇にいる仲間たちの中でそんな自分自身を受け入れてもらえた、一人の人間としての感情を尊重してもらえる体験をした。だからこそ、刑務所から仮釈放で出るために身元引受人になってほしいという私の思いに対して、「なれない」という自分の気持ちを正直に伝えてくれた。
依存症者の私に同じ問題を持つ仲間が必要なように、母親にとっても自分と同じような悲しみや苦しみを知っている仲間の存在が必要だったのだ。
きっと私たち親子に限らず、いろんな場所で暮らしている家族の方々や友人、支援に携わる人たちにも、役割のあるなしにかかわらず、自分が自分でいられる場所や人間関係は本当に大切だし、助けになる。支えになるし、大切なつながりになっている。改めてそう感じている。