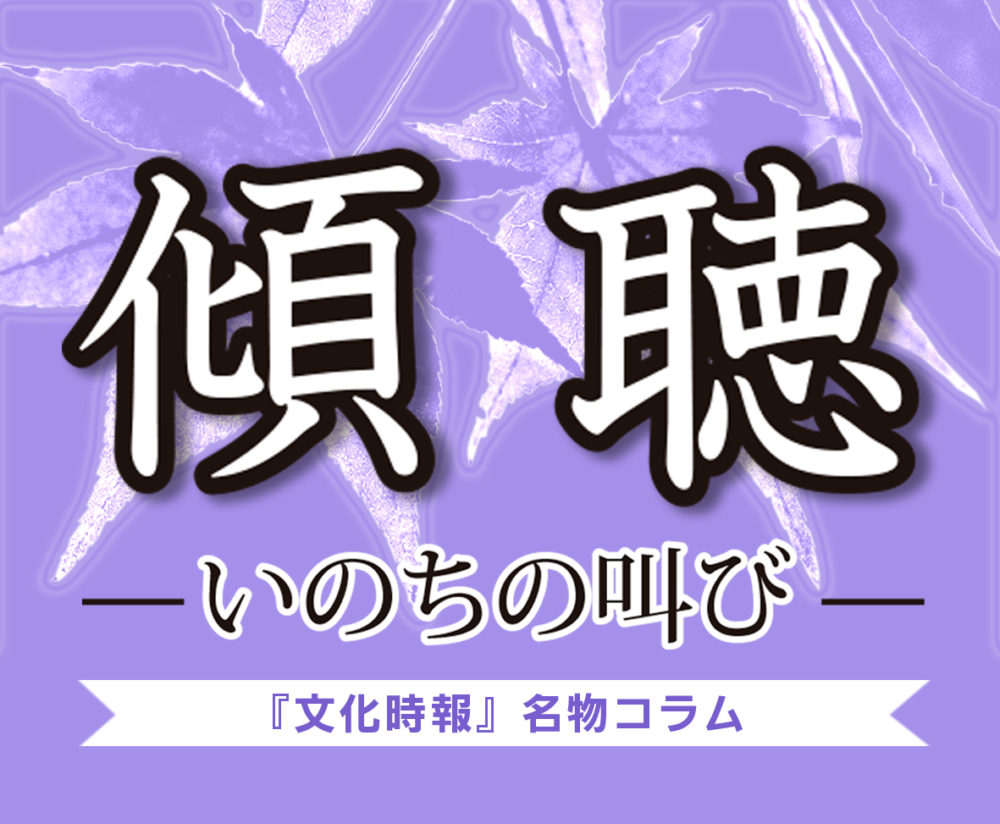読む
「文化時報」コラム
〈47〉楽しくて、切ない
2023年10月15日 | 2024年8月5日更新
※文化時報2023年7月28日号の掲載記事です。
夏といえば、七夕、お盆、夏祭り。そしてやっぱり、花火大会。
ここ数年は、諸般の事情で中止になっていた花火大会ですが、今年は各地で復活、開催されるようです。私の地元でも、4年ぶりの開催が決定しました。
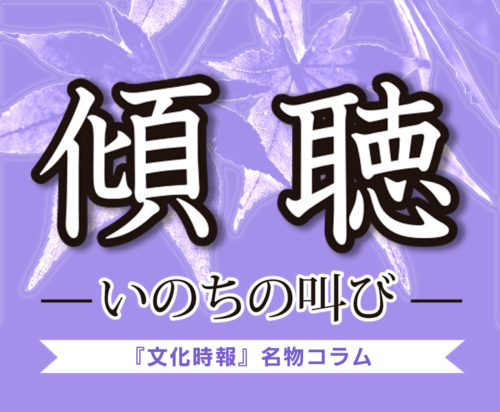
私の地元には大きな川がありまして、花火はその中州で打ち上げられます。花火大会の当日は、まだ明るいうちから、浴衣姿交じりの老若男女が河原の土手を埋め尽くします。駅から川まで行く道々には、さまざまな屋台がずらりと軒を並べて、いつもは着物を売っている呉服屋さんまでもが、店先でたこ焼きを売っていたりします。
見物客はあっちの屋台、こっちの屋台にひっかかってはついつい買い込んでしまい、両手いっぱいにおいしいものを抱えて河原に向かうのです。
人々のざわめき。川面を渡る風。夕焼けに染まる空。宵の明星。
ようやく空が暗くなった頃、「ど~ん」と打ち上がる1発目の花火に、ぬるくなったビール片手に「た~まや~」なんて叫んだりして…。毎年繰り返すこの瞬間が、どうしてこうも待ち遠しくて、楽しくて、そしてちょっぴり切ないのでしょうか。
思い起こせば、最初は彼と2人で見ました。そのうち、1人、2人と家族が増えました。そのあと、彼が逝って1人減って。そうこうするうち、息子がお嫁さんを連れてきて、また1人増えて。そして、いよいよ今年は、小さき人が初めての花火大会参加です。
時が流れ、人が移ろい、それでも変わらず夜空を染める夏の花火。
この瞬間がこんなにも楽しくて切ないのは、こうやって一緒に過ごせることのありがたさを、夜空に咲く花火のはかなさに重ねて見てしまっているせいかもしれません。
だからでしょうか、河原からの帰り道、何度も何度も約束しないではいられないのです。
「きっと、きっと、また来年も、一緒に見ようね」