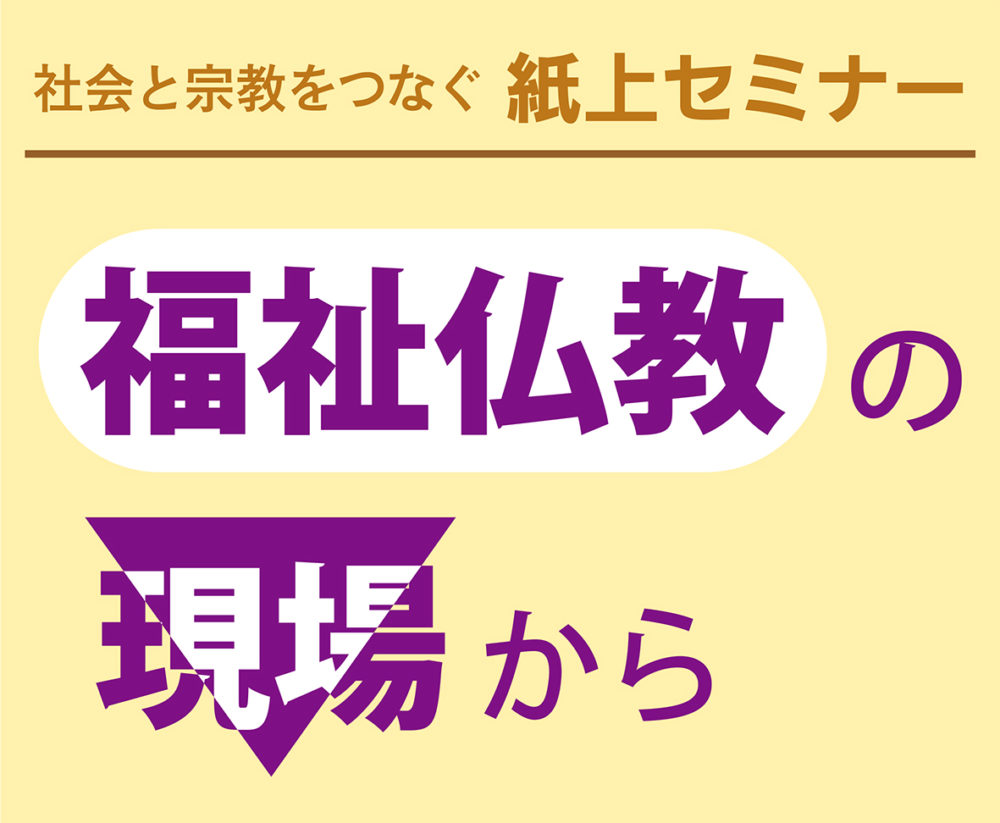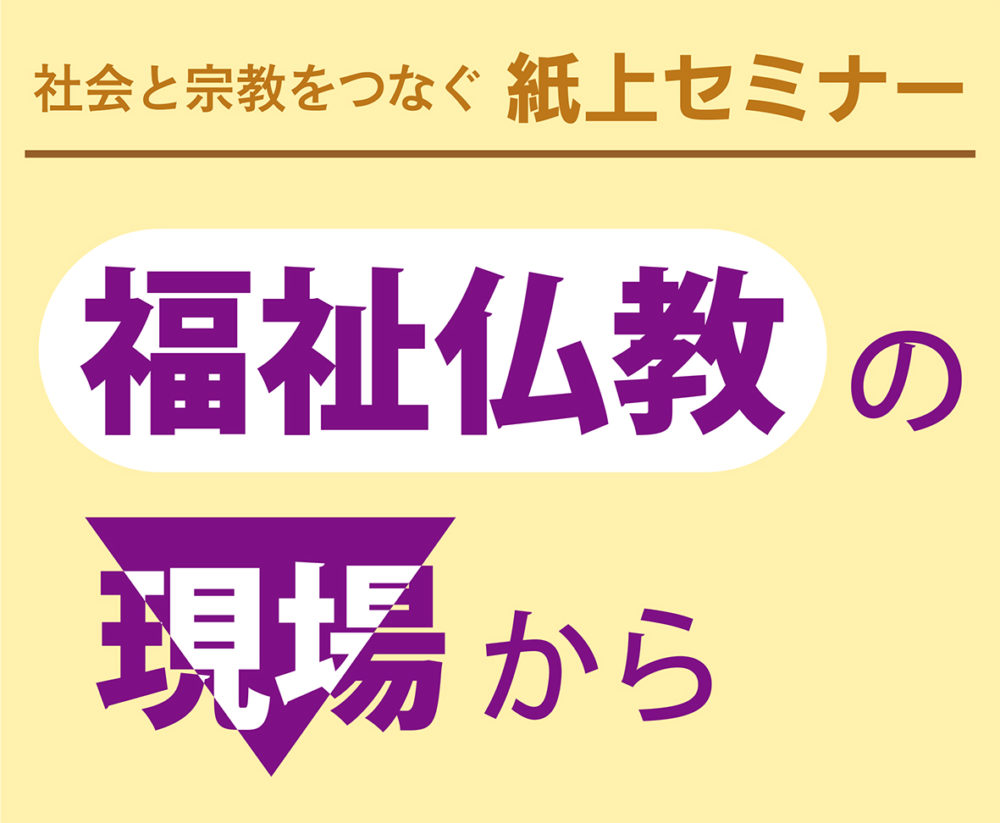読む
「文化時報」コラム
〈69〉一体感と排他
2024年3月16日 | 2024年10月2日更新
※文化時報2023年11月21日号の掲載記事です。
プロ野球阪神タイガースが59年ぶりの関西対決を制し38年ぶりの日本一を達成した。筆者が生まれたのは1965(昭和40)年。前年に阪神対南海の日本シリーズがあり、この年から読売巨人軍の9連覇が成された。筆者がプロ野球に関心をもった頃は巨人軍が日本一になるのが当たり前の時代であった。
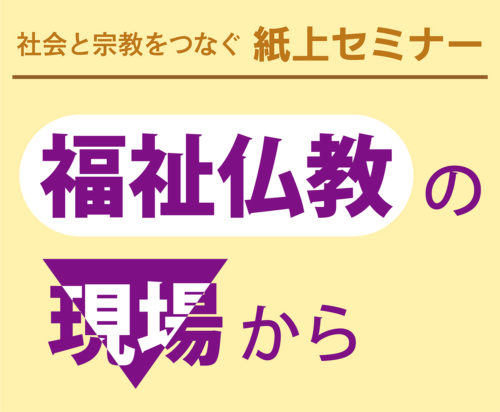
20歳になった85年に「阪神優勝」という生まれて初めての経験をし、阪神は球団史上初の日本一になった。日本一となった日の夜、筆者は大阪・道頓堀にいた。橋の上から次々に道頓堀川へ飛び込む人たちを目の前で見ていた。
先日、面白い記事を見つけた。オリックス・バファローズのファンは見ず知らずの者同士のハイタッチを一瞬ためらうが、阪神ファンはためらわない。見知らぬ者同士でも喜び合うというのである。真偽のほどは分からない。ただ、ありそうな話だとは思った。
阪神ファンは、年齢も性別も国籍も宗教も職業も全て超越して優勝を喜び合える気がする。それは悔しい思いを共有してきたからこそ生まれる一体感ではないかと感じる。「六甲おろし」を歌えばみんなお友達という熱い空気がたしかにある。
しかし、一体感は「排他」を生む。今年の甲子園は、夏の高校野球で慶應義塾高校が107年ぶりの優勝に沸いた。その慶應を応援する人たちが集まってきて、決勝戦はテレビでみていても異様さを感じるくらいの声援があった。彼ら彼女らに一体感を与えるのは「若き血」という応援歌であったろう。
そして、先日の日本シリーズ。甲子園での試合は、レフトスタンドの一部を除いて球場全体が阪神ファンで埋まっていた。ホームゲームといえばそれまでだが、なんとなく「これでいいのだろうか?」とは思った。
大阪は浄土系の寺院が数多くある。六文字名号は「六甲おろし」や「若き血」ではない。「例外なく救われる」からありがたい。
第7戦で敗れたオリックスの選手たちは、京セラドーム大阪のレフトスタンド、すなわち阪神側に向かって整列一礼した。とても大事なメッセージだと思った。