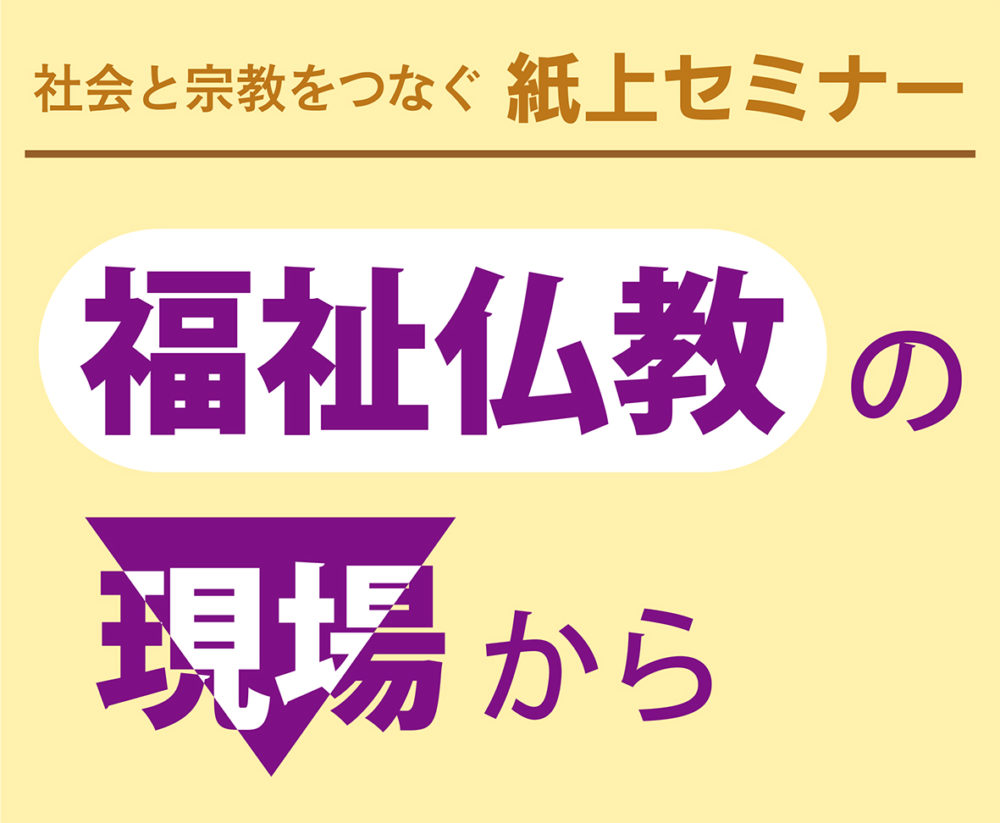インタビュー
橋渡しインタビュー
レンズ越しに見る光と影…映像作家・宍戸大裕さん
2025年6月21日 | 2025年7月15日更新
映像作家の宍戸大裕さん(42)=東京都小金井市=はドキュメンタリー映画を中心に制作している。2月8日に公開された映画『杳(はる)かなる』では、筋萎縮性側索硬化症(ALS)=用語解説=などの難病患者を撮影し、日々の暮らしや心の葛藤を描いた。この作品では、宍戸さん自身が一瞬登場する場面があり、患者たちと向き合う様子が映っている。なぜ、宍戸さんは難病患者や障害者の生活を深掘りし、作品に残そうとしているのか。
「実は今、クマのドキュメンタリーを撮っています」。宍戸さんはそう語り始めた。聞けば、5年ほど前から岩手県盛岡市でクマと人間の共存をテーマにしたドキュメンタリーを撮影しているという。
自身の屋号を「くまのあくび舎」と名付け、「クマがあくびをして生きられるような社会をつくりたい」という思いを込めている。

2008(平成20)年から映像制作を始め、『高尾山 二十四年目の記憶』を学生時代に制作。13年には『犬と猫と人間と2 動物たちの大震災』が劇場公開された。
16年には『風は生きよという』で重度障害のある女性にスポットを当てた。18年には知的障害のある青年を映したドキュメンタリー映画『道草』を制作した。
自分の思いを伝えるために、最も適しているのが映画だと考えている。環境問題や障害といった硬派で根深い問題に焦点を当て続ける。現在は映画制作のため、東京都と岩手県の2拠点生活を送っている。
サラリーマンでなくても生きる道を探して
宍戸さんは1982(昭和57)年生まれ。宮城県で育ち、子どものころは内気で集団行動が苦手だった。自然や動物を愛しており、少年時代は獣医か政治家になって動物を守りたいと、熱い志を持っていた。
早稲田大学教育学部国語国文学科に進学。他の学生たちとの付き合いが希薄で、相変わらず1人で過ごす時間が多かった。留年し、気付けば6年生になっていた。
就職先を探したものの、面接で素直な気持ちを話すと相手にされず落とされてしまう。だが、内定をもらうために自分の考えをねじ曲げるのも違う。苦痛な日々だった。
悶々(もんもん)としていた2007(平成19)年、参議院選挙に出馬した在日2世の金政玉(キム・ジョンオク)氏と知人の紹介で出会い、選挙運動を手伝ったことが転機となった。
障害者の権利擁護のために出馬した金氏の周りには、たくさんの障害者が集まり、「自分の生活をなんとかしたい」と意気込んで応援していた。そうした様子を見て、宍戸さんは彼らと関わりを持つようになった。

「当時、僕は将来を不安に感じていましたが、障害があって企業に勤めていなくても、彼らは力強く生きていました。その姿を見て、一緒に過ごしてみたいと思ったんです」
障害があっても自分を貫く姿を目の当たりにしたことで、宍戸さんの気持ちは次第に前向きになっていく。「ここなら自分らしくいられる」と、心が落ち着いた。
その後はアルバイトをしながら、ドキュメンタリーを制作。友人から聞いた高尾山のトンネル開発計画で自然破壊に危機感を覚え、工事に反対する人々の姿を映像に収めた。その頃は特に映画好きというわけではなかったが、多くの人に伝えるには映像が最適ではないかと考えた。
共存できる世界を探して
人工呼吸器を使って暮らしていた海老原宏美さんとの出会いも大きかった。安楽死への反対や命の尊厳を強く訴えようとしていた海老原さんから、「私たち呼吸器ユーザーの日常を撮ってほしい」と依頼された。
重度障害者に対する社会のまなざしに、宍戸さんはとても敏感だ。社会から否定され続けてきた学生時代の感覚が、根底にある。「自分の存在をないものにされる恐怖。これは、人ごとではないです」
これまでに出会ってきた障害のある一人一人は宍戸さんにとって恩人であり、孤独だった自分を救ってくれた大切な存在だ。人も動物も互いがどうしたら共存できるのか。自分たちの居場所を守るためにも、かき消されそうな声を拾い集めて、粘り強くカメラを回し続けている。

『杳かなる』を上映し、たくさんの人から反響があった。「心が洗われた」「介護者の姿も素晴らしい」などと、さまざまな思いを聞けたことに、宍戸さんは安堵(あんど)した。
単に介護の大変さや病状の重さなどを映すのではなく、出演者の人柄や希望を見せようとしていた。「それぞれに感じてもらうことがあってよかった」と笑みを見せた。
出演者たちとは、今も変わらず気軽にお茶をするような関係性を築いている。何げない会話やふとした疑問から、次の制作につなげていくのだろう。
【用語解説】筋萎縮性側索硬化症(ALS)
全身の筋肉が衰える病気。神経だけが障害を受け、体が徐々に動かなくなる一方、感覚や視力・聴力などは保たれる。公益財団法人難病医学研究財団が運営する難病情報センターによると、年間の新規患者数は人口10万人当たり約1~2.5人。進行を遅らせる薬はあるが、治療法は見つかっていない。