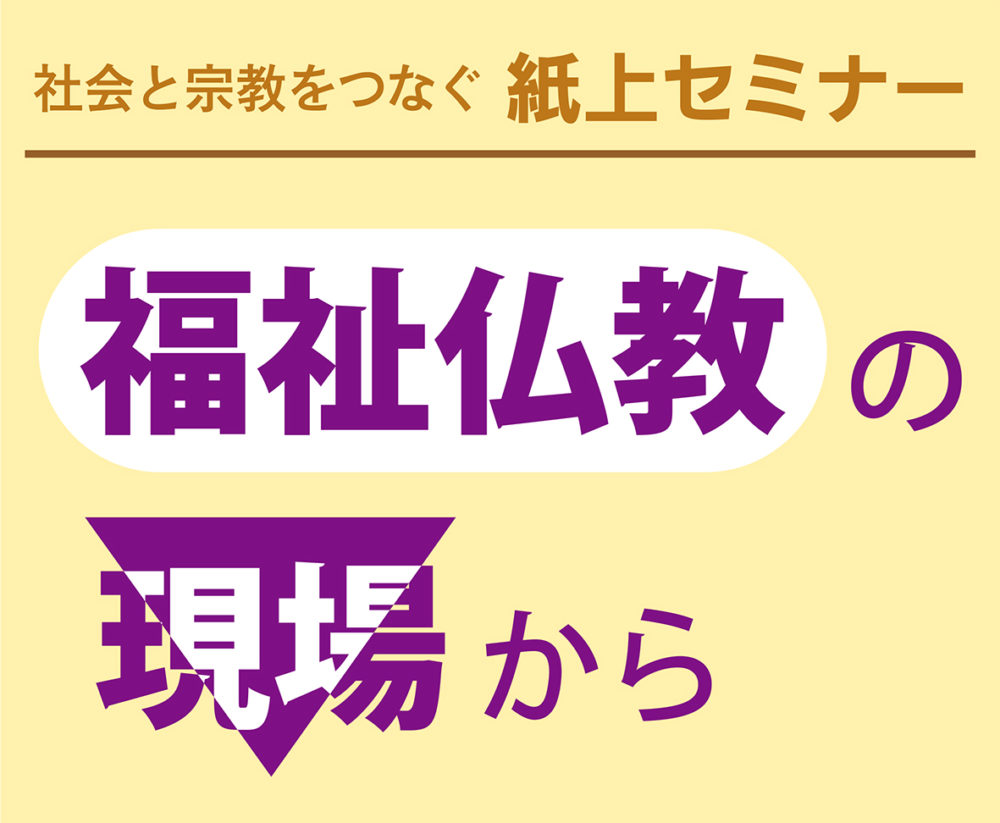知る
お寺と福祉の情報局
ダウン症の娘、苦しんだのは母だった
2022年9月1日
ダウン症のある金澤翔子さん(37)は、天才書家として知られる。母の泰子さんが「今は幸せ」と話すのは、翔子さんが書家として成功したからではない。

「こういう子が生きていてはいけないのだと思い、死ぬことばかり考えていた」
泰子さんは、42歳で翔子さんを授かり、ダウン症があることを医師に告げられた時のことを、そう振り返る。
地元小学校の普通学級に通い、担任の先生から「翔子ちゃんがいると、皆が優しくなる」と言われ、「翔子はいてもよいのだ」と感じた。
ただ、学年が進むと、普通学級に通うことが難しくなった。特別支援学級を設ける遠くの小学校に通う必要がある。納得できず、一時は自宅にひきこもった。
結局は転校せざるを得なかったのだが、予想に反して翔子さんが喜んで通学した姿を見た時、泰子さんは心が楽になったという。
「苦しいのは親の私だった。翔子は、ダウン症を苦しんでいなかった」
親なきあとを超えて
障害のある子を持つ親は、障害の大小にかかわらず、自分が世を去った後のわが子の生活を不安に思う。「親なきあと」の問題だ。

泰子さんは「もう終活をしなければならない年齢」と語りながらも、不安を顔に出さない。なぜなら、翔子さん自身が、親なきあとも生活できる環境を、自らつくり上げたからだ。
翔子さんは、30歳から一人暮らしを始めた。ある講演会で、突然「やる」と宣言したため、泰子さんは、いやが応にも準備を進めざるを得なくなった。
ダウン症のある子を受け入れる物件は少なかったが、自宅から徒歩7分の距離に住まいを見つけた。 それから7年。翔子さんは、一度も実家に帰っていない。自分で買い物に行き、料理もする。町の人たちは、家族のように接してくれる。「翔子は、自ら共同社会をつくった。これが一番の功績」と、泰子さんは話す。
そして「子どもは障害があっても、大きな力を持っている。社会に合わないからと諦めないで、その子を尊重してほしい」と語る。