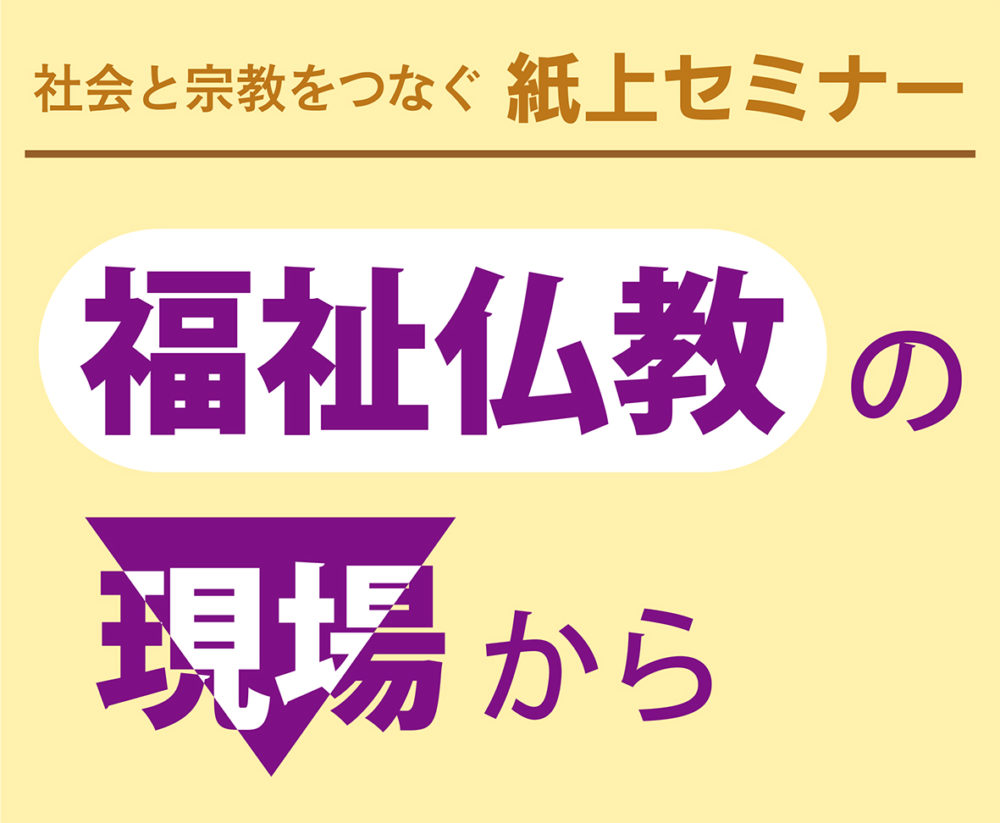つながる
福祉仏教ピックアップ
お寺で激走ミニ四駆 子どもの休日を応援
2025年1月2日 | 2025年1月3日更新
※文化時報2024年10月29日号の掲載記事です。
1980年代に一世を風靡(ふうび)しリバイバルブームを繰り返す自動車模型「ミニ四駆」のサーキットを常設したお寺が、青森・下北半島にある。曹洞宗長福寺(吉田眞一住職、青森県佐井村)。模型メーカーのタミヤ(静岡市駿河区)が注目して「寺四駆」と名付け、全国のファンに知られるようになった〝聖地〟だ。将来世代が仏教に親しめるようにと、吉田眞永副住職(32)が手掛ける先進的な取り組みが、人口1600人余りの村で花を咲かせつつある。(主筆 小野木康雄)

佐井村は本州最北端の大間町の南隣に位置する。青森市から車で約3時間半、最寄り駅からでも約1時間半かかり、冬場は路面が凍結するため往来もままならない。
そうした厳しい条件にありながら、長福寺には村の内外から多くの人が訪れる。お目当ての一つが、大広間に設けられたミニ四駆のサーキット。全長100メートル超のコースを、マシンがうなりを上げながら疾走する。

2018(平成30)年の成道会=用語解説=に合わせたイベントで、坐禅や写経などと共に「懐かしのおもちゃ体験」として行ったのがきっかけだった。吉田副住職が会員制交流サイト(SNS)にその様子を投稿したところ、タミヤの公式アカウントが「これは新しい!『寺四駆』」と反応した。
これを受けて吉田副住職はサーキットを常設。マシンのレンタルや工作体験ができるよう大広間を整え、小さい子ども向けのおもちゃや親子で楽しめるボードゲームなどもそろえた。遊び場として土・日曜と祝日の午後に開放し、お盆やお彼岸のお参り、法事などでも子どもの休憩場所として使ってもらっている。

初めて訪れた子には、全ての漢字にルビを振ったお寺のパンフレットを手に、「お寺探検」として本堂を案内。本尊の釈迦如来や円空=用語解説=が彫った十一面観音立像(青森県重要文化財)に手を合わせてから、大広間に通す。あくまで仏教やお寺に関心を持ってもらうことが第一だ。
若い世代とのご縁づくり
吉田副住職は長福寺で生まれ育ち、大本山永平寺(福井県永平寺町)で修行。師匠の方針でお布施を頂く以外の仕事を経験するため、仙台市内のイベント会社で4年間働きながら自坊の法務を手伝った。

「若い世代とのご縁が少ない。このままだと私の代で大変なことになってしまう」。お寺でもイベントを矢継ぎ早に打ち出して人を呼び込もうとするのは、そうした強い危機感があるからだ。
寺四駆の取り組みは「テラヨンカーズ」という吉田副住職が会長を務める任意団体が主催しており、長福寺から大広間を有償で借りる形をとっている。お寺を私物化していると見られないための配慮だ。

テラヨンカーズは「子どもの休日応援団体」と銘打っている。手伝ってくれる人も徐々に現れはじめた。9月28日には一日修行体験会を開き、子どもたちが坐禅や精進カレーの昼食、作務をした後、思う存分ミニ四駆で遊んだ。
「子どもたちにはここでの体験を基に、菩提寺に行ったりお寺巡りをしたりしてほしい。昨今はお寺離れが叫ばれるが、こういう地道な取り組みが必要ではないか」。吉田副住職はそう語る。
整体で副業「普段から関係築く」
吉田副住職のもう一つの顔が、整体師。かつて患者として通っていた仙台市内の整体院に教えを請い、昨年5月に「すこやか整体 そわか」を開業した。長福寺を間借りし、会員制交流サイト(SNS)や口コミで村外からもお客を増やしている。
整体は、お寺でできる副業として着目したが、坐禅の基本である調身(姿勢を調える)、調息(呼吸を調える)、調心(精神を調える)に通じている。効果を求めてやるのではなく、続けていると知らず知らずのうちに心が安らぐところも共通している。

仏教を大切にしつつ、寺四駆や整体などさまざまな取り組みをしていると、檀家から「子どもを安心して連れてこられる」「長福寺が菩提寺で良かった」などと喜ばれるという。
たまに、お寺は法事と葬式さえやっていればいいと考える人から「本当に苦しんでいる人はイベントに来るのか?」などと批判されることもある。吉田副住職は、きっぱりと言う。
「人はいつ苦しみに直面するか分からない。元気なうちにイベントで知り合ったお寺に、駆け込められればいい。僧侶は普段から相談される関係を築いておくことが大切だ」
これからも、イベントに力を入れていくつもりだ。

【用語解説】成道会(じょうどうえ=仏教全般)
釈尊が悟りを開いたこと(成道)を記念して12月8日に行う法会(ほうえ)。臘八会(ろうはちえ)ともいう。
【用語解説】円空(えんくう、1632〜95)
江戸前期の修験僧。美濃国(現・岐阜県)生まれ。全国を旅しながら神仏を彫り続け、「円空仏」と呼ばれる独特な作風の仏像を各地に残した。一説には、彫った仏像は生涯で約12万体に上るとされる。