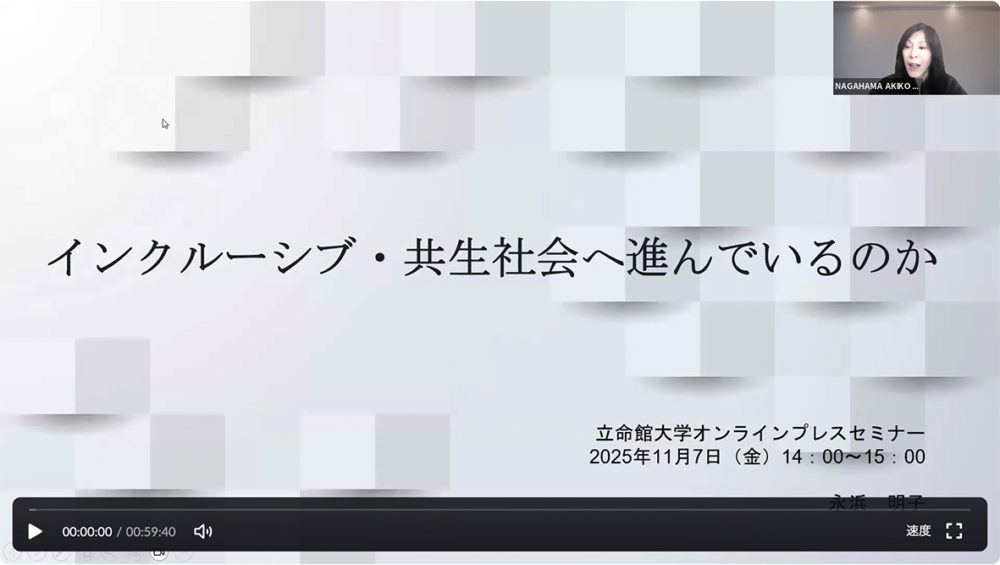つながる
福祉仏教ピックアップ
人に頼ってお寺を開く 4月6日「まぜこぜ大阪」
2025年3月24日
※文化時報2025年3月14日号の掲載記事です。
誰もが当たり前に生きられる社会を体験する地域イベント「まぜこぜ大阪」が4月6日、大阪市生野区の真宗大谷派定願寺で開かれる。在阪テレビ局も会場になったことのある有名な催しで、寺院での開催は初めて。「誰も排除することなく、お寺を開きたい」。そうした願いを持つ楠正知住職(47)は、自然体で楽しいお寺づくりを心掛けている。(主筆 小野木康雄)
境内改修し準備
まぜこぜ大阪は、世界自閉症啓発デー(4月2日)に合わせて2016(平成28)年から開催。通り一遍の福祉イベントではなく、音楽ライブやマルシェと啓発活動を合わせて行うことで、障害のある人や生きづらさを感じる人たちと共に楽しめる仕掛けになっている。23年には毎日放送1階の「ちゃやまちプラザ」(大阪市北区)などで行われた。
定願寺が今年の会場に選ばれたきっかけは昨年9月、大阪・関西万博を生野区から盛り上げる区役所主導の「EXPOいくのヒートアッププロジェクト」に参加したこと。会合で「お寺を開きたい」と思いを伝えたところ、出席していたまぜこぜ大阪実行委員の藤田秋香(あきか)さん(62)から「ぜひ会場に」と依頼された。

場所を貸すだけと思って気軽に引き受けたが、調べてみると「想像をはるかに超えるすごいイベントだった」。可能な限りハード面で協力しようと、門徒総代に相談し、多目的トイレの整備や車いす対応のための改修工事を行ったという。
楠木正成の末裔
定願寺は、楠正成(楠木正成)の孫で浄土真宗に帰依した正長が、室町時代の1412(応永19)年に開基した。
楠住職は正成の末裔(まつえい)に当たり、2019(平成31)年2月、急死した前住職の正継師の跡を継いで第21代住職に就任。600年以上続く名刹(めいさつ)を急遽(きゅうきょ)任される立場になり、お寺とはどのような場所で何ができるのか、自問自答を繰り返した。

そんなとき、法事の機会を捉えて門徒の子どもに何げなく「お寺ってどんなところ?」と尋ねたところ、「お葬式をするところ」と言われてショックを受けたという。
「人は人生の大半を楽しく愉快に過ごしているはずなのに、お寺は『亡くなった人とその家族』としてしか見ていないことに気付いた。お葬式だけのお寺と思われたままでいいのか」。お寺を開くことで「楽しい場所にしたい」と切望した瞬間だった。
とはいえ、開く方法が分からなかった。「自分一人では、何もできない」。幼少のころから祖父や父を手伝い、法務一筋で歩んできた人生。社会人経験がなく、人脈も乏しかった。
お地蔵様を安置
会員制交流サイト(SNS)を活用し始めたものの、コロナ禍になって動くに動けず、時が流れた。
昨年3月、地域住民のよりどころだった街角のお地蔵様が立ち退きで行き場を失っていたところを、頼まれて境内に安置した。これを境に、お寺を支えてくれる人や助けてくれる人が相次いで現れたという。「自分ができないことは、できる人に頼る。『分からないから助けて』と発信し続ければ、必ず誰かが助けてくれる」と、楠住職は語る。

現在ではお寺主催の落語会や演奏会、場所を貸しての子ども食堂など、月1回は法要以外の行事が催されるようになった。これからもお寺を開放し、さまざまな人に活用してもらいたいと考えている。
「点と点が線になり、いつの間にか輪になるようなつながりが、僕の知らないところでできれば、すてきやなと思う。それが、お寺の存在価値を高めることになるのでは」。誰かに頼りながら、頼られるお寺になることを目指していく。
大阪をブルーに染めよう
誰もが当たり前に生きられる社会を体験する地域イベント「まぜこぜ大阪」を主催するのは、福祉関係者やまちづくりに携わる有志でつくる実行委員会。実行委員の藤田秋香さんは「お寺は本来人が集まる場所。化学反応に期待している」と話す。
元々は大阪・梅田で開催していたが、長らく使用していた小学校跡の会館が取り壊されることになり、新たな会場を探していた。
藤田さんによると、今回初めて会場となる定願寺は「いいあんばいの広さ」。畳敷きの本堂でダンスを含めた本格的な音楽イベントができることを、楽しみにしている。

境内で行うマルシェには、ミシュランガイドに掲載された京都のフレンチレストラン「MOTOÏ」(モトイ)やクロワッサンで有名な大阪・北新地の「LE SUCRÉ︲COEUR」(ルシュクレクール)なども出店。障害のある人が店員を務めるという。
実行委は「大阪をブルーに染めよう!」として、自閉症啓発デーのシンボルカラーである青色の服やアクセサリーなどを身に着けて来場するよう呼び掛けている。藤田さんは「たった一日でもいい。誰も排除せず、お互いに歩み寄れる社会になれば」と話している。

4月6日午前11時~午後5時。物販は完売次第終了。問い合わせはメール(mazekozeosaka@gmail.com)で。