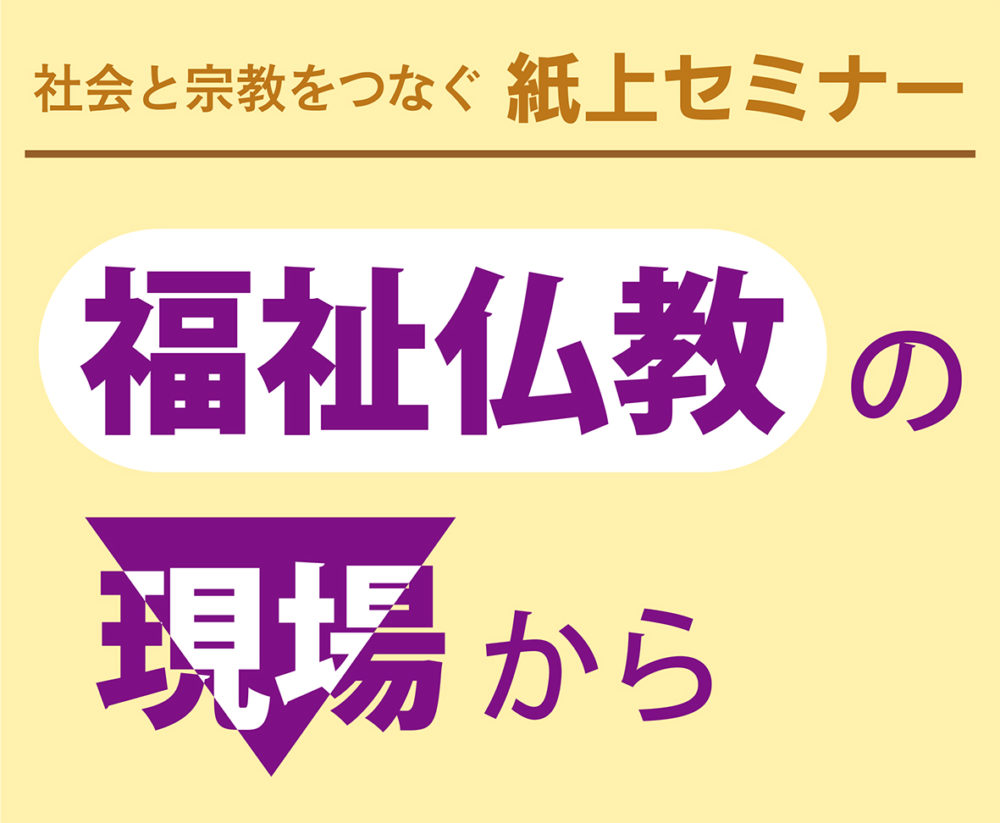つながる
福祉仏教ピックアップ
死を見つめて生きる 看護師兼僧侶・東承子さん
2024年12月13日 | 2025年1月29日更新
※文化時報2024年9月27日号の掲載記事です。
大阪府寝屋川市の小松病院の緩和ケア病棟で看護師として勤務する東承子(あずま・しょうこ)さん(54)は、スピリチュアルケア=用語解説=の重要性を訴える浄土真宗本願寺派の布教使だ。さまざまな診療科を経験して感じたのは、誕生する命もこれから死を迎える命も「美しい」ということだった。東さんは強調する。「自分の死を見つめることがなければ、本当の意味で生きることができない」(大橋学修)
東さんは小松病院の前に、「お坊さんのいる病院」として知られる独立型緩和ケア病棟「あそかビハーラ病院」(京都府城陽市)で働いた経験を持つ。両者の一番の違いは、ビハーラ僧=用語解説=の存在だという。
緩和ケア病棟では、患者が「もう死んでしまいたい」「死んだらどうなるのか」とこぼすことがある。多くの看護師はどのように応じればいいか困惑するが、東さんは「答えはいらない。むしろ、答えは求めていない」と説明する。
東さんは信仰を背景に、スピリチュアルな悩みに対する自分なりの答えを持っている。決して押し付けることはなく、「確信を得ているから、患者の言葉で心が揺るがない。だから、患者を『そのままでいい』と受け止められる」。ビハーラ僧も同じ立ち位置で患者に接していると考えている。
あそかビハーラ病院と異なり、小松病院にはビハーラ僧がいない。臨床心理士が週に数日通うが、思いを吐き出す場を提供できているわけではないという。「ビハーラ僧のような立ち位置の人が、病棟内をぶらぶらと歩いていてくれれば」と語る。
声なき患者の目線
東さんは佛教大学社会学部社会福祉学科を卒業後、一般企業に就職。1年ほどで退職して本願寺派の僧侶養成学校「中央仏教学院」に入学した。在家出身だが、信仰のあつい母の影響だったという。

25歳で結婚したが、子どもが1歳になる直前で離婚。生計を立てるために、看護師を目指した。子育てしながら勉強し、29歳で旧星ケ丘厚生年金病院(現・地域医療機能推進機構星ケ丘医療センター、大阪府枚方市)の付属保健看護専門学校を卒業。同病院で従事するようになった。
東さんが緩和ケア病棟で働くのを目指したのは、ある消化器外科の患者との出会いがきっかけだった。消化器外科では、手術で治療中の患者と治療が困難で死を待つばかりの人が混在して入院していた。
あるとき、ナースコールの呼び出しで向かった先は、ボタンを押すことさえ困難な患者の病室だった。力の限りを尽くして東さんを呼び出したものの、体がつらくて声も出せない。
そうした中、背後で別の病室からのナースコールが鳴る。患者は、細くやせた腕を伸ばし「行かないで」と目で訴えた。東さんは、受け止めた手を振りほどいて、別病室に行かざるを得なかった。
それ以来、患者の切ない目線が忘れられなくなり、死に直面した人にゆっくりと向き合う必要を感じた。「緩和ケアに行こう」。あそかビハーラ病院に掛け合って、転職した。37歳のときだった。
「承子、人間になりや」
東さんは、緩和ケアの世界に入ってから、「いかにも患者のためのように振る舞っている自分」の存在に気付くことになった。患者の前では、それが見透かされているようにも感じた。
「承子、人間になりや」。亡くなった祖母の言葉を思い出した。看護師として働くようになってから、仏壇の前で手を合わせることをしなくなっていたが、教えの中に答えを求めるようになった。
布教使の養成研修に通い、だんだんと学んだ教えがふに落ちるようになった。「人に見せたくないずるい自分自身を見つめ続けることが、人として生きることなのだ」と確信した。
最近は、患者の言葉から教えを見いだすようにもなった。ある患者は「命に限りがあるから、一生懸命に生きるんやな」と言い、別の患者は「人生思うようにならないからこそ、喜びがある」とつぶやいた。釈尊が説いた諸行無常が思い浮かんだ。
患者の死が、自分自身の死を考える機会となり、「私はこれでいいのか。今のままでいいのか」と自問自答するようにもなった。そして、こう考えるようになった。
「患者を鏡として、偽ることなく自分自身を見つめる。どうしようもない自分であっても阿弥陀如来が必ず浄土に生まれるように抱き取ってくれるから救われる」
看護師と患者という立場の違いはあっても、同じ人間同士。同じ方向を向いていたい、と思っている。
【用語解説】スピリチュアルケア
人生の不条理や死への恐怖など、命にまつわる根源的な苦痛(スピリチュアルペイン)を和らげるケア。傾聴を基本に行う。緩和ケアなどで重視されている。
【用語解説】ビハーラ僧(浄土真宗本願寺派など)
がん患者らの悲嘆を和らげる僧侶の専門職。布教や勧誘を行わず、傾聴を通じて相手の気持ちに寄り添う。チャプレンや臨床宗教師などと役割は同じ。浄土真宗本願寺派は、1987(昭和62)年に医療・福祉と協働して生老病死の苦しみや悲しみに向き合う仏教徒の活動「ビハーラ活動」を展開しており、2017年度と19年度には「ビハーラ僧養成研修会(仮称)」を試行。計10人が修了した。