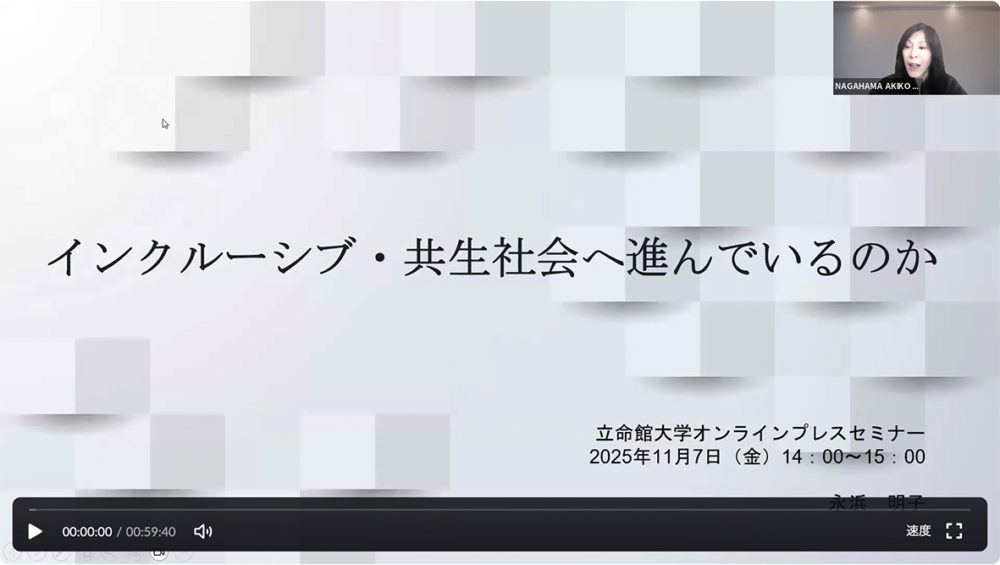つながる
福祉仏教ピックアップ
アートで共生考える 願生寺「ごちゃまぜフェス」
2024年12月15日
※文化時報2024年10月4日号の掲載記事です。
浄土宗願生寺(大河内大博住職、大阪市住吉区)などは9月22日、大阪市長居障がい者スポーツセンター(同市東住吉区)体育室で、アートやファッションに特化した「ごちゃまぜフェス」を開催した。障害のあるなしにかかわらず運営者や参加者になれるイベントで、災害時に必要とされる住民同士の支え合いや共生社会などについて必要性を感じてもらった。(大橋学修)
「みんなの楽しみと心配事を一緒に体感」をテーマに、NPO法人VAROR(バロール、兵庫県三田市)の辻和王(かずたか)代表理事が監修した。

アート作品や洋服を扱う就労継続支援B型事業所=用語解説=などがブースを設置。飲み込む力の弱い障害のある人でも食べられる防災食や、肢体不自由の人を運ぶ担架などを紹介するコーナーも設けた。
ステージでは、重度脳性まひの長男と一般社団法人HI FIVE(ハイファイブ、大阪市西淀川区)を立ち上げた畠山織恵さんが講演。一般社団法人学生ダンサー協会(同市東住吉区)がダンス体験などを行った。
ファッションショーには、身体障害や発達障害のある人、支援者らがモデルとして登場。NPO法人さをりひろば(同市都島区)などが提供した「さをり織り」の衣装を身に着けてランウェイを行き来した。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)=用語解説=患者の米田晴美さんも参加。夫の裕治さんは「妻は、いつも以上のメークで喜んだ。販売ブースでは、たくさんの商品を買わされてしまった」と笑顔を見せ、米田さんを支えるライフサポートリアン(兵庫県芦屋市)の大城盛子(あつこ)さんは「いろいろと趣向を凝らし、いい意味で障害のある人が注目されたイベントだった」と語った。
防災プロジェクトが進化
願生寺は2021年9月に「防災プロジェクト」を立ち上げて以降、医療的ケア児=用語解説=などの要配慮者と地域住民が助け合う枠組みづくりを進めている。今年4月には今回と同様の趣旨で「ごちゃまぜゆるスポーツ大会」を開き、共生社会の構築に向けて一歩を踏み出した。
発達障害のある人が美容業界で活躍できるよう支援する合同会社カラーズ(大阪市東成区)の講師で、発達障害のある石井桃子さんは、普段の活動では社会の人々と交流する機会が少ないと指摘し、今回のイベントについて「運営に携わった生徒たちの成長を感じる」と語った。

看護師の森川泰子さんは「スタッフの配置や準備を通じて、災害時での介助を考える機会にもなった」と振り返り、別の支援者は「いつもとは違う障害のある人や支援者と交流でき、認識が広がった」と話した。
お寺を拠点とした共生社会の構築に詳しい小西かおる大阪大学大学院教授(保健学)は「講演などでいろいろなエピソードが紹介され、理解を深め合う機会になった」。大河内住職は「協力してくださった支援団体が交流し、防災に関して発見し合える場になった」と手応えを感じていた。
【用語解説】就労継続支援B型事業所
一般企業で働くことが難しい障害者が、軽作業などを通じた就労の機会や訓練を受けられる福祉事業所。障害者総合支援法に基づいている。工賃が支払われるが、雇用契約を結ばないため、最低賃金は適用されない。
【用語解説】筋萎縮性側索硬化症(ALS)
全身の筋肉が衰える病気。神経だけが障害を受け、体が徐々に動かなくなる一方、感覚や視力・聴力などは保たれる。公益財団法人難病医学研究財団が運営する難病情報センターによると、年間の新規患者数は人口10万人当たり約1~2.5人。進行を遅らせる薬はあるが、治療法は見つかっていない。
【用語解説】医療的ケア児
人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、痰(たん)の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童。厚生労働省によると、2021年度時点で全国に約2万180人いると推計されている。社会全体で生活を支えることを目的に、国や自治体に支援の責務があると明記した医療的ケア児支援法が21年6月に成立、9月に施行された。