





読む
「文化時報」コラム
〈74〉受けたもう
2025年2月6日 | 2025年2月12日更新
※文化時報2024年11月8日号の掲載記事です。
山伏の修行を体験してきました。星野文紘先達のもと、総勢二十数名の出羽三山鳳来講です。昔から修験の場である鳳来寺山は、深く、静かで、凜(りん)としていました。
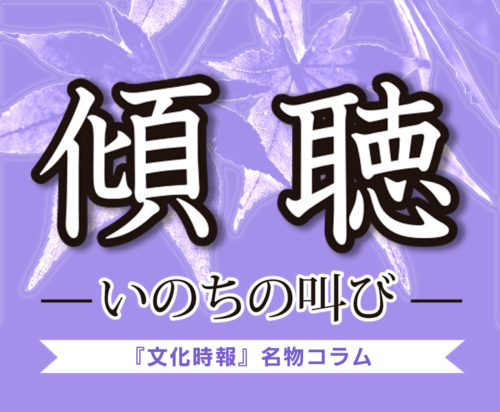
先達の吹くほら貝で、まずは山の神々に入山のご挨拶。ほら貝の響きが、幾重にもこだましながら天高く染み込んでいくのが見えます。
以降、修験者に許されるのは「受けたもう」の言葉だけです。源頼朝が寄進したという1425段の石段に息が切れても「受けたもう」。苔生(こけむ)した岩肌に滑ってしたたかに尾てい骨を打っても「受けたもう」。なんとかたどり着いた山頂から見させていただいた九重に広がる薄墨色の山々の姿に歓声を上げそうになっても「受けたもう」です。
この「受けたもう」。何度も何度も口にしているうちに、己の度量がじわじわと広がっていくのを感じました。足指にまめができて、痛みはじめます。「どうしよう。まめができちゃった。まだまだ歩かなきゃいけないのに。こりゃ、困った。大丈夫かな。どうしたらいい?」。歓迎できない事態に身も心もささくれ立ち、私はこの「まめができてしまった」という出来事に支配されます。
ところが、「受けたもう」と言ったとたんに、事態は一変。「まめができた」という事態は、私の支配下に入ります。「なに、まめができた? 受けたもう」。あとは、そのまめのできた足で、いかに歩き続けるかを考えればよいだけです。
受けたくないと頭を抱えて逃げ回るから、余計苦しい。とにかくいったん懐に入れてしまえば、あとは自分で、それをどう料理するかじっくり考えられるというわけです。
これは、どんな状況においても当てはまることかもしれません。そういえば、命の終わりの場面でも、全てを医者任せにしてしまわず、最後まで自分で考え選んでいた方のほうが、穏やかでいらっしゃったように感じます。
「受けたもう」。己の度量を広げる魔法の言葉。なにかにつけ唱えていこうと思います。え? 原稿の締め切り? 受けたもう!!


