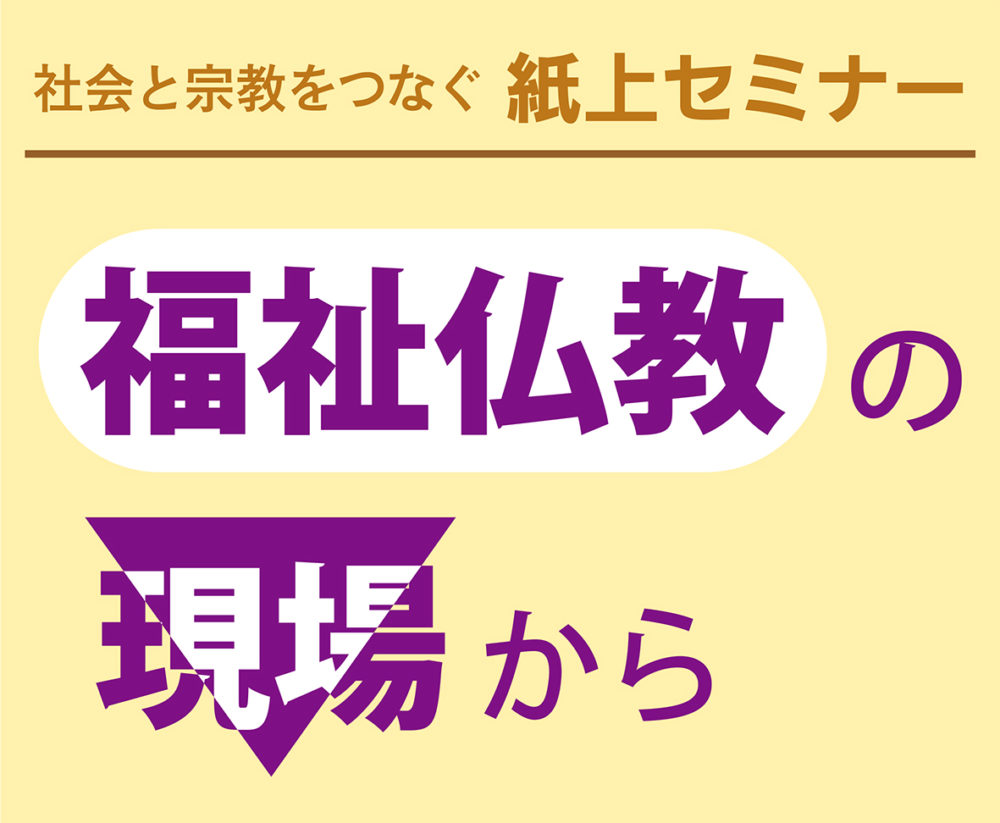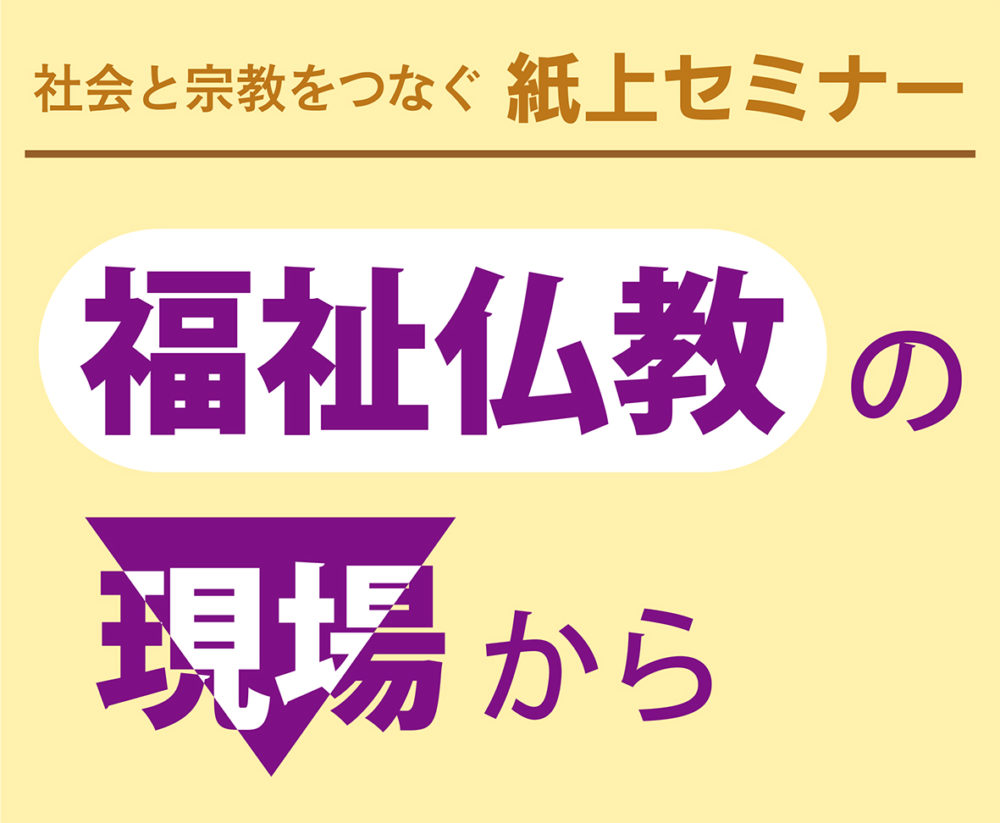読む
「文化時報」コラム
〈92〉医療者向けの法話
2025年3月3日
※文化時報2024年11月12日号の掲載記事です。
衆議院選挙も終わり「このままではいけない」と思う国民の声が少しは反映されたのではないかと思う。大阪は19の選挙区全てで日本維新の会の候補者が当選するという結果になった。他の都道府県から見れば「大阪だけ異質」と映っているのかもしれない。
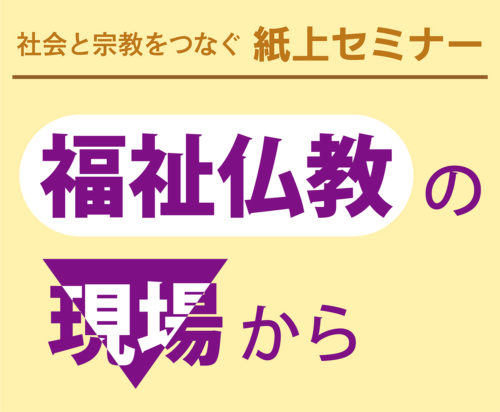
11月3~4日に福岡で開催された「地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク」の全国大会で講演してきた。医療者が中心の集いに、僧衣で登壇する僧侶が増えてきた。筆者もその1人である。
医療者から「地域共生を支える輪の中に僧侶も入ってほしい」という声が年々強くなっている。それは全国各地で個々の宗教者が地道な活動を続けてきたことが、少しずつ実を結んできたのだと思う。
近親者が亡くなった方にとっては、葬儀のほんの数日前まで医療者に頼っていた部分が大きいだろう。その割には、終末期といわれる時期に、命を終えていく人や家族がどんな思いで過ごしているかに関心を寄せる宗教者が少ないように思う。「葬儀からが出番だ」と宗教者側で勝手に思い込んではいないだろうか?
筆者は「終末期から葬儀・納骨までトータルに寄り添う僧侶」と自負している。何十例もある中から発表してもいい事例を選び、講演で話す。年々事例が増えてくるのでネタに困ることはない。
終末期における患者・家族の気持ちの変化を伝えると大きくうなずく人がたくさんいる。現場のリアルを医療者と共有できていると実感する。
その上で和讃(わさん)などを引用して僧侶からの視点を伝える。そう、法話である。
「法話において一番大切なことは、話し手が仏法に出遇(あ)った事実や感動、ときには苦悩や悲哀を、具体的に話すこと」(伊藤恵深著『法話のきほん』法藏館)といわれている。
医療者に仏法を伝えようと思えば、医療現場で起こったことから話すのが最も効果的であろう。大阪だけの特殊事情ではないはずである。