





読む
「文化時報」コラム
〈78〉〝普通〟でない人
2025年4月14日
※文化時報2025年1月24日号の掲載記事です。
月に1度開いている地域のよろず相談の場で、先日、お子さんが学校に行かれなくなってしまった方のお話を聴く機会がありました。生まれつきお勉強がしづらい特性をもっているので、それもあいまって、家から一歩も外に出られなくなってしまったそうです。
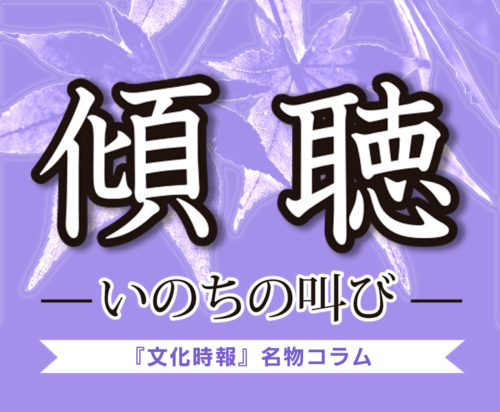
ひきこもるわが子を抱えた母親の気持ちは計り知れません。「こんなふうに生んでしまった私のせい」「決して多くは望んでいない。〝普通〟でいられればいいだけなのに」「かわいそう」。コンクリートの道で転んでできた膝のすり傷のように、心からジワジワと血がにじみ出ているかのようでした。
そのお話を聴きながら、ふと、高校の時に生物の教師が話していたことを思い出しました。
「みなさんは、障害を持った人をかわいそうだとか、気の毒だとか言って、どこか一段下のように見ているのかもしれないけれど、それは違います。いわゆる〝普通〟から外れる個体は、生物学的にある一定数どうしても出現しなければならないものです。誰かが担わなければならないのです。それを、担ってくれているのが、あの方々です。むしろ、彼らによって、私たちはこうして存在させてもらっているのです。だから、〝かわいそう〟ではなくて、〝ありがとう〟と言うべきです」
この話を聞いたとき、自分の頭の中がぐるりと回転するほどの衝撃を受けたことを覚えています。
今、目の前にいるお母さんに、この話をお伝えしたらどうだろう。私の視界が変わったように、この方の視界も変わりやしないだろうか。そして、少しは、楽になってくれやしないだろうか。
結局、言えませんでした。だって、それは、重い荷物を背負い、腰を曲げて、必死で一歩一歩進んでいる人の横に、スッと乗り付けた車の窓を下ろして「ありがとう」って声をかけているようなものでしょう? 「とっとと車を降りて、この荷物を背負ってみろ!」ってことだからです。


