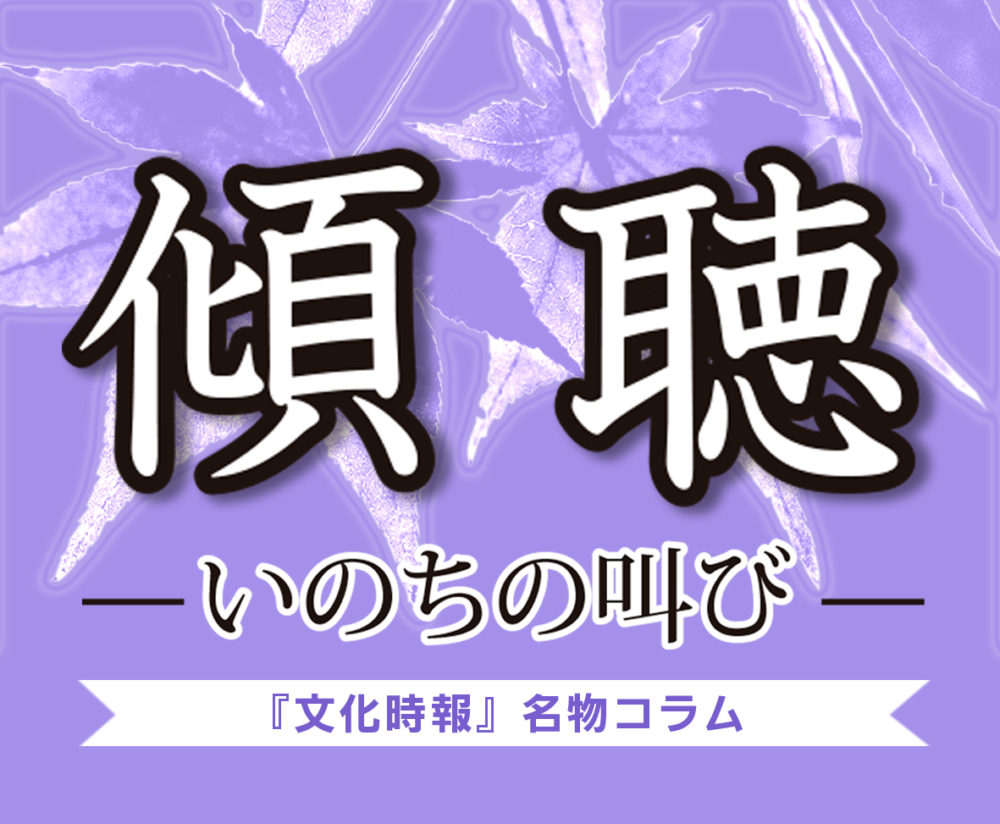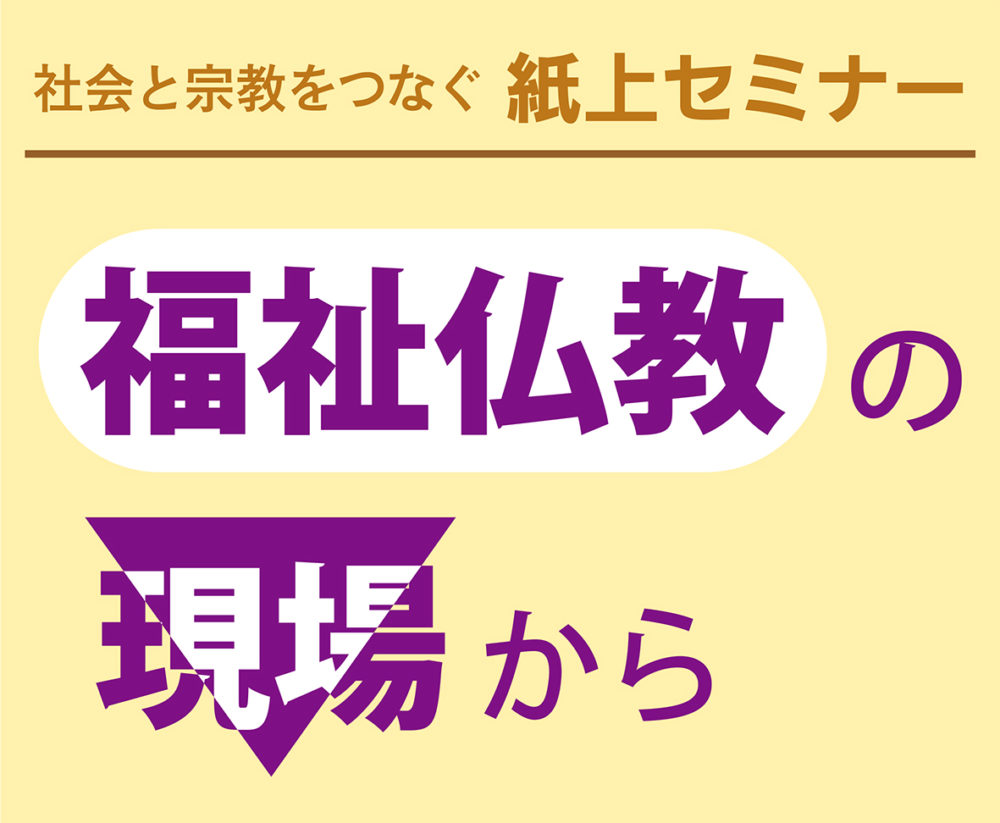読む
「文化時報」コラム
〈80〉春の満月
2025年5月14日 | 2025年5月15日更新
※文化時報2025年2月21日号の掲載記事です。
最近、よく彼女のことを思い出します。
彼女は、医療的マッサージのスペシャリストでした。その確かな技術に救われた人は数知れず、その分野を牽引(けんいん)する先駆者でもありました。さらに、起業家としてもやり手で、東京の一等地にとても雰囲気の良い施術ルームを設け、大いに繁盛していました。
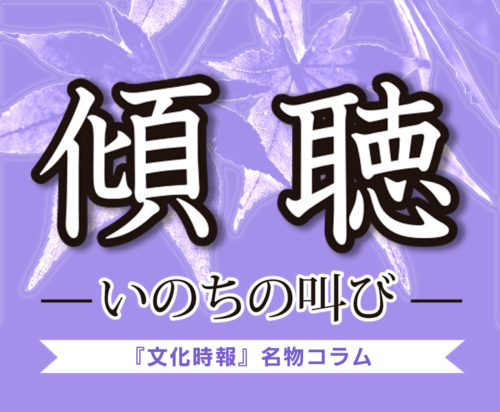
彼女が空に飛んだのは、そんな順風満帆な春の夜だったと、数日後に届いたご子息からの連絡で知りました。「母が、ダイブしました」
彼女とは、同じ医療従事者としての仕事を絡めた付き合いでしたから、私は必要以上に感傷的になる立場ではありません。周りの人たちが口々に、「なにか悩んでいたのなら言ってくれたらよかったのに」「彼女のつらさを察してあげられなかった自分が悔しい」「相談してくれさえしていたらなんとかなったかもしれないのに」と言うのを、どうやってものみ込めない乾ききったパンを口いっぱいにほおばってしまったような気持ちで聞いていました。
違うのではないか、と思ったのです。
彼女は悩んでいたわけでも、つらかったわけでも、相談できなかったわけでもないんじゃないかと。
美人で、スタイル抜群で、頭が良くて、技術も確かで、商売もうまくいっていて、すてきなパートナーがいて。彼女はもう、全てを手に入れていた。これ以上、望むべきものはないくらい、完璧だった。しかも、あとでカレンダーを見返して知ったのですが、あの夜は、満月でした。きっと彼女はあの場所から、満月の光にぼんやり輝く満開の桜を見たのでしょう。完璧なる完全。完全なる完璧。
だからこそ、彼女は、その状態で完了させるしかなかったのかもしれません。
春の満月が近づいてくると、記憶の奥底からそろりと出てくる想(おも)い。
厄介なのは、本当のところはどうだったのかと問い、答えを聞くことができないことです。今は。いずれ会うときも来るでしょうから、そうしたら聞いてみようと思っています。