





読む
「文化時報」コラム
〈81〉祈っている人を見ない
2025年6月4日
※文化時報2025年3月7日号の掲載記事です。
東京の美術館でときどき開催される特別展。彼(か)の地から国宝や重要文化財に指定された仏様方が、一堂にお集まりになります。
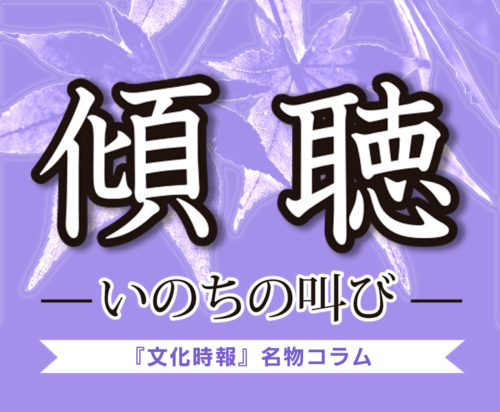
めったにない貴重な機会ですから、そういう特別展には必ず行くようにしているのですが、これまでに「祈っている人」を見たことがありません。どの人もガラスケースに額を寄せて熱心に見入っていらっしゃるのですが、首を垂れ、手を合わせて祈っている人は、ついぞ見たことがないのです。
さて、先日は自分が彼の地に出向いて、小雪の舞う中、6カ寺を巡り仏様方のご尊顔を拝しました。入り口で拝観料を納め、拝観券を片手に床板が鳴く音に耳を奪われながら回ります。寺内は、舞う雪をむしろ風情と捉えたのであろう多くの人でにぎわっていました。
そして、そこにも「祈っている人」はいなかったのです。どの人も、国宝に指定された美術品を熱心に鑑賞する目をしているのでした。
ふと、台湾のお寺の「熱熱鬧鬧」(ルールーナオナオ:ものすごくにぎやかな様子)な活気を懐かしく思い出しました。静寂とは程遠い混沌(こんとん)とした空気の中で、ある人はひざまずき、ある人は叩頭(こうとう)して、口々に祈りの言葉を吐きながら必死に祈っています。全身全霊をかけて、仏にすがりついています。仏様はというと、そんな人々の熱気にもみくちゃにされながら、電飾を背負って、シュッとしています。
活(い)きているんですよね。仏も人間も。生きている。人々は仏を通してその向こうに、先に逝った人の面影を、自分の人生の禍福を、来世への希望を見ています。仏様は、蓮華座(れんげざ)から降りていらして、祈りの間を歩き回りながら、一人一人をしっかりと見てくださっているようです。
彼の地の仏様の向こうに、亡き夫の姿は見えませんでした。荘厳で、ありがたくはあるけれど、温度がない。拝観券を持つ指先は、すっかり冷たくなっていました。


