





読む
「文化時報」コラム
〈83〉恐るべき丹田
2025年7月6日
※文化時報2025年4月11日号の掲載記事です。
先日、名倉幹先生のご指導の下、はじめて「静坐(せいざ)」を体験してきました。
ご存じの方も多いかと思いますが、静坐法とは、大正時代に岡田虎二郎という先生が確立なさったものだそうです。坐禅のような足の組み方ではなく、いわゆる正座の姿勢で静かに坐(すわ)ります。
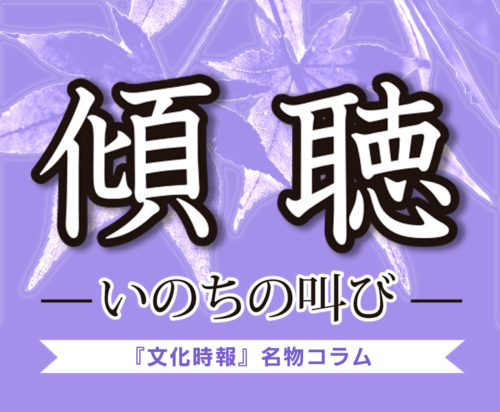
この静坐法には、いくつか独自の大切な要点があるのですが、中でも印象的だったのは「丹田を充実させていく」ということでした。独特の呼吸法に合わせて、丹田に力を込め、一息一息に集中していくのです。
この「丹田」という言葉、実はこれまでにも何度か耳にしたことがありました。
高野山で戒を受けた時、山道で四苦八苦していた私の後ろからひたひたと迫ってきた老僧が「丹田で登れ。足で登ろうとするから登れんのじゃ!」と言い放ち、あっという間に追い越して行ってしまいました。
古式泳法を習っていた時もそう。コツがつかめずばちゃばちゃしていたら、先生からこう言われました。「丹田から全身にエネルギーを回せ。手や足に力を入れるな!」
うーむ。恐るべき丹田。私にはまだよく分からないのですけれど、どうやら確かにあるらしいエネルギーの坩堝(るつぼ)。
もしかすると、人の話を聴く時にもこの丹田、使えるかもしれません。よく「耳を傾けて傾聴する」と言いますが、耳で聞こうとするとついつい分析したり、解釈したり、ジャッジしたり、比べたりしてしまいます。なまじ耳が脳に近いからかもしれませんが、とにかく、ありのままを聴くことが難しいのです。
それなら、丹田で聴く。耳ではなく、丹田で聴く。なんだかものすごく、腹にすとんと落ちそうではありませんか。超安定した聴き方が、そこに生まれるような気がします。
さて、静坐の極意にはもうひとつ「鳩尾(みぞおち)を落とす」というポイントがありまして、これも目からウロコのアメージング体験でした。が、そのお話はまたの機会といたしましょう。静坐。実に奥深い世界です。


