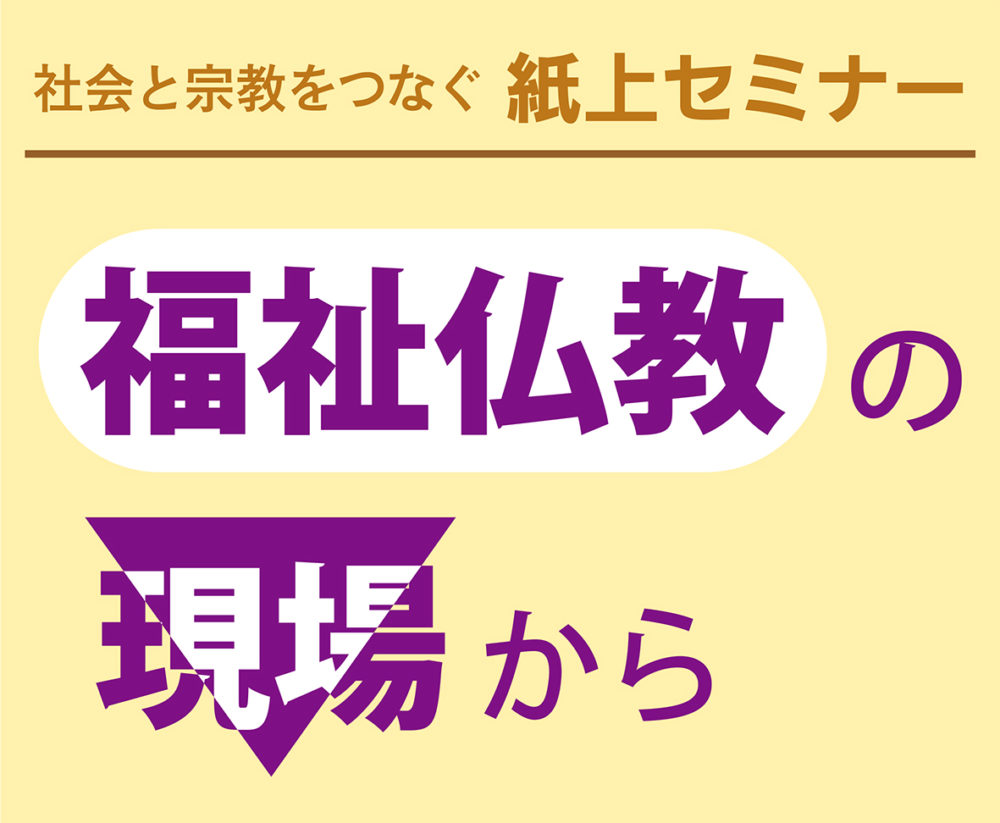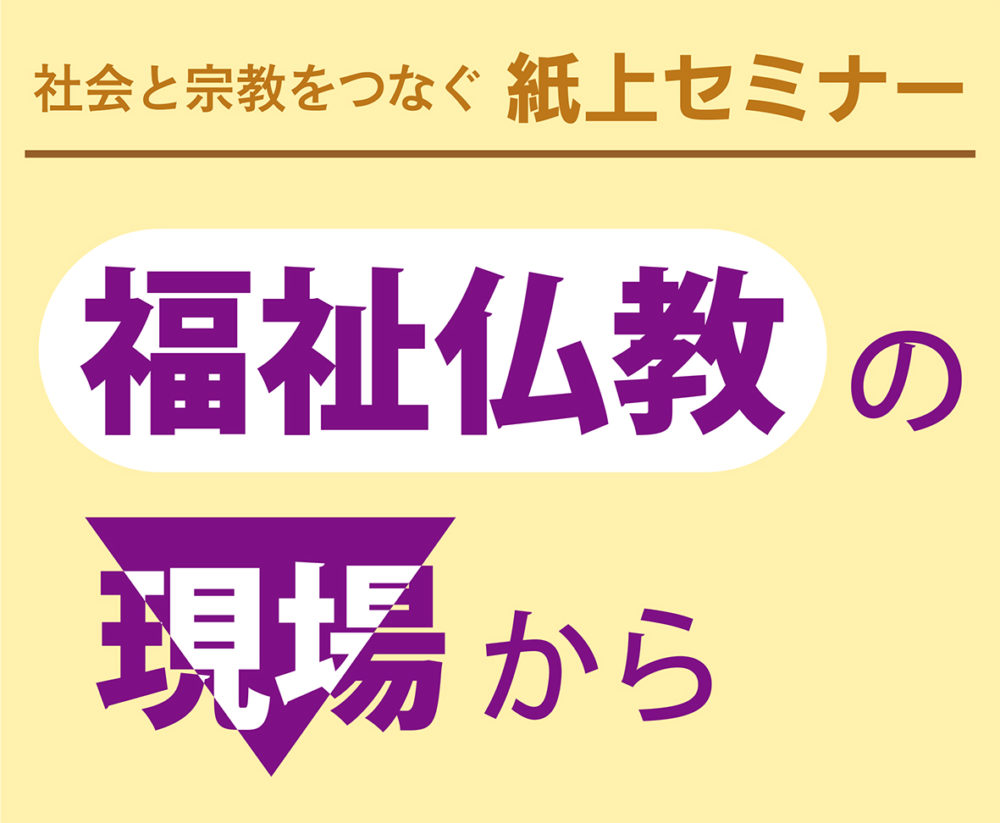読む
「文化時報」コラム
〈67〉比べられる葬儀
2024年2月22日 | 2024年10月2日更新
※文化時報2023年10月24日号の掲載記事です。
身寄りがない人の葬儀が続いている。死亡診断の後、まずケアマネジャーへ連絡が来る病院もあれば、葬儀社へご遺体を預けたと連絡してくる病院もある。そして、ケアマネジャーからお寺へ勤行(読経)の依頼が来るという流れである。大阪市であれば、生活保護を受けている人の葬儀だと、葬儀社が葬祭扶助の中から読経料を包んでくれる場合が多い。
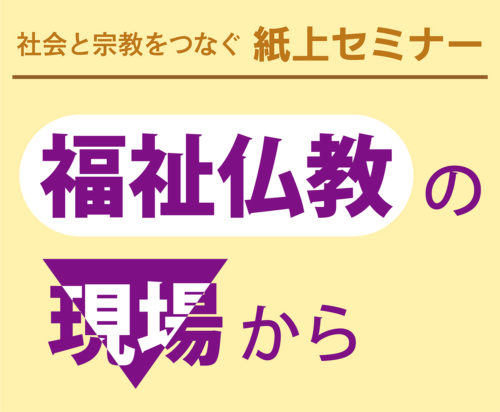
筆者はこういう流れの葬儀を年間10件くらい引き受けている。年々増えてきている感覚がある。大阪市から同じ費用が出ているはずだが、葬儀社によって扱いがまるで違う。一般的な喪家と何ら変わりない丁重な葬儀社もあれば、眉をひそめたくなるような経験をすることもある。
区によっても若干の違いを感じる。病院は身寄りがない患者と扱っていても、葬祭扶助が下りる前に区役所職員が徹底的に親族を捜す。筆者の経験では亡くなってから火葬まで最長1カ月待たされたことがある。特に夏場はご遺体の損傷が激しくなるため、「故人の尊厳を守ってほしい」と市会議員を通じて市に申し入れたこともあるが、なかなか改善されない。
では、お寺の対応に違いはあるのだろうか? ごくたまに他のお寺が勤行する葬儀に参列させてもらうことがある。おそらくだが、どのお寺も丁重な勤行をしているだろうとは感じる。
ただ、法名(戒名)を授けることはないようだ。また、火葬場までは行かないのが一般的になっているようである。
他のお寺がどうしているかを比べるのも、下品な話かもしれない。筆者は、葬儀社が承知してくれれば、通夜・葬儀から炉前まで、全てで勤行する。もちろん、法名も授ける。
良いか悪いかは分からない。しかし、葬儀社の係員は比べているかもしれない。通夜勤行は葬儀社には歓迎されない気はしているが。
身寄りがない人の葬儀は今後ますます増えるだろう。こんなところにも福祉仏教はある。