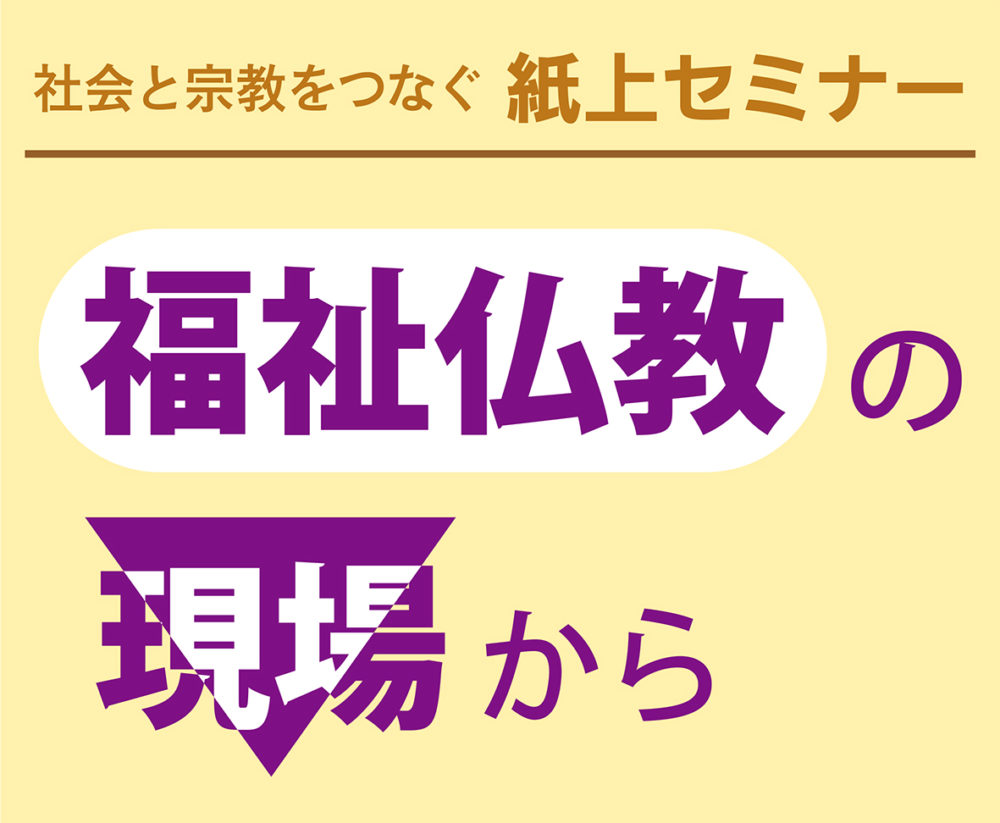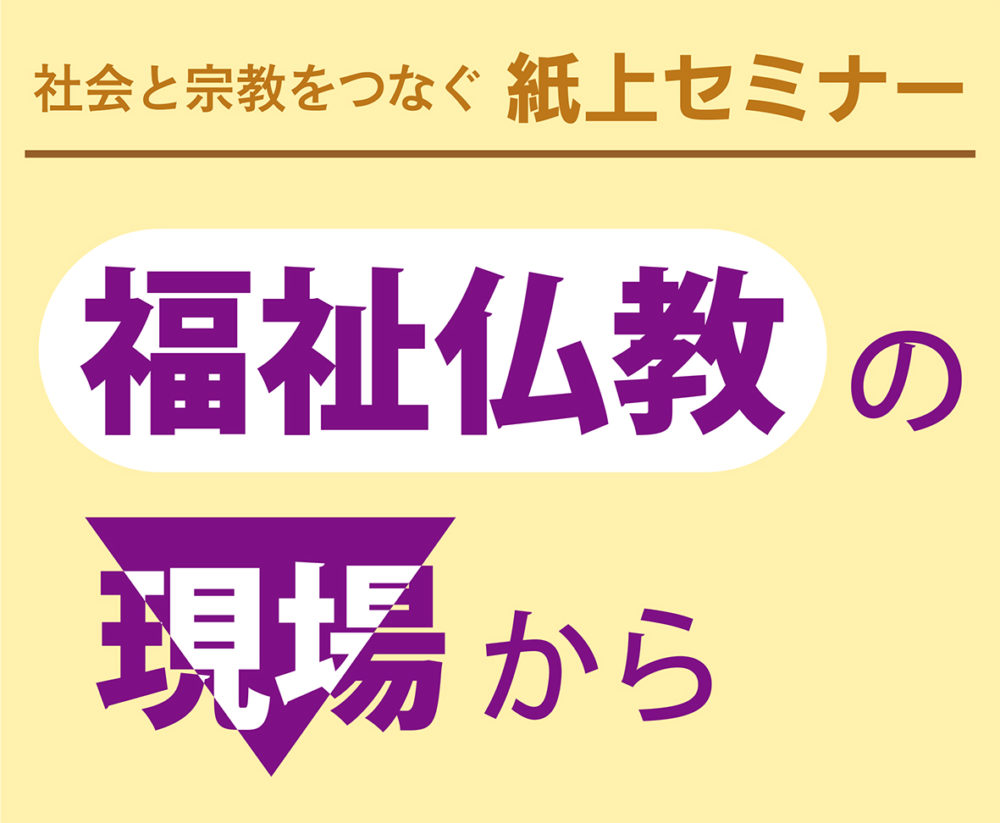読む
「文化時報」コラム
〈85〉聞法道場の未来
2024年10月13日
※文化時報2024年7月30日号の掲載記事です。
一般財団法人安住荘は1974(昭和49)年7月24日が法人成立の日として登記されている。
ところが不動産関係の書類を見ると、それ以前の日付で個人から財団法人への寄付があったと記されている。引き継ぎを受けた者としては、できるだけ事実に近いことを後世に伝承していきたいと考える。
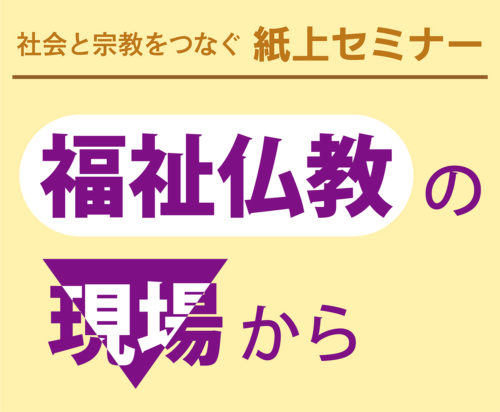
現在の安住荘の土地建物は、故内山宗一氏が個人所有していたものを財団法人に寄付した。その後、ご子息の宗之氏が引き継いで聞法道場を護(まも)ってこられた。
先日、創立者である宗一氏の二十七回忌法要が、妻清子氏の十七回忌を併修する形で安住荘にて勤められた。施主となった宗之氏は、法要の案内文に「安住荘は建て替えられるのでこれが見納めとなる」という一文を入れていた。
法要当日、たくさんの親族や有縁の人が集まってこられた。安住荘を建て替える責任者として、筆者が皆さまにごあいさつと説明を行った。
「建物の姿は変わりますが、安住荘が建設された『佛法ひろまれ』の願いは、これから先も変わらず継承されていきます」
お寺はこのようにして100年、千年という長い時間を継承されてきたのだとしみじみ感じた。
現在、全国各地の多くのお寺が葬儀および先祖供養に関連した寄付を経済基盤にしていることだろう。それはおそらく江戸時代にルーツがあり、明治政府が用いた「家長制度」によって支えられてきたものであろう。
しかし、社会は「家」に対する概念が変化してきている。お寺を存続していくには、揺らいできた経済基盤を立て直す必要がある。
安住荘の建て替え工事は来年始まる。費用は億単位となる。原資は福祉事業から捻出する。これは筆者が提唱を続けてきた「福祉仏教」を具現化したものになる。
聞法するのにお金は必要ない。聞きたい時に気軽に集まることができる場にする。檀家になる必要もない。安住荘は全ての人に開かれている。専従の管理者として真宗大谷派僧侶を置く―。
それらを宣言するために年忌法要の時間を少し頂いた。けじめのつもりであった。