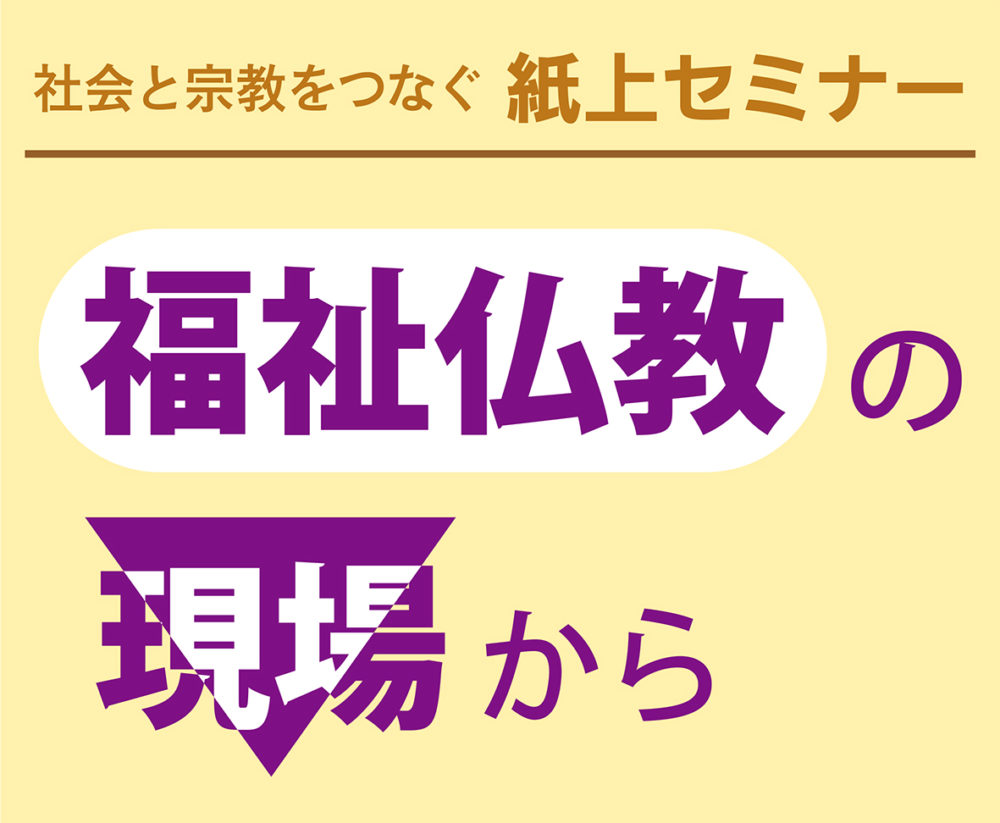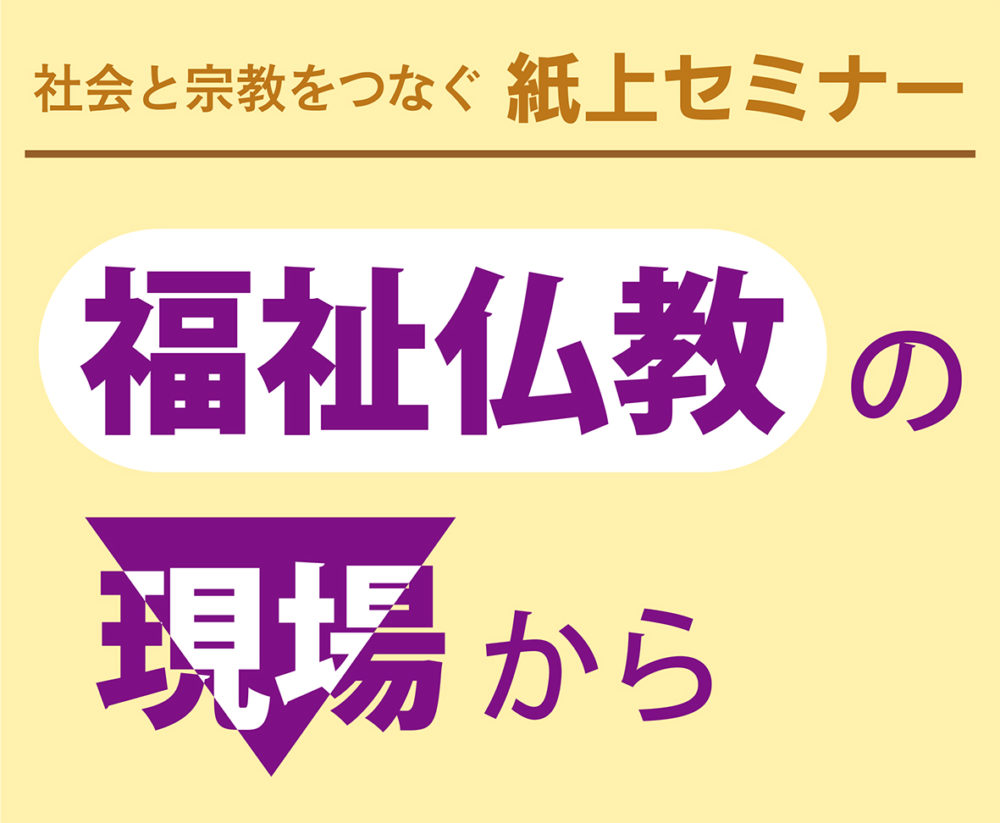読む
「文化時報」コラム
〈89〉お寺に集まる意味
2024年12月6日 | 2025年2月12日更新
※文化時報2024年10月1日号の掲載記事です。
彼岸の中日、兵庫県宝塚市の真言宗大覚寺派成福院で「親あるあいだの語らいカフェ」が初開催された。一般財団法人お寺と教会の親なきあと相談室の18ある支部の一つを設けている。生きづらさを感じている当事者さん、発達障害のお子さんがいる親御さん、8050問題=用語解説=真っただ中で藁(わら)をもつかむ気持ちで来てくださった高齢の方。さまざまな方々がお集まりくださった。
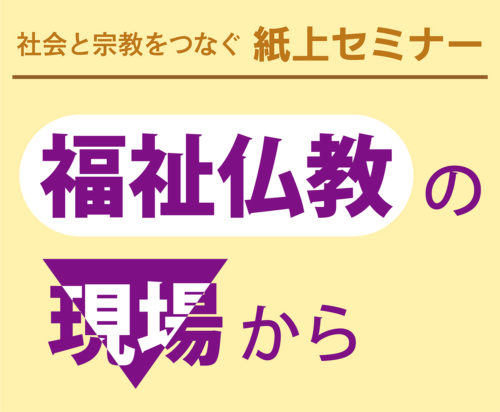
ご自身が抱えている苦しみや前向きに取り組んでいる話などを、参加者の多くは饒舌(じょうぜつ)に語った。利害関係なくフラットな状態で吐き出せる場の重要性を改めて感じた。初めて訪れる場であっても、そこがお寺であることの安心感を何人もが口にしていた。
本堂が檀家さんではない人たちで埋め尽くされている光景を想像していただきたい。確実にお布施を頂ける法要とは趣旨の違う集会に、本堂を使われることに抵抗がある寺院関係者は多いと思う。
一方、人が苦悩を吐き出すのに対価を払うことが必要なんだろうか?とも思う。
もちろん、長い歴史でお寺が伝えてきた教えや、集まった人々が聞いてきた教えは、そんなに軽いものではないはずである。そうであるからこそ、堂々と「布教」すればいいと筆者は考えている。
苦悩を抱えてお寺に来る人々は、医療からも行政からも見放されたと感じている場合が多い。医療も行政も、人間が社会生活を営むために必要なシステムだろう。
しかし、「思い通りにならない老病死」という現実は変わらない。そこに直面している人々に仏教を伝えずして、お寺といえるだろうか?
もちろん伝え方に工夫は必要となる。檀家さんと同じようにはいかない。ただ、筆者は強く思う。お寺に集まってくる人に「布教しません」は違うと。
成福院さんに初めて来たという参加者のお一人がこう言った。
「公民館ではなく、お寺に集まる意味が来てみて分かった」
【用語解説】8050問題(はちまるごーまるもんだい)
ひきこもりの子どもと、同居して生活を支える親が高齢化し、孤立や困窮などに至る社会問題。かつては若者の問題とされていたひきこもりが長期化し、80代の親が50代の子を養っている状態に由来する。