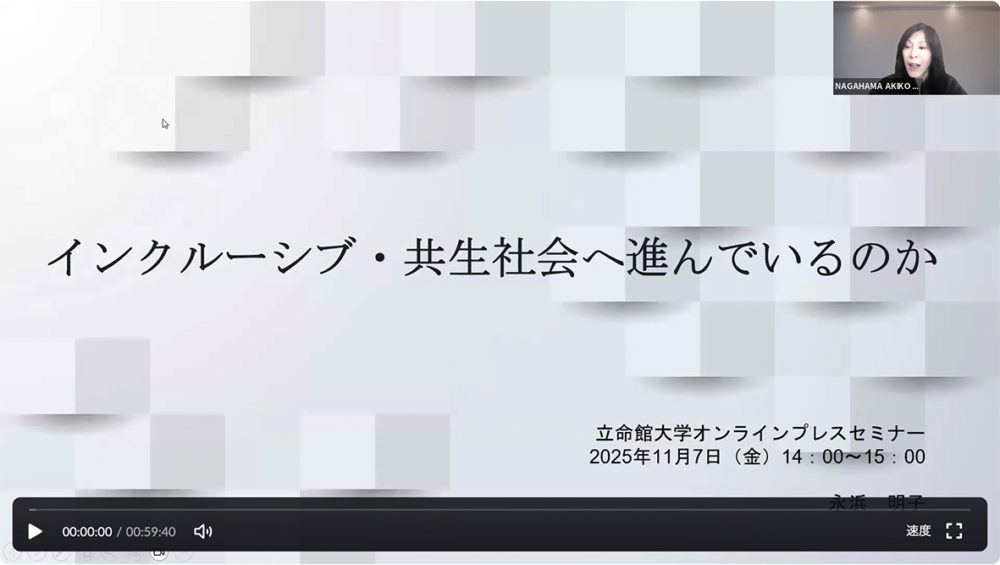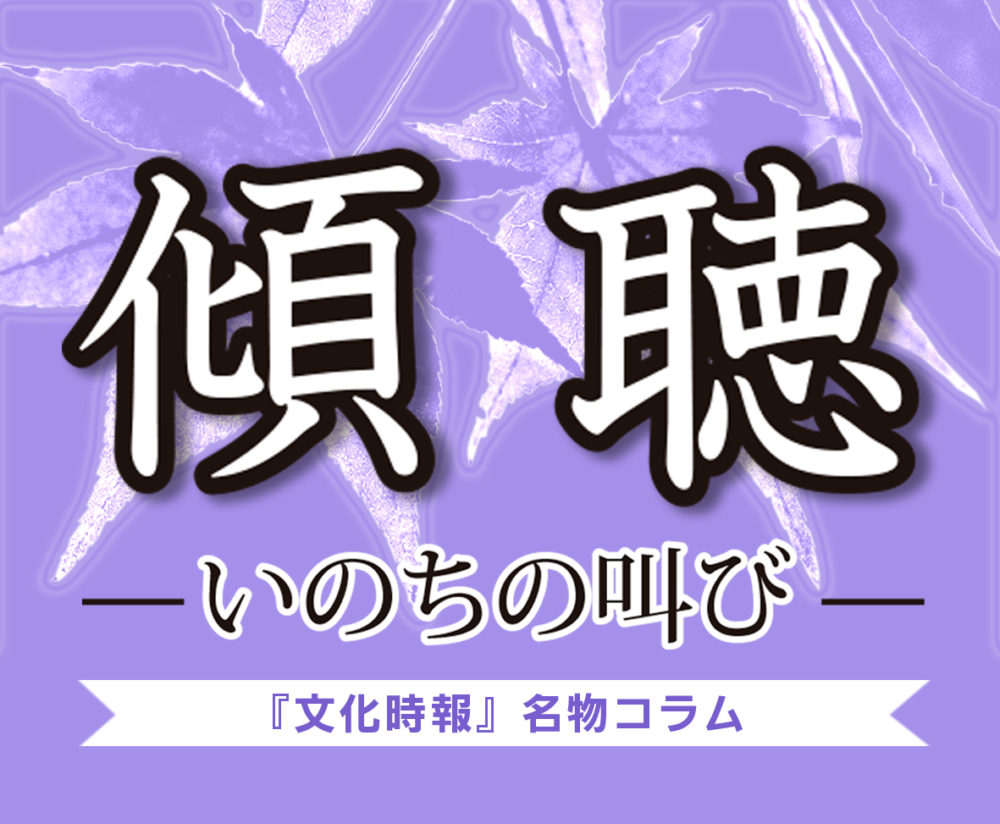インタビュー
橋渡しインタビュー
テレジン収容所の幼き画家紹介 野村路子さん
2024年3月22日 | 2025年1月29日更新
第2次世界大戦中、チェコ北部に「アウシュビッツへの控え室」と呼ばれたテレジン収容所があった。ユダヤ人の子どもたち約1万5000人が親から離され、子どもだけの建物で暮らし、わずかな食事しか与えられず、慣れない労働を強いられた。体が弱ったり、病気になったりした子は「労働力」として役に立たないと、貨物列車に詰め込まれてアウシュビッツへ送られていた。子どもたちはみな死への不安とつらい日常に絶望的になっていた。そこに現れた女性画家フリードル・ディッカーが子どもたちに絵を教え、生きる希望を与えたという。ノンフィクション作家の野村路子さん(84)はチェコ・プラハを旅行中、テレジンの子どもたちの絵と出会ったことで運命が変わった。1989(平成元)年から35年間にわたり、日本全国で展覧会を開催。当時の生還者との交流も果たした。
学校図書株式会社が発行する小学6年の国語教科書には、野村さんが書き下ろした「フリードルとテレジンの小さな画家たち」が収録されている。野村さんは、小学生の感想文を大切に読んでいる。

1937(昭和12)年、東京生まれ。小学2年の時に東京大空襲で家を失った。幸い家族は無事だったが、疎開先で感じた差別や偏見を今でも思い出すという。
早稲田大学仏文科卒業後、国家公務員となり、結婚後はコピーライターとして働いた。子育てをしながらタウン誌の編集長を務め、弁護士だった父親の勧めもあり家庭裁判所の調停委員をしていた。
多忙な中だったが、次女の麻紀さんが大学を卒業する際、記念として一緒にヨーロッパを旅行した。親子でまず訪れたのは、ナチスドイツによる悲劇を生んだアウシュビッツだった。
一見すると大学のキャンパスにも見えるというレンガの外観。誰もいない重々しい雰囲気の中、虐殺された人々の大量の髪の毛や衣類品を目にした。死を思わせる空間が至る所にあり、親子で肩を寄せ合いながら歩いた。
「娘は生まれた時から体に異常があって、18歳までしか生きられないと言われていましたが、大学を卒業する年齢にまで成長しました。16歳で死んだアンネ・フランクよりも長生きし、『無事に生きてこられてよかったね』と、娘にこの場所で伝えたかったのです」
だが実際には伝えられなかった。それ以上に戦争の傷ましさや悲惨さが身に染み、簡単に「生きていてよかった」と口に出せないまま、チェコ・プラハへと移動した。
ダビデの星と子どもの絵
偶然にも、訪れた日は「社会主義宣言記念の日」だった。街は赤旗とデモ隊で埋め尽くされ、観光どころではなかったという。
諦めてホテルに戻ろうと路地に入ると、ユダヤ人墓地の横に小さな建物があった。何となく足を踏み入れると、そこには子どもが描いたと思われる絵が展示されていた。
明るい色合いの子どもらしい作品を眺める中、1枚の衝撃的な絵が飛び込んできた。
「それは、ダビデの星を付けた人間が首つりされる場面の絵でした。どうしても気になって、次の日に現地で歩く人に声をかけ、英語を話せる人を探して聞いてみたのです。『あそこに行けば分かるかも』と連れて行かれた事務所で、手に入れたのが薄い1冊のパンフレットでした」
チョウが飛んでいる子どもの絵が表紙になっていた冊子。開くと、英語はなくフランス語で書いてあった。野村さんはホテルで徹夜し、フランス語の辞書を引きながら調べ上げた。

大学時代に学んだフランス語のおかげで分かった事実。それは、チェコ北部にあるテレジン収容所に収容されていた子どもたちの絵だった。
子どもたちに絵を描かせたのは、フリードル・ディッカーという女性だった。美術教育に高い関心を持ち、画家として活躍していた彼女もユダヤ人だった。その後、テレジンからアウシュビッツへ送られてしまったという。
野村さんは帰国後、自ら在日チェコスロバキア大使館へ行き、日本でテレジンの子どもたちが残した絵の展覧会を開催したいと直談判した。
当時は平成初期。メールも携帯電話もない時代に、高額な国際電話と手紙のやり取りを重ね、再びチェコに行ってユダヤ博物館で交渉を進めた。

戦後発見された約4000点もの絵から、150点を展示したいと申し出た。実際の絵は元々ドイツ兵の捨てた紙などを拾い集めたものに描かれており、かなり劣化しているため、国外へ出すのは難しいとのことだった。両手で持たなければ崩れてしまうようなものもあった。改革直後のチェコではフィルムは手に入らず、日本からフィルムを運んで撮影してもらうことになった。
「一緒に日本に連れていくからね。たくさんの方に見てもらおうね」
野村さんは作品を見ながら思わず声をかけた。展覧会開催の費用がどうなるか不安はあったが、絵や子どもたちを裏切れない―。そんな気持ちが心を熱くした。
費用は周囲からの協賛で工面した。野村さんが書いたエッセー『アンネへの手紙』の出版後、日経新聞に掲載された文章を当時の安田火災海上保険の社長が目にして、スポンサーになってくれたという。
生き残った者のつらさ
テレジン収容所ではたった100人の子どもたちが生き残った。野村さんは生還者を探して何度も手紙を書いた。そのうちの7人と直接会って話ができたという。
今でも交流があるのはディタ・クラウスという女性だ。現在94歳となり、イスラエルのナターニアという街で、花の絵を描きながらアマチュア画家として制作を続けている。とても悲惨な戦争体験したとは思えないほど、心和ませる絵を描いていた。

ディタさんの左腕には73305という番号の刺青が残っている。テレジンからアウシュビッツに送られ、ガス室の手前まで行って生き残った証拠だ。
「私はディタの刺青を見て、何も言えませんでした。彼女は笑顔で話し、最後に自ら腕を見せて写真を撮らせてくれたのです。シャッターを押すのに勇気が入り、3枚ほど撮りました。現像してからわかったのですが、彼女の顔はとても悲しそうにうつむいていました」
ディタさんは戦後、孤児院で暮らした。10代で亡くなった友達の兄と再会し結婚。夫と共に懸命に働き、いまいましい収容所生活については口にせず、長年心にふたをしてきた。
だが、野村さんの活動や思いを知って自分の過去と向き合い、勇気を出して胸の内を話してくれたのだった。

「ディタがあの収容所で明るい絵を描けたのは、フリードル先生の教育があったから。子どもたち一人一人を名前で呼んでくれて、唯一楽しい時間だったと話していました」
また、ディタさんは東日本大震災のニュースを見て心を痛めたという。福島や岩手の避難所で、元気に駆け回る子どもたちの映像。親や友達を亡くした子が大勢いるのに、涙を流さず過ごす様子が海外メディアでも報道された。
だが、生き残った者のつらさを、ディタさんは痛いほど知っている。居ても立ってもいられず野村さんに連絡し、プラハに呼び寄せた。
ディタさんは震災で被災した子どもたちと、収容所にいた自分が重なると話し始めた。被災した子どもたちにぜひ伝えてほしいと、野村さんにこう告げた。
「自分だけが生き残るのは本当につらいこと。でも、生き残ってよかったのです。亡くなった人の分まで幸せになってね。亡くなった人は、幸せになってほしいと望んでいるのだから」
ディタさんは戦争で家族を全員殺された。自分が幸せになることを何十年も罪のように感じていたが、夫から亡くなる寸前に聞いた「幸せになっていいのだよ」の一言で、生還者として生きてきた自分を受け入れようとした。

たとえ短い生涯でも、生きた証しを残したテレジンの子どもたち。一瞬でも笑顔になれた時間を過ごせたのは、フリードル以外にも命懸けでドイツ兵に「絵の教室」を開かせてくれと頼み込んだ人や、紙を拾い集めたり、子どもたちに生きる希望を与えようとした大人たちがいたからだ。
「大人は次世代に生きる子どものために頑張らなくていけない」と、野村さんは話を締めくくった。
茶色くなった紙にはカラフルな花やチョウ、三角屋根の家、遊園地で遊ぶなどした懐かしい日々が描かれている。そんなかわいらしい純粋な絵から伝わる壮絶な悲しみと生きる大切さを、テレジンの子どもたちが今日も訴えかけている。