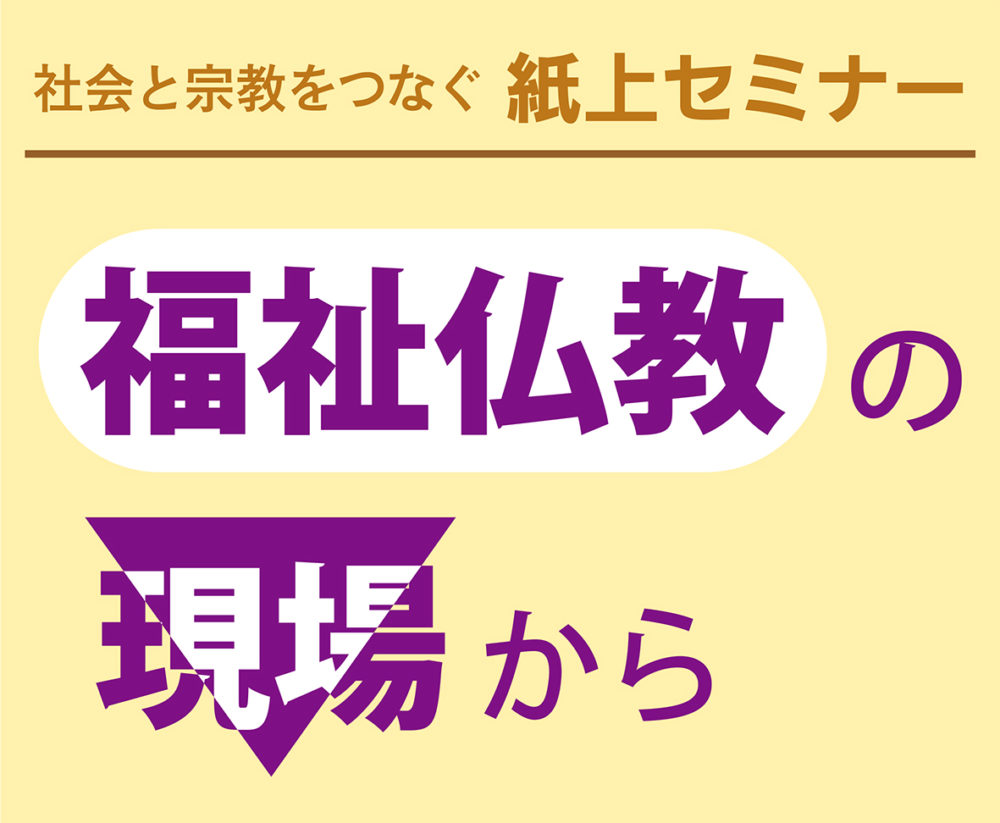インタビュー
橋渡しインタビュー
ケアラーとして伝えたいこと 友田智佳恵さん
2024年5月6日
東京都の友田智佳恵さん(32)は小学6年生の時に母親が突然、くも膜下出血で倒れた。母は一人で過ごすことが難しくなり、日中はデイサービスを利用するなど生活が一変。友田さんはヤングケアラーになった。高校卒業後、若くして結婚・出産を経験し、6年前までは認知症の祖母の介護も行っていた。現在も子育てと母の介護を担う「ダブルケアラー」として日々を送る傍ら、一般社団法人ケアラーワークス(東京都府中市)のスタッフとして講演活動を行っている。
ヤングケアラーとは、障害や病気のある家族の家事や世話、感情面のサポートなどを、大人の代わりに日常的に担っている18歳未満の子どものことをいう。
子どもにとって、家族のケアをすることは決して悪いことではない。だが、家の中で親や小さな兄弟の世話を日常的に続けることは容易ではなく、場合によっては子どもが背負うには負担が大きすぎて、責任も重すぎる。

誰にも話さず母を介護
今から20年ほど前、友田さんが小学6年生の時のこと。「頭が痛い」と母親が訴え、父親が病院へ連れて行ったところ、くも膜下出血と診断された。
8時間に及ぶ緊急手術で一命は取り留めたが、右片のまひと高次脳機能障害が残った。退院後は歩行の補助、着替え、排泄(はいせつ)などの介護が必要となった。
当時、家族は友田さんを含め、父、母、兄、祖父母の6人暮らしだった。
中学校に入ると、友田さんの生活は他の同級生と比べ、独特になった。朝は自分の身支度以外に、母を起こし、着替えを手伝い、デイサービスへの送り出しまで行う日もあった。そこからようやく登校。雨の日は送迎車が遅れがちで、授業に遅れることがたびたびあったそうだ。
学校の配慮で、デイサービスの送り出しで間に合わない日は遅刻扱いにはならなかった。だが、それ以外のことは担任に相談することはなく、他の生徒と同じように過ごしていた。

「この年齢で、親の介護をしているのは自分だけ。そう思うと、周りに話す気になりませんでした。学校が唯一、13歳の自分が自分として過ごせる貴重な場所でしたから」
熱心に勉強し、生徒会にも立候補。部活で結果を残し、塾の先生にも褒められた。周りから見れば、何の問題もない優等生だった。自分の力を発揮し、将来の可能性を狭めたくないと思ってのことだった。
しかし家に帰れば、夕方から母の世話が待っていた。父が仕事から帰ってくるまでの間は、そばに寄り添い続けた。
フィリピン人の母は20代半ばで日本へやってきた。やがて夫となる友田さんの父と出会い、結婚。日頃から親子での会話やスキンシップの多い、家族愛を大事にする人だったという。
愛情を一身に受けて育った友田さんは、子どもながらに精いっぱい、母の介護に徹した。だが、進路を決める際に憧れていた私立高校への受験を断念せざるを得なくなった。
「経済的にも余裕があるわけではなく、受験は思うようにいかなくて、公立高校へ入りました。希望した学校ではなかった時に『もし母が倒れていなければ、私の生活は違ったかもしれない』と初めて思いました」

当時の友田さんを支えたのは、ラジオや音楽。電波に乗せて、同世代のリスナーたちが悩みを投稿していた。自分以外にもたくさんの人たちが、周りに話せない悩みや思いを抱えている。そう感じながら、静かに思いを共有した。音楽を聴くときは、受け入れ難い現実や自分の心情を曲に重ね、励まされることもあった。
適切な支援ができる世の中になるために
現在は夫と2人の子ども、父母と同居している。ダブルケアラーとして、慌ただしい毎日を送るが、その中で尽力するのがヤングケアラーに関する講演・支援活動。行政や民間企業などで、実体験を素直に伝えている。

活動を続けていて、当事者の声を発信する重要性を感じるようになったという。
最近は、埼玉県内の小中学校・高校で開催されている県教育委員会の「ヤングケアラーサポートクラス」で、教職員や児童・生徒、保護者を前に出張授業を行っている。
「ヤングケアラーの割合は1クラス30人ほどの中で1人か2人といわれています。現在はヤングケアラーの状況になくても、超少子高齢化の日本で生きていると、介護やケアに関わる確率はこの先ずっと高くなると想像します。教育の中で介護・ケアの学びは必須と考えますし、直接携わらなくても、社会で高齢者やケアを必要とする人を支えていくことに変わりはありません。知識や情報が少しでも入っていたら、いざという時に適切な支援につながることができると考えます」
遊びたい、学びたいという10代のころに、家族の介護で自分の時間を制限された友田さん。いつも学校では笑顔だったが、感情にふたをしてなんとかやり過ごしていた。本音を言えば、思春期や青春時代をもっと「自分らしく」生きたかった。
「ヤングケアラーだけでなく、世の中にはいろいろな境遇の子がいます。必ず乗り越えようと思う必要はないですが、自分の人生を否定しないでほしい。私も年月を重ねる中で、自分や家族に起きる出来事の意味付けが変わっていきました。今の自分を大切にして生きてもらえたらと願っています」
目の前で困っている子どもを救うことや理解を求めることだけが目的ではない。長い目で、ヤングケアラーへの支援を続けてもらうために、スピーカー役に徹するつもりだ。